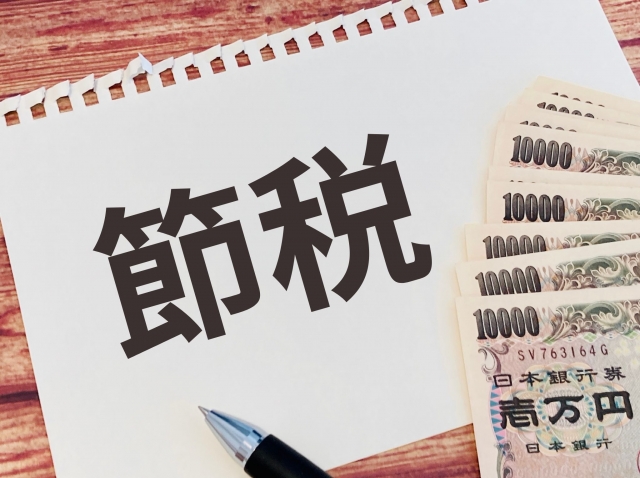個人事業主が法人成りする8つのメリット
法人成りには税制面だけでなく、経営の幅を広げるメリットがあります。
個人事業主が法人成りするメリットは次のとおりです。

- 税金が減る可能性がある
- 資金調達の選択肢が増える
- 損失を最大10年間繰り越せる
- 経費になる範囲が増える
- 消費税が最大2年間免除されるかもしれない
- 社会保険に加入できる
- 事業承継がスムーズになる
- 決算月を変更できる
順にみていきましょう。
税金が減る可能性がある
個人事業主が法人化すると、所得にかかる税金の仕組みが変わります。個人事業主は「所得税」が適用され、所得が高くなるほど税率も高くなる累進課税制度(最高45%)が採用されています。一方、法人は「法人税」が適用され、利益に対する税率が一定(中小法人の場合は最大でも23.2%)のため、利益が大きくなるほど法人のほうが有利になります。
また、法人では自分に「役員報酬」を支払うことができ、経費として計上できます。さらに、家族に役員報酬を払って所得を分散すれば、家族全体での税負担も軽減できる可能性があります。
法人成りが節税になる理由を詳しく知りたい場合はこちらの記事をあわせてご覧ください。
関連記事:法人成りが節税になると言われる理由は?節税にならないケースと失敗しないためのポイント
資金調達の選択肢が増える
法人になると「株式」を発行して出資を募ることができるようになります。株式は個人事業主にはない資金調達手段です。
たとえば、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家に株式を引き受けてもらうことで、銀行融資に頼らずに多額の資金を確保することが可能です。株式を通じた出資であれば、返済義務がないため、資金繰りの負担も軽減されます。
将来的に事業を拡大したいと考えている方にとっては、法人化することで多様な資金調達の選択肢が増えます。
損失を最大10年間繰り越せる
事業で赤字が出た場合、その損失(欠損金)を翌年度以降の黒字と相殺できる「繰越控除」という制度があります。
個人事業主(青色申告の場合)は赤字を最長3年間しか繰り越せません。しかし、法人であれば最長10年間も繰り越すことができます(2025年現在)。
たとえば、創業初期に赤字が続いても、その分を後の黒字と相殺できるため、法人化しておくことで中長期的な税負担を抑えられるのです。
参考:国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
参考:国税庁「青色申告制度」
経費になる範囲が増える
法人になると、経費として認められる範囲が個人より広くなります。
たとえば、社長本人に支払う「役員報酬」や、社宅制度を使った住居費の一部、社用車の維持費、福利厚生費、生命保険料なども、条件を満たせば経費として処理が可能です。
個人事業主の場合、家事関連費(プライベートとの区別が難しい支出)は経費できませんが、法人であれば「業務に必要」と認められる支出の幅が広がります。経費が増えることで、最終的な課税所得が減り、法人税の負担を抑えることができます。
消費税が最大2年間免除されるかもしれない
新たに法人を設立した場合、期首の資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税が免除されます。「消費税の免税事業者」になるためです。
個人事業主で消費税を納めている場合でも、法人として新たにスタートすれば、再び免税期間が適用される可能性があります。特に、個人事業での売上が1,000万円を超えている方が法人成りする場合、「適切なタイミング」で法人化すれば、消費税の納税を先送りできるというメリットがあります。
ただし、課税事業者である個人事業主が法人成りをする場合、個人事業で使っていた資産を新たに設立した法人に売却する場合、売却資産に対して消費税を支払うことになるため注意が必要です。
法人成り後の消費税の免除期間を長くするポイントを知りたい場合はこちらの記事を参考にしてください。
関連記事:法人成りすると消費税の免除がなくなる?免除期間を長くするポイントと個人事業主への影響
社会保険に加入できる
法人を設立すると、代表者1人でも社会保険への加入が義務になります。社会保険に加入することで得られるメリットは以下の通りです。
- 老後の年金が手厚くなる(厚生年金)
- 病気やケガの時の保障が充実(傷病手当金・出産手当金など)
- 将来の介護や遺族への保障もカバーされる
また、個人で国民年金・国民健康保険に加入するよりも、法人で厚生年金・協会けんぽに加入する方が保障内容が豊富で、万が一のときにも安心です。
社会保険料は会社と本人で折半して負担する仕組みですが、役員報酬額によって金額は変わります。報酬を抑えれば、負担も軽くなります。
1人社長の社会保険料の計算方法はこちらの記事に詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:1人社長の社会保険料はいくら?具体的な計算方法と役員報酬8万円の社会保険料の金額
事業承継がスムーズになる
法人化しておくと、事業を後継者へ引き継ぐ際の手続きが簡単になります。
個人事業主の場合、事業用資産・契約・口座・従業員との関係などをすべて個人から個人へ引き継ぐ必要があります。そのため、時間も手間もかかり、トラブルの原因となるかもしれません。
一方、法人であれば、会社の株式を譲渡するだけで事業全体をまとめて承継できます。代表者が交代しても、会社名や取引先との契約などはそのまま継続できるため、円滑に事業を引き継ぐことが可能です。
特に、家族や社員への承継、第三者へのM&Aを視野に入れている場合は、早めの法人化が有利です。
関連記事:京都の後継者不足の現状は?放置するリスクと事業承継で税理士が果たす役割
決算月を変更できる
個人事業主は毎年1月〜12月が事業年度と決まっていますが、法人であれば自分で自由に決算月を選べます。
決算月を自由に変更できることにより、以下のような調整が可能になります。
- 繁忙期を避けて決算業務の負担を軽くする
- 利益の出やすい時期に合わせて節税効果を高める
- 売上や設備投資のタイミングに合わせて最適な利益コントロールができる
また、設立のタイミングと決算月を上手に組み合わせることで、消費税の免除期間を実質的に延ばす工夫も可能です。こうした調整によって、キャッシュフローの改善や税金対策がしやすくなるのも法人ならではのメリットです。
ここまでご紹介したように、法人化にはさまざまなメリットがあります。ただし、適用条件やタイミングによって、得られる効果は変わってきます。
法人化するタイミングを詳しく知りたい場合はこちらの記事をあわせてご覧ください。
関連記事:法人化するタイミングは何月がいい?おすすめしない月と月の途中で法人成りするときのポイント
私たち石黒健太税理士事務所では、個人事業主の法人成りに関するご相談を受け付けております。税務のシミュレーションはもちろん、社会保険・資金調達・事業承継のことまで、あなたに最適な法人化の形をご提案できます。
「法人にしたほうがいいのか迷っている」「今のタイミングでいいのか不安」という方も、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。あなたの一歩を、私たちが全力でサポートします。
個人事業主が法人成りするデメリット
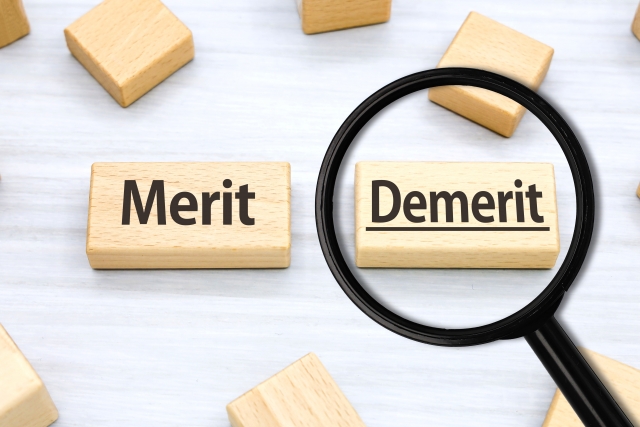
法人化には多くのメリットがありますが、その一方で注意すべきデメリットも存在します。法人成りを検討する際に知っておきたいデメリットは次のとおりです。
- 設立費用がかかる
- 社会保険への加入が必須になる
- 赤字でも均等割を支払う必要がある
- 役員報酬を毎月自由に変更できない
- 確定申告が複雑になる
順にみていきましょう。
設立費用がかかる
法人を設立するには、まず初期費用がかかります。たとえば以下のような費用が必要です。
|
項目 |
株式会社 |
合同会社(LLC) |
|
登録免許税 |
15万円(最低) |
6万円 |
|
定款認証代 |
約5万円 |
不要 |
|
定款印紙代 |
4万円(※電子定款なら0円) |
4万円(※電子定款なら0円) |
|
合計の目安 |
約20〜25万円 |
約6〜10万円 |
株式会社の方が知名度や信用力は高い一方で、設立コストは割高になります。事業の規模や目的に応じて、会社形態を選ぶことが大切です。
合同会社と株式会社の違いは、こちらの記事でくわしく紹介しています。自分に向いている会社形態を知るためにぜひご覧ください。
関連記事:合同会社と株式会社の違いは?向いている会社形態と会社設立で失敗しないためのポイント
社会保険への加入が必須になる
法人を設立すると、従業員がおらず、役員1名のみでも社会保険への加入が義務になります。
個人事業主は、従業員が5人以上いる場合に社会保険への加入が義務になりますので、従業員の人数によっては社会保険への加入が不要です。
|
加入要件 |
個人事業主 |
法人 |
|
社会保険の加入 |
従業員が5人以上いる場合(※一部業種を除く)に義務 |
役員1人でも原則強制加入 |
個人事業であれば少人数の運営では国民健康保険・国民年金で済みますが、法人では必ず健康保険+厚生年金に加入する必要があります。保険料の負担が増える点に注意しましょう。
赤字でも均等割を支払う必要がある
法人は、利益が出ていなくても「法人住民税(均等割)」という最低限の税金を支払う義務があります。均等割は赤字でもかかる税金と覚えておきましょう。
均等割の金額は自治体によって多少異なりますが、資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人の場合、一般的には年間7万円前後が目安です。
個人事業主の場合、赤字であれば所得税や住民税がかからないこともありますが、法人は「法人であること」によって最低限の税負担が発生する点を理解しておきましょう。
役員報酬を毎月自由に変更できない
法人では、役員に支払う報酬は「定期同額給与」のルールが適用されます。定期同額給与は、毎月同じ金額で支払うことが原則で、簡単に変更できない仕組みです。
たとえば、「今月は売上が少ないから報酬を下げよう」といった調整が原則としてできません。期の途中で金額を変更すると、その報酬が損金(経費)として認められない可能性があります。
役員報酬は、期首(事業年度の開始後3ヵ月以内)に金額を決めて、安易に変更しないことが基本となるため、事前に資金繰りや利益計画を立てて設定することが重要です。
役員報酬の相場を知りたい場合はこちらの記事を参考にしてください。
関連記事:中小企業の役員報酬の相場は?役員報酬が高すぎる中小企業の注意点と手取りをシミュレーション
確定申告が複雑になる
個人事業主の確定申告は、比較的シンプルな「所得税の申告」で済みますが、法人になると提出書類の数が大幅に増え、会計知識や専門用語も必要になります。
たとえば法人では以下のような申告書類が必要です。
- 法人税申告書
- 消費税申告書
- 地方法人税・法人住民税の申告書
- 勘定科目内訳明細書
- 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
こうした書類は税理士のサポートがほぼ必須といえるほど複雑で、申告ミスや期限遅れにはペナルティも発生するため、手間とコストの両面で負担が増す点を覚えておく必要があります。
京都で法人成りするメリット
京都で事業を行う個人事業主が法人化することで、全国的なメリットだけでなく、地域特有の支援制度を活用できる可能性が広がります。
ここでは、京都市・京都府で法人が対象となる具体的な融資制度や補助金制度をご紹介します。
対象となる融資制度が増える
京都では、法人に限定された創業支援の融資制度があります。その一つが、京都信用保証協会の「開業・経営承継支援資金<創業無保証人型>」です。
開業・経営承継支援資金<創業(開業)型>は、保証料率に0.2%上乗せすることで、経営者が会社(法人)の連帯保証人となる必要がない保証制度です。保証限度額は1,500万円で、追加要件を満たした場合は、3,500万円になります。
|
対象者 |
府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む(ただし、創業無保証人型の場合、個人開業の方は対象外、税務申告1期未終了者は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要)) |
|
資金の使い道 |
設備資金・運転資金 |
|
保証限度額 |
1,500万円、追加要件を満たした場合は、3,500万円 |
|
保証期間 |
10年以内 原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可 |
|
貸付利率/保証料率 |
年1.2%(固定金利)/年0.70% |
このように、法人化することで保証人不要でも融資を受けられる道が開かれるのは強みです。
参考:京都信用保証協会「開業・経営承継支援資金<創業無保証人型>」
補助金の上限額が増える
法人化することで、京都市の一部補助金では補助上限額が高くなる制度もあります。たとえば、京都市が実施する「京都市伝統産業新商品開発・販路開拓支援事業補助金」では、個人と法人で補助金の上限額に違いがあります。
【補助金の概要】
京都の伝統産業を担う事業者が、新商品の開発や販路開拓(展示会出展、パンフレット作成、海外販売など)を行う際の経費の一部を補助するものです。
【補助上限額の違い】
個人事業主:上限5万円
法人:上限10万円
このように、法人のほうが補助金の対象経費や上限額が広く設定されているケースがあり、法人化することで実質的に受け取れる補助金の金額が倍増することもあります。
京都で伝統産業や地域資源を活かしたビジネスを行っている場合、こうした補助制度をフル活用するためにも法人化を検討する価値があります。
参考:京都市情報館「京都市伝統産業新商品開発・販路開拓支援事業補助金の募集開始」
法人成りするタイミング

法人成りには多くのメリットがありますが、「いつ法人化するか」がとても重要です。タイミングを間違えると、せっかくの節税効果や支援制度の恩恵を受け損ねてしまうこともあります。
ここでは、法人成りを考えるべき代表的な5つのタイミングを紹介します。
課税売上高が1,000万円を超えたとき
個人事業主が「消費税を納める義務」が発生するのは、課税売上高が1,000万円を超えた年の2年後です。つまり、1,000万円を超えた年があると、将来的に消費税の納税義務が生じます。
ここで法人化すれば、新設法人は原則として2年間、消費税が免除される可能性があります。消費税の免除により、事務作業の負担が軽くなり、節税効果が期待できるでしょう。
関連記事:1,000万円超えたり超えなかったりする時の消費税の納税義務は?いくら払うかのシミュレーションと事務負担を減らす方法
課税所得が800万円から900万円になったとき
個人は、所得が増えるほど高い税率が適用されます。たとえば、所得900万円を超えると、税率は33%以上に達することも珍しくありません。
一方、法人であれば、課税所得800万円以下の部分は約15%の軽減税率が適用され、課税所得800万円超でも法人税率は23.2%程度に抑えられます。そのため、課税所得が800万円を超える頃が、法人成りの一つの目安です。
法人化して家族に役員報酬を支払うなどの方法も組み合わせれば、さらに節税効果を高められます。
関連記事:合同会社が節税対策になると言われる理由は?節税金額のシミュレーションと効果を高めるポイント
主要取引先から法人間の取引を求められたとき
大手企業や官公庁、上場企業などの取引先によっては、契約相手を「法人限定」としているケースがあります。
「信頼性」「契約上のリスク管理」「税務処理の都合」などを理由に、個人事業主との取引を避ける会社も少なくありません。そのため、取引の継続や新規開拓のチャンスを逃さないためにも、法人化は一つの重要なステップとなります。
従業員の雇用を考えるとき
人を雇う際、雇われる側にとって「働く先が法人であるかどうか」は重要です。
法人であれば、社会保険に加入できるため、従業員は厚生年金・健康保険・雇用保険などの公的保障を受けることができます。また、福利厚生制度やキャリアの安定性といった面でも、法人の方が魅力的に映るケースが多く、優秀な人材の確保にもつながります。
スムーズな事業承継を考えるとき
将来、事業を家族や第三者に引き継ぎたいと考える場合は、早めに法人化しておくのが得策です。
個人事業の場合、事業用資産や契約などを一つひとつ名義変更する必要があります。しかし、法人であれば、株式の譲渡だけで事業全体を承継できるため、相続やM&Aの場面でもスムーズです。
法人成りは、タイミングと準備によって「得をするか」「損をするか」が分かれます。収益の状況や将来の展望、人の採用や設備投資の計画などによって、最適な時期は変わってくるからです。
私たち石黒健太税理士事務所では、法人成りのタイミングや節税効果のシミュレーション、社会保険の影響、会社形態の選び方などをトータルでサポートしています。
「法人にしたほうがいいのか分からない」「いつのタイミングがベストか相談したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。あなたの事業の未来にとって、最善の一手をご一緒に考えます。
法人成りの失敗を避けるためのポイント
法人化には多くのメリットがありますが、準備不足や思い込みによる失敗例も少なくありません。特に最初の判断や手続きが甘いと、せっかくの法人化が逆効果になることも。
ここでは、法人成りで後悔しないために押さえておくべき6つのポイントをご紹介します。
法人化の目的を明確にする
まず重要なのは、法人化の目的をはっきりさせることです。
- 節税のため?
- 融資や補助金の獲得?
- 取引先との信頼性向上?
- 従業員を雇うため?
- 事業承継を見据えて?
目的によって、設立のタイミングや会社形態(合同会社か株式会社か)も変わってきます。目的が曖昧なまま法人化してしまうと、「思っていたより税金が増えた」「手続きが面倒だっただけ」など、後悔する原因になりかねません。
手元に残るお金の増減をシミュレーションする
法人化すると、社会保険料の負担や法人住民税(均等割)、税理士費用などのコストが増えます。「節税になるからお得」と思っていたら、手元に残るお金が減っていたというケースも珍しくありません。
法人化前に、以下のような項目をもとに「収支シミュレーション」を行いましょう。
- 売上・利益の見込み
- 役員報酬の額
- 社会保険料
- 法人税・住民税
- 顧問税理士の報酬
事前に数字で見える化しておくことで、法人化による「見えないコスト」を把握でき、安心して次のステップに進めます。
個人事業主と法人化でどちらが得になるのかをシミュレーションした記事がございますので、あわせてご覧ください。
関連記事:個人事業主と法人化はどっちが得?シミュレーション結果を解説
設立費用を確保する
法人化には設立費用(登録免許税、定款認証費用、印紙代など)がかかります。株式会社であれば約20〜25万円、合同会社でも約6〜10万円ほどの資金が必要です。
ここで注意したいのが、「運転資金を使って設立費用を払ってしまう」こと。すると、法人設立後の家賃・仕入れ・外注費などの日常的な支払いが滞る恐れがあります。
法人化する際は、設立費用とは別に、3〜6ヶ月分の運転資金を残しておくのが理想です。
個人と会社のお金を完全に分ける
法人化後は、会社のお金と個人のお金をきっちり分けることが基本です。
「売上は会社名義の口座に入金」「会社の支払いは会社名義の口座から」「役員報酬を通じて生活費を得る」など、法人と個人の経理を分離しておかないと、税務上のトラブルに発展するリスクがあります。
特に、「経費のつもりで私的支出を会社から払ってしまった」「役員報酬を勝手に増減した」といったケースは否認・追徴課税の原因になりかねません。
関連記事:お金がない会社の特徴とお金が残らない本当の理由は?経営を安定化するための改善策
事業に必要な許認可を再取得する
法人化によって「事業者」が個人から法人へ変わるため、一部の許認可や登録は再申請が必要になることがあります。
たとえば以下のような業種では注意が必要です。
- 飲食業(営業許可)
- 建設業(建設業許可)
- 介護・福祉事業(指定申請)
- 古物商(警察への再届出)
法人化後に事業に必要な許認可を更新し忘れると、無許可営業とみなされる可能性があるため、事前に関係官庁などへの確認を忘れずに行いましょう。
信頼できる専門家をパートナーに選ぶ
法人成りは、税務・労務・法務・社会保険など、複数の分野にまたがる手続きが発生します。そのため、信頼できる専門家(税理士・司法書士・社労士など)と連携することが成功のカギです。
税金面だけでなく、「融資や補助金のアドバイス」「役員報酬の設計」「社会保険の加入手続き」などもワンストップで相談できる専門家がいると、安心して法人化の準備ができます。
京都の法人成りは石黒健太税理士事務所へご相談ください!

ここまで、法人成りのメリット・デメリット、ベストなタイミング、京都ならではの制度などを詳しく解説してきました。法人化は、事業の成長を支えるステップですが、その一方で「税金の仕組みが変わる」「社会保険の負担が増える」「設立手続きが複雑」など、不安や迷いがつきまとうのも事実です。
だからこそ、専門知識と地域事情に精通したパートナーの存在が欠かせません。
私たち石黒健太税理士事務所は、京都を拠点に個人事業主の法人成り支援に多数の実績を持つ税理士事務所です。「京都信用保証協会の融資制度」や「京都市の補助金制度」など、京都特有の支援制度にも対応。事前のシミュレーションから設立後の経理・税務まで、あなたのビジネスをトータルでサポートします。
法人化を考えているけれど、「何から始めればいいかわからない」「損をしない方法を知りたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料。あなたの事業にとって最適な選択をご一緒に考えます。
まとめ
個人事業主が法人成りを検討する際には、節税や資金調達、社会的信用の向上といった数々のメリットがある一方で、設立費用や社会保険の負担、手続きの複雑さなど注意すべきデメリットもあります。特に京都での法人化は、地域独自の融資制度や補助金制度が充実しており、法人化による恩恵を受けやすい環境が整っています。
ただし、法人化の効果を最大限に活かすには、「いつ」「どのように」法人成りするかが非常に重要です。税金・社会保険・資金計画・許認可など、多方面に配慮が必要なため、信頼できる専門家に相談しながら進めることが成功の近道です。
京都で法人成りを検討されている方は、ぜひ石黒健太税理士事務所へご相談ください。あなたの事業にとって最適な形で、法人化を丁寧にサポートいたします。