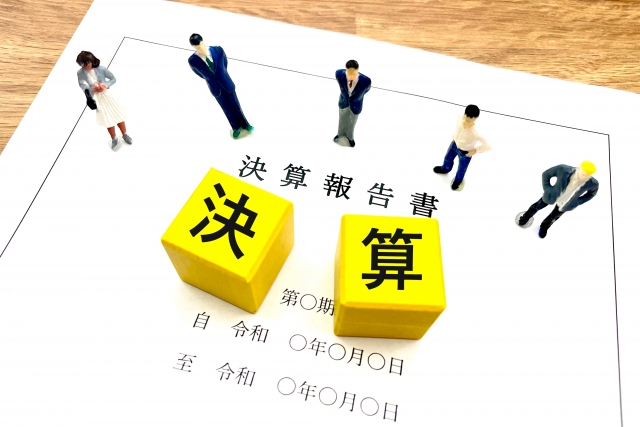京都市で開業した法人設立届の提出先と必要書類
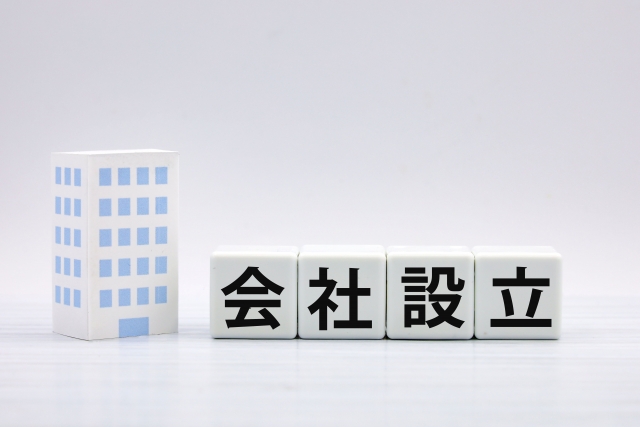
京都市で法人を開業した場合、法人設立届など必要書類の届出をします。
ここでは、税務署、京都府府税事務所、京都市の3つの提出先と、それぞれに必要な書類について解説します。
税務署
京都市で法人を開業した場合、税務署への必要書類は、以下のとおりです。
- 法人設立届出書
- 定款の写し(資本金1億円以上の内国普通法人の場合は2部)
提出期限は、法人設立の日から2か月以内。提出先は、法人の本店所在地を管轄する税務署です。京都市内の場合、地域によって以下の税務署が該当します。窓口に出向けない場合は、郵送などで提出できます。
|
税務署 |
所在地 |
管轄地域 |
|
右京 |
〒615-0007 京都市右京区西院上花田町10の1 |
右京区・西京区・向日市 長岡京市・乙訓郡 |
|
上京 |
〒602-8555 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358 |
北区・上京区 |
|
左京 |
〒606-8555 京都市左京区聖護院円頓美町18 |
左京区 |
|
下京 |
〒600-8181 京都市下京区間之町五条下ル大津町8 |
下京区・南区 |
|
中京 |
〒604-8482 京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎 |
中京区 |
|
東山 |
〒605-0914 京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5 |
東山区・山科区 |
|
伏見 |
〒612-0084 京都市伏見区鑓屋町 |
伏見区 |
参考:国税庁「税務署所在地・案内(京都府)」
京都府府税事務所
京都市で法人を開業した場合、京都府府税事務所への必要書類は、以下のとおりです。
- 法人設立 異動等届出書
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 定款の写し
提出先は「京都地方税機構申告センター(京都府庁西別館4階)」です。窓口に出向けない場合は、郵送やeLTAXでの対応ができますので、法人設立の日から速やかに提出しましょう。京都府庁、府税事務所、府広域振興局、また、市町村へもそれぞれ提出できますが、できるだけ申告センターに提出しましょう。
参考:京都府「府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人届出・申告関係)」
京都市
京都市で法人を開業した場合、京都市への必要書類は、以下のとおりです。
- 法人等設立 解散 変更届出書(法人設立届出書)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 定款の写し
提出期限は、法人設立の日から速やかに。提出先は「京都市役所 市民税課(法人市民税係)」です。窓口に出向けない場合は、郵送やeLTAXでの対応ができますので、法人設立の日から速やかに提出しましょう。
参考:京都市情報館「法人等設立・解散・変更届出書」
法人設立後の各種届出は、提出先が複数にわたるため、漏れや記入ミスが生じやすいものです。また、青色申告や消費税関連の届出も早期に判断が必要です。
私たち石黒健太税理士事務所では、京都市での法人設立支援や設立後の税務手続きのサポートを行っております。「どこに何を出せばいいかわからない」「税務署への書類の書き方が不安」など、お気軽にお問い合わせください。
京都市の法人設立届出書はどこでもらえる?
法人設立届出書は所定の様式があるため、法人を設立したら、京都市に「法人設立届出書」をもらいましょう。
ここでは、京都市の「法人設立届出書」の入手方法を2つご紹介します。
公式サイトからのダウンロードが便利
京都市の法人設立届出書は、京都市公式サイトから届出書をダウンロードする方法が便利です。PDF形式で用意されており、自宅や職場のパソコンから印刷して記入することができます。わざわざ市役所まで行かなくてもすぐに準備できるので、忙しい方にもおすすめです。
ダウンロードできる書式には、記入例も掲載されているため、初めての方でも迷わず進められます。
参考:京都市情報館「法人等設立・解散・変更届出書」
窓口で届出書を受け取ることもできる
自分で書類の記入するのが不安な方や、ついでに相談もしたいという場合は、京都市役所の窓口で法人設立届出書を直接受け取ることも可能です。
係員から書き方のアドバイスを受けられるため、対面で確認したい方には安心できる方法です。
法人設立届の提出方法
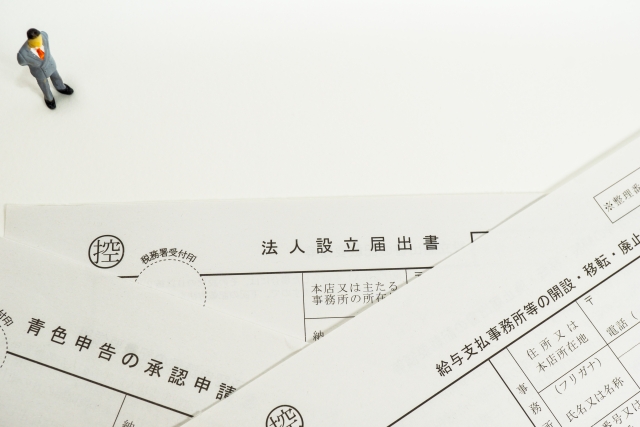
法人を設立した際には、税務署・都道府県・市区町村に対して法人設立届を提出する必要があります。提出方法は「窓口持参」「郵送」「オンライン」の3種類から選ぶことができ、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ここでは、それぞれの提出方法について詳しくご紹介します。
窓口へ直接持参する
法人設立届を窓口へ直接持参する方法は、その場で職員に書類を確認してもらえるため、万が一不備があった場合でもすぐに修正が可能です。担当者に直接質問できるので、スムーズに提出できるでしょう。
届出などを提出する場合、提出用と控えを準備しておきましょう。控えを保存することで、いつどんな届出などを提出したか、後で確認できます。提出時に控えがあると、受領印を押印してもらうことが可能です。
以前は法人設立届の控えに収受日付印(受領印)を押してもらえましたが、2025年(令和7年)1月より税務署での窓口提出時に収受日付印(受領印)を押さない方針に変わりました。これにより、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要になります。
ただし、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に法人設立届を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者に渡されます。ご自身での管理に不安な場合や、銀行口座の開設や他の届出のために、法人設立届の控えを準備するだけでなく、リーフレットはもらっておくとよいでしょう。
一方で、平日の開庁時間(通常9:00〜17:00)に合わせて訪問しなければならないため、仕事の都合などで時間的な制約を受けやすいというデメリットもあります。窓口が混雑している場合には待ち時間が発生する可能性もあるため、時間に余裕を持って行くとよいでしょう。
【メリット】
- その場で書類の確認をしてもらえる
- 収受日付印(受領印)の代わりに申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものがもらえる
- 担当者に直接質問できることもある
【デメリット】
- 平日の開庁時間内のため時間的な制約がある
- 窓口が混雑していると待ち時間が発生する可能性がある
郵送で提出する
法人設立届を郵送で提出する方法は、窓口に足を運ぶ必要がないため、時間や移動の手間を省けます。平日に市役所や税務署の窓口へ行く時間が取れない方でも、自分の都合の良いタイミングで手続きを進められるため、忙しい方には特に便利な方法といえるでしょう。
一方で、書類に不備があった場合には、返送や再提出が必要となり、その分手続きに時間がかかることがあります。
控えについては、あらかじめ写しを用意し、返信用封筒(切手貼付済み・返送先住所記載)を同封しましょう。税務署の場合は、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送されます。
なお、重要な書類ですので、郵送には「簡易書留」や「レターパックライト・プラス」など、配達記録が残る方法を利用することをおすすめします。
【メリット】
- 窓口に行く必要がなく、時間や移動の手間を省ける
- 平日に時間が取れない方でも対応できる
【デメリット】
- 書類の不備があった場合、返送や再提出となり時間がかかる
オンラインで提出する
法人設立届は、国税および地方税の専用オンラインシステムを使ってインターネットから提出することも可能です。国税(税務署)への届出には「e-Tax(イータックス)」、地方税(府税・市税)への届出には「eLTAX(エルタックス)」というシステムを利用します。
オンラインで提出する最大のメリットは、24時間いつでも手続きができる点です。郵送や窓口提出のように時間に縛られることがなく、自分の都合に合わせて作業できます。また、郵送費や移動の手間がかからず、効率的に手続きを進められることに加え、過去に提出したデータがシステム上で保存・管理できるため、再提出や内容確認も容易です。
一方で、オンライン提出にはデメリットもあります。利用にあたっては電子証明書やICカードリーダーの準備が必要になる場合があり、特に初めての利用時には導入や設定に手間がかかることがあります。また、システムの操作に慣れていない方にとっては、提出までに時間を要する可能性もあるため注意が必要です。
提出後の控えについては、電子送信後に発行される受信通知や受付結果をPDF形式で保存・印刷することで、提出証明として利用することができます。紙での証明が必要な場面でも安心して対応できます。
【メリット】
- 24時間いつでも提出できる
- 郵送費や移動時間がかからない
- 過去の提出データがシステム上で管理できる
【デメリット】
- 電子証明書やICカードリーダーの取得・設定により、初回は手間がかかる
- システム操作に不慣れな場合は、設定や送信に時間がかかる
設立届と一緒に提出を検討する書類例
法人設立時には、設立届のほかにも、今後の経理・税務・労務に関わる重要な書類を一緒に提出しておくとスムーズです。
ここでは、提出を検討すべき6つの書類と、それぞれの概要や提出期限についてわかりやすく解説します。
|
書類名 |
概要 |
|
青色申告の承認申請書 |
法人税の申告を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続きです。 |
|
減価償却資産の償却方法の届出書 |
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続きです。 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続です。 |
|
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設する場合などに届け出る手続きです。 |
|
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続きです。 |
|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。 |
青色申告の承認申請書
青色申告とは、節税メリットが大きい申告方法のひとつです。法人が青色申告を行うことで、赤字(欠損金)の繰越控除や30万円未満の少額減価償却資産の一括経費計上など、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。
この青色申告を適用するためには、あらかじめ「青色申告の承認申請書」を提出しておく必要があります。申請を出さなければ、自動的に白色申告となり、青色申告のメリットは受けられません。
一般的な提出期限は、「設立日以後3か月を経過した日」または「最初の事業年度終了日のいずれか早い日」の前日までと定められています。期限を過ぎてしまうと、その事業年度から青色申告を使うことはできませんので、早めの提出がおすすめです。
参考:国税庁「青色申告書の承認の申請」
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却とは、1台あたり10万円以上のパソコンや車両、備品などの高額な資産を複数年に分けて経費計上する会計処理のことです。法人がこれらの資産を購入した場合、その費用を一度に全額経費にするのではなく、数年かけて分割しながら計上する必要があります。
このとき、「どの方法で分割するか(償却方法)」を自分で選んで指定できるのが「減価償却資産の償却方法の届出書」です。主な償却方法には、毎年同じ額を均等に計上する「定額法」と、初年度に多く、年々少なくしていく「定率法」があります。
この届出を提出すれば、自社の経営方針や資金計画に応じて、より効果的な償却方法を選ぶことが可能です。提出しない場合は、原則として法定の償却方法が自動的に適用されます。
提出期限は、事業年度の申告期限(=決算日から2か月以内)までです。設立初年度で設備や備品を購入する場合は、早めに届出書を提出しておくと安心です。
参考:国税庁「減価償却資産の償却方法の届出」
適格請求書発行事業者の登録申請書
「適格請求書発行事業者」とは、いわゆる「インボイス」を発行できる事業者のことです。2023年にスタートしたインボイス制度により、取引先が仕入税額控除(消費税の控除)を受けるには、請求書の発行者が「適格請求書発行事業者」として登録されている必要があります。
つまり、自社がインボイスを発行できなければ、取引先が「この会社との取引は損になる」と判断してしまい、取引を見送られる可能性もあるのです。
適格請求書発行事業者の登録を行うには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を国税庁に提出しなければなりません。申請が受理されると、法人番号に基づいた「インボイス登録番号」が発行され、それを請求書に記載することで、正式なインボイスを発行できるようになります。
登録申請期限はありませんが、登録を希望する15日前までに手続きが必要です。一般的に、法人を設立して2期は消費税の納税義務はありません。しかし、1期目から適格請求書発行事業者の登録をすると、1期目から消費税の納税義務が発生するため注意しましょう。
関連記事:インボイス制度後の個人からの仕入れはどうなる?消費税に与える影響と対策を解説
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
法人を設立して役員や従業員に給与を支払う場合は、必ず提出すべき書類があります。それが「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」です。
この届出は、税務署に対して「当社は給与を支払う体制を整えました」ということを知らせるためのものです。届け出ることで、源泉所得税(給与から天引きする税金)を正しく管理・納付する義務が発生します。役員1人だけの会社であっても、役員報酬を支払う場合は提出が必要です。
届出書には、会社の所在地や給与の支払い開始日、従業員数などを記入します。書式は国税庁の公式サイトからダウンロードでき、記入例もあるので安心です。
提出期限は、「開設の事実があった日から1か月以内」とされています。うっかり忘れると、源泉徴収や納付の管理が正しく行えなくなるため、必ず期日内に対応しましょう。
参考:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員や従業員に給与を支払う場合、その給与から差し引いた源泉所得税は、毎月納付するのが原則です。しかし、少人数の企業では毎月の納付作業が大きな負担になることもあります。そんなときに活用したいのが「源泉所得税の納期の特例」です。
源泉所得税の納期の特例を利用すれば、源泉所得税の納付を7月と翌年1月の年2回にまとめることができ、事務作業を大幅に減らせます。対象となるのは、常時雇用している従業員が10人未満の事業所です。多くの中小企業や1人社長の法人にとって非常に便利な制度です。
この特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。提出後、税務署からの承認が得られた月の翌月以降から適用されます。
提出期限は法律上明確に定められていませんが、特例を受けたい場合は給与の支払いを始めるタイミングで早めに提出するのがベストです。承認されるまでの間は月ごとの納付義務があるため、特例を希望する場合は設立時点で忘れずに提出しておくと安心です。
参考:国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
法人を設立したら、たとえ代表者1人の会社であっても、原則として健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。これは「常時使用関係」があるとみなされるためで、役員報酬を受け取る社長自身も対象となります。
その加入手続きを始めるために提出するのが、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」です。この書類を提出することで、法人として社会保険の適用事業所となり、保険証の発行や年金加入の手続きがスタートします。
提出先は、会社の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)です。提出には、書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された法人登記簿謄本の原本が必要です。
提出期限は、法人設立日から5日以内。期間が短いため、設立準備と並行して書類を整えておくことが重要です。特に、従業員を雇用する場合は、労災保険や雇用保険の手続きともあわせて行う必要があるため、余裕を持った準備が欠かせません。
関連記事:1人社長の社会保険料はいくら?具体的な計算方法と役員報酬8万円の社会保険料の金額
参考:日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
法人設立後は、提出すべき書類が多く複雑になりがちです。「いつ、どこに、何を出せばよいかわからない」「必要な書類が漏れてしまいそう」とお困りの場合は、石黒健太税理士事務所にぜひご相談ください。法人設立から届出、税務・労務まで、一貫して丁寧にサポートいたします。
設立届を京都市の税理士に依頼するメリット

ここまでお伝えしたように、法人を設立した直後は、事業の準備に追われながらも、税務・労務など数多くの届出や手続きが発生します。これらをすべて自分で対応するのは、思った以上に負担が大きいものです。そこで頼りになるのが、地元・京都市の事情に詳しい税理士の存在です。
ここでは、設立届を税理士に依頼することで得られる3つの大きなメリットをご紹介します。
メリット1:複雑な書類作成の手間から解放される
法人設立後には、税務署・府税事務所・市役所などに対して、さまざまな書類を提出する必要があります。それぞれの提出先によって様式や記入内容が異なるため、初めての方にとっては非常にややこしく感じることでしょう。
税理士に依頼すれば、こうした書類を正確かつスピーディーに作成・提出してもらえるため、自分で一つひとつ調べたり記入ミスを心配したりする必要がなくなります。特に、青色申告の承認申請や源泉所得税の特例申請など、見落としやすい書類までカバーしてもらえる点は大きな安心材料です。
メリット2:設立当初から節税を意識した経営ができる
法人を立ち上げたばかりの時期こそ、税金対策の基盤を整えることが重要です。たとえば、役員報酬の金額設定や減価償却の方法選定など、最初の判断が将来の税額に大きな影響を与える場面が多くあります。
経験豊富な税理士であれば、設立時から「節税を前提とした経営アドバイス」が可能です。帳簿のつけ方や経費の使い方など、日々の業務にも直結する実践的なノウハウが得られるため、事業のスタートダッシュを力強くサポートしてもらえます。
メリット3:融資・補助金のサポートが受けられる
設立後の資金調達をスムーズに行うためには、融資の申請や補助金・助成金の活用が欠かせません。こうした制度には審査があり、計画書の内容や提出タイミングが影響します。
京都市に精通した税理士なら、地元の信用金庫や金融機関、自治体の補助制度に詳しく、適切な制度の紹介から申請書類の作成、金融機関とのやり取りまで一括でサポートしてくれます。経営初期にありがちな「資金不足」の悩みも、専門家と連携することで解消しやすくなるでしょう。
法人の設立届は京都市の石黒健太税理士事務所にご相談ください!
法人の設立時には、税務署・京都府・京都市などの提出先にそれぞれ異なる届出が求められます。さらに、青色申告の申請や源泉所得税の特例、社会保険の手続き、インボイス登録など、提出すべき書類は多岐にわたり、提出期限もバラバラです。
こうした煩雑な手続きを、正確に、そして無理なく進めていくためには、専門家のサポートが欠かせません。
石黒健太税理士事務所は、京都市内での法人設立支援に豊富な実績があり、地域の税務・行政制度にも精通しています。設立届の作成・提出はもちろんのこと、開業直後の節税対策や社会保険のアドバイス、融資や補助金の申請サポートまで、ワンストップで対応可能です。
初めての法人設立で「何から手をつけていいか分からない」という方でも、私たちが丁寧に、そして確実にサポートいたします。
「きちんと届出を済ませたい」「設立直後から安心して事業に専念したい」とお考えの方は、石黒健太税理士事務所にご相談ください。
まとめ

法人を設立したあとは、税務署や地方自治体などにさまざまな届出が必要です。提出先ごとに書類の種類や期限が異なるため、手続きに不慣れな方にとっては戸惑うことも多いでしょう。特に青色申告や源泉所得税の特例、インボイス制度などは、早めの判断が将来の経営に大きな影響を与えます。
こうした複雑な手続きを確実に、そして効率よく進めるためには、地域の制度に詳しい専門家のサポートが欠かせません。京都市で法人を設立される方は、石黒健太税理士事務所にご相談ください。設立届の作成・提出から節税・融資対策まで、あなたのビジネスのスタートを丁寧にサポートいたします。