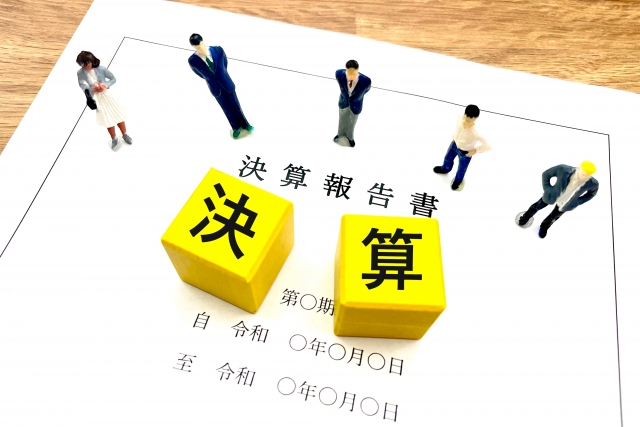合同会社の決算は自分でできるが大変

法人の場合、事業年度が終わったら決算書を作成し、申告・納税します。この一連の手続きが決算です。合同会社の決算は、税理士に依頼せずに自分で行うことも可能です。しかし、決算書の作成も税務申告の手続きも個人の確定申告と比べて複雑なので、実際にやってみると大変だと感じる人が多いのも事実です。
コストを抑えるためとはいえ、経営者が決算業務に時間を取られ、事業活動がおろそかになってしまっては意味がありません。手順や注意点をよく確認し、専門家に依頼しなくてもよいのか慎重な判断が求められます。
合同会社は売上がなくても決算は不要にならない
合同会社の決算書の作成と申告・納税は法律で定められた義務です。たとえ事業年度内に売上がなくても、決算は不要とはなりません。法人住民税の均等割は、売上がない場合も一般的には最低7万円程度は課税されるため、申告書を提出する必要があります。
また、2期連続で申告期限に遅れると、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性が高いです。青色申告が取り消されると、赤字が出た場合に翌年以降の黒字と損益通算できる「欠損金の繰越控除」や、30万円未満の減価償却資産を一度に経費にできる特例など、青色申告の場合に認められる節税の措置が受けられなくなってしまいます。
関連記事:売上なしの合同会社にかかる税金とかからない税金は?売上なしでも決算は不要にならない
合同会社の決算はいつまでに終わらせる?
決算には期限があり、期限を守らないと延滞税や無申告加算税などのペナルティを課されるリスクがあります。期限を守って手続きを終えるのが理想ですが、どうしても難しい場合は提出期限を延長することも可能です。ここでは、合同会社の決算の期限や期限の延長制度について解説します。
事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内が期限
法人税や消費税の申告期限は、事業年度が終了した日の翌日から2ヵ月以内です。たとえば、事業年度が3月31日で終了する場合、申告期限は5月31日になります。
期限内に申告しない場合のペナルティとして、延滞税や無申告加算税があります。延滞税は、納期限の翌日から納税が完了するまでの日数に応じて課され、延滞の期間が長くなるほど負担が重い税金です。無申告加算税は、期限後に自主的に申告すれば納税額の5%、税務署から指摘されて申告する場合、税額により15~30%が加算されます。
期限を過ぎてしまうと、本来払わなくてもよかったはずの多額の税金を納めることになりかねません。決算は事前にスケジュールを組んで、早めに対応することが大切です。
参考:財務省「加算税の概要」
提出期限は1ヶ月延長できる
法人税の申告期限は、定款等の事業によっては税務署に「申告期限の延長の特例の申請書」を提出することで1ヶ月延長できます。たとえば、通常の申告期限が5月31日である場合、延長手続きを行えば6月30日まで申告期限の延長が可能です。
ただし、申告期限を延長した場合でも、納期限は延長されない点に注意が必要です。通常通り、事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に見込み額で納税し、税額が確定してから追加で納めるまたは還付を受けるという対応になります。
また、消費税の申告期限は延長することができません。そのため、消費税の申告・納付は法人税とは別に期限内に行う必要があります。申告期限までに余裕を持って終えられるよう、準備を進めましょう。
自分で期限内に申告するのは難しいと感じたら、早めに税理士に相談してリスクを回避しましょう。石黒健太税理士事務所では、合同会社の決算をサポートいたします。無料相談も受け付けていますので、決算に不安がある方はお気軽にお問い合わせください。
参考:国税庁「申告期限の延長の申請」
合同会社の決算をスムーズにするやり方・進め方

決算の流れを把握して計画的に進めることで、期限内にスムーズに終えることができます。ここでは、決算のやり方や進め方を5つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1:記帳を完了する
記帳とは、日々の取引を帳簿に記録する作業のことです。日頃から正しく記帳を行っていれば、決算時には売上や経費が正しく入力されている状態のため、このステップにはあまり時間を要さないでしょう。
逆に「決算のときにまとめてやればいいや」と帳簿を放ったらかしにしておくと、決算の際に領収書などを整理し、内容を思い出しながら記帳しなければならなくなり、大変な手間がかかります。日々の記帳を習慣化し、月に1度は内容を確認しておいたほうが、決算がスムーズに進みます。
関連記事:月次報告とは?経理初心者が月次決算をするメリットと会社の成長を加速させるポイント
ステップ2:決算整理仕訳を追加する
記帳を完了した後は、決算整理仕訳を行います。決算整理仕訳とは、決算時点の実際の状況と帳簿にずれが出ないように、決算のときだけ行う仕訳です。決算整理仕訳の例を紹介します。
・売掛金の計上
事業年度内に売上が発生し、まだ入金がない場合は「売掛金」として計上します。期中は入金のタイミングで売上を計上している場合でも、たとえば決算月の売上で翌年度に入金されるものは、決算時に売掛金として処理します。
|
借方 |
貸方 |
||
|
売掛金 |
50,000円 |
売上 |
50,000円 |
・未払費用の計上
事業年度内にサービスの提供などを受け、まだ支払っていない費用を計上します。たとえば、水道光熱費や通信費など、使った月の翌月に請求されて支払うものがあります。
|
借方 |
貸方 |
||
|
水道光熱費 |
10,000円 |
未払費用 |
10,000円 |
・減価償却費の計上
事業で使用する設備や機器は、一度に費用計上するのではなく、耐用年数に応じて減価償却します。たとえば、取得価額30万円、耐用年数5年のパソコンを減価償却する場合は以下のような仕訳をします。
固定資産から減価償却費を直接差し引く直接法と、償却額の累計を表示する間接法があります。記載を統一すれば、どちらを選んでも問題ありません。
【直接法】
|
借方 |
貸方 |
||
|
減価償却費 |
60,000円 |
工具器具備品 |
60,000円 |
【間接法】
|
借方 |
貸方 |
||
|
減価償却費 |
60,000円 |
減価償却累計額 |
60,000円 |
・貸倒引当金の設定
売掛金が将来的に回収できない可能性を考慮し、貸倒の金額を見積もっておきます。売上債権総額のうち一定の割合を貸倒引当金とするのが一般的です。たとえば、卸売業の会社が期末に50,000円の売掛金があり、その10/1,000を貸倒引当金として計上する場合の仕訳は以下の通りです。
|
借方 |
貸方 |
||
|
貸倒引当金繰入 |
500円 |
貸倒引当金 |
500円 |
ステップ3:決算書を作成する
決算整理仕訳が完了したら、次に決算書を作成します。作成する主な書類は、損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)です。
損益計算書は、会社の売上や経費、最終的な利益を示す書類です。「いくら稼ぎ、いくら使い、どれだけ利益が出たか」を明確にします。貸借対照表は会社の資産・負債・純資産の状況を示す書類です。「会社がどのような資産を持ち、どのように資金を調達しているか」が分かります。
関連記事:【初心者向け】主要な3種類の決算書の種類と見方とは?経営者が読み方を知らないリスクとトレーニングする方法
ステップ4:税金の申告書を作成する
決算書の内容をもとに税金の申告書を作成し、税額を計算します。法人の場合、以下のような税金の申告書が必要です。申告書作成ソフトを利用すれば、自分で計算する手間が省けるケースが多いです。
1.法人税
法人税は法人の所得に対して課される税金です。税率は資本金や所得金額によって異なります。申告書の提出先は所轄の税務署です。
2.法人住民税
法人住民税は法人税割と均等割があります。法人税割は法人税をもとに算出されます。均等割は赤字でも支払う必要があり、金額は最低7万円程度です。法人住民税は道府県民税と市町村民税があり、申告書の提出先は県税事務所等と市区町村役場です。
3.法人事業税
法人事業税は、事業そのものに対して課される税金で、翌年損金算入できるのが特徴です。税率は資本金や所得金額によって異なり、赤字の場合は納める必要がありません。申告書の提出先は県税事務所等です。
4.消費税(該当する場合)
設立時の資本金が1,000万円以上の場合、新しく設立した合同会社でも消費税の申告・納税義務があります。設立時に免税事業者でも、2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるなど、一定の条件を満たすと消費税の課税事業者となります。申告書の提出先は所轄の税務署です。
ステップ5:申告書の提出と税金の納付をする
申告書の提出方法は、税務署や自治体に持参または郵送する方法もありますが、おすすめは電子申告(e-Tax)です。申告書作成ソフトで作成した申告書のデータをそのまま提出できるため、印刷や提出に出向く手間をかけずにスムーズな申告が可能です。
法人税や消費税は、税務署や金融機関で現金納付ができるほか、クレジットカードも利用できます。税額が30万円以下の場合はコンビニ納付やスマホ決済も可能です。法人住民税や法人事業税は、納付書払いのほか、自治体によっては電子納税などの方法を導入している場合があります。申告書の提出と納税が終わったら、一連の決算手続きは完了です。
決算は会計や税務の知識がないと難しいものです。わからないことがあれば、事前に専門家に相談して疑問を解消しておくとよいでしょう。石黒健太税理士事務所では、合同会社の決算についてのご相談を受け付けています。
お電話でのご相談もできますので、「自分でやろうと思ったけれど、決算時の帳簿の処理がわからない」など、お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
合同会社の決算を自分でするデメリット
決算は単なる書類作成ではなく、専門知識を必要とする複雑な作業です。不慣れな人が何とか自力で進めても、時間がかかるだけでなく、申告ミスや納税漏れなどが発生するリスクもあります。ここでは、合同会社の決算を自分で行うデメリットを解説します。
決算業務に時間を取られる
前述のとおり、決算は帳簿の処理から決算書の作成、申告・納税まで多くの作業があります。これらをすべて自分で行うには、多くの時間と労力がかかります。
コストを抑えるために決算を自力で行うはずが、営業や顧客対応に時間を割けなくなり、結果的に税理士に依頼した場合の報酬以上に売上が減少してしまう可能性があります。税理士報酬は必要経費と割り切り、決算は専門家である税理士に依頼して、自分は事業に専念するという方法は、経営的には理にかなっていると言えます。
関連記事:会社が税理士を雇わないリスクは?税理士なしで法人決算をする方法と費用を抑えるポイント
ペナルティが発生するリスクがある
決算を自分で行う際に怖いのが、申告の遅れや申告ミスによるペナルティの発生です。税金の納期限に遅れると、延滞税が発生する可能性があります。また、期限内に申告をしなかった場合は無申告加算税、申告・納税しても、申告内容の誤りなどにより納税額が過少であった場合は過少申告加算税が課される場合があるため注意が必要です。
ペナルティを避けるためには、税務知識を身につける必要があります。しかし、税制は毎年改正されるため、最新の情報を把握するのは簡単ではありません。税理士に依頼すれば、より正確な申告ができるだけでなく、申告漏れも防げます。
関連記事:企業の成長が加速する税理士の選び方は?依頼する目的から選ぶ税理士の選び方とポイント
節税対策が不十分になる
節税対策が不十分だと、必要以上に税金を支払うことになります。とはいえ、自分で税制などを調べて、自社の状況に応じた適切な節税対策を講じるのは難しいものです。節税対策は期中からの対策が重要で、決算のときに気がついても遅い場合も少なくありません。
税理士に相談することで、経費は適切に計上できているか、自社に有利な税制を活用できているかなどを確認し、決算に備えることができます。
関連記事:節税の提案をしてくれない税理士に依頼するデメリットは?経費にしてくれない理由と対策
合同会社の決算にかかるコストを削減する方法

合同会社の決算には、会計ソフトの導入費用や税理士への依頼費用など、さまざまなコストがかかります。特に創業間もない場合や小規模な合同会社では、決算のコストをなるべく抑えたいと考える経営者の方も多いでしょう。
適切なコスト削減の方法を知ることで、経営者の負担を減らしながら、安心して決算に臨むことができます。
会計ソフトを活用する
会計ソフトを活用すれば、会計の知識があまりない場合でも、日々の記帳や決算書の作成がスムーズに進められます。特に、クラウド会計ソフトには、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で仕訳するなど、記帳の時短ができる機能があります。
また、帳簿のデータをもとに簡単な手順で決算書を作成したり、申告書作成ソフトと連携して電子申告をしたりすることも可能です。決算を自分でやりたいと考えている人にとって非常に便利です。税理士に依頼する場合も、データ共有が容易にできるというメリットもあります。
自社で記帳して税理士に依頼する
記帳から決算まですべて税理士に依頼すると予算をオーバーしてしまう場合は、記帳作業を自社で行うことでコストを抑えられる可能性があります。
決算のみ税理士に依頼する場合は、日々の記帳は自社で正確に行う必要があります。月に一度試算表を作成して財務状況を確認するとともに、記録漏れがないように注意しましょう。領収書や請求書などの書類を整理しておくことも大切です。
関連記事:税理士に決算のみを依頼する場合の相場は15万円以上?費用を抑える方法
合同会社の決算はお気軽にご相談を!
合同会社の決算を自分でやることは不可能ではありませんが、手間やリスクを考慮すると、税理士に依頼したほうがコストがかからないケースもあります。期限が近くなる前に決算の手順を確認し、自分でやるかどうかを検討しましょう。

石黒健太税理士事務所では、合同会社の決算をサポートいたします。電話相談もできますので、決算を自分でやることに不安を感じる経営者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。