京都の会社設立の相談所はどこを選ぶ?3つの専門家を比較
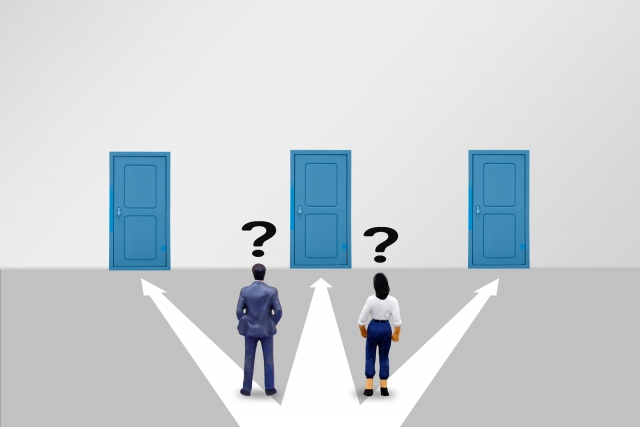
会社設立の相談先は、主に司法書士、行政書士、税理士の3つの専門家です。それぞれ得意分野が異なり、会社設立登記は司法書士、許認可申請や定款作成は行政書士、開業後の税務申告は税理士が専門です。どの専門家も、あなたに代わって書類作成や手続きを代行してくれます。
|
専門家 |
依頼できること |
|
司法書士 |
会社設立登記申請の代行、定款作成、定款認証手続きの代行 |
|
行政書士 |
許認可申請の代行、定款作成、定款認証手続きの代行 |
|
税理士 |
会社設立前の税務相談、開業届などの提出代行、設立後の会計処理・決算・税務申告の代行 |
商工会議所でも、創業セミナーや相談会を開催している場合がありますが、主な役割は情報提供です。会社設立の手続きは行ってもらえないため、必要に応じて専門家を紹介してもらうとよいでしょう。
司法書士
会社設立の際には法務局への登記申請が必須です。司法書士は登記の専門家として、申請書類の準備や提出を代行してくれます。法人形態や定款の内容についても、専門家の視点からアドバイスをもらえるでしょう。
会社設立登記には、定款や設立時役員の就任承諾書など、専門知識がないと作成が難しい書類が多くあります。ひな形を使って自力で書類を作成するのは、手続きのやり直しのリスクや制度設計のミスのリスクがあるためおすすめできません。司法書士に書類の作成から提出まで依頼することで、正確で迅速な手続きが期待できます。
ただし、経営相談は司法書士の得意分野ではありません。税務や財務に踏み込んだアドバイスが欲しい場合は、税理士などへの相談が必要です。
|
メリット |
複雑な登記手続きを正確に進められる、書類作成の負担が軽減できる |
|
デメリット |
設立後の税務に関する相談はできない |
行政書士
会社のルールブックである定款の作成は行政書士の専門分野です。事業内容に則した定款を正確に作成し、株式会社の場合は公証役場での定款認証まで代行してもらえます。
また、飲食業や建設業などの許認可申請書類の作成や申請代行もサポート可能です。現在個人として許可を受けて営業している方も、法人名義で許可を取り直す必要があります。スムーズに営業開始するために、会社設立の検討段階から許認可の相談もしておくと安心です。
ただし、登記や税務は専門外のため、司法書士や税理士と連携して手続きを進める必要があります。
|
メリット |
定款作成・認証を依頼できる、開業に必要な許認可申請までサポートしてもらえる |
|
デメリット |
登記や税務の相談・手続き代行はできない |
税理士
税理士は税務と財務の専門家です。会社設立時の手続きとしては、税務署への法人設立届出書や青色申告承認申請書などの作成・提出代行をサポートできます。登記申請は専門外のため、司法書士と連携して行います。
税理士の強みは税務や経営に関する幅広い相談ができることです。設立時には、将来の税負担や資金繰りのシミュレーション、事業計画書の策定、創業融資や補助金の活用など、多岐にわたるサポートが受けられます。
開業後は、記帳や決算申告の代行だけでなく、節税対策や経営改善のアドバイスを継続的に受けられます。会社を成長させたい経営者にとっては心強いパートナーとなるでしょう。
|
メリット |
設立時から将来を見据えた節税対策や資金繰り計画を立てられる |
|
デメリット |
会社設立登記は司法書士と連携する必要がある |
石黒健太税理士事務所は、会社設立の手続きはもちろん、経営コンサルティングも得意としています。設立後の成長戦略や資金調達についてもお気軽にご相談ください。
顧問税理士をつけるメリットや税理士の選び方については以下の記事もご覧ください。
関連記事:京都で顧問税理士をお探しの方は石黒健太税理士事務所へお気軽にご相談ください
会社設立までの流れ
会社設立は、事前に流れを把握し、期間に余裕をもって準備を進めることが大切です。専門家に依頼する場合は、設立希望日の1ヵ月半〜2ヵ月前には相談を始めましょう。
会社形態を決める
会社を設立する際にまず決めるのは会社形態です。一般的なのは株式会社と合同会社の2つですが、合資会社と合名会社も含めると4つの選択肢があります。会社形態の比較は以下の表の通りです。
|
株式会社 |
合同会社 |
合資会社 |
合名会社 |
|
|
資本金 |
1円以上 |
1円以上 |
1円以上 |
1円以上 |
|
出資者 |
株主 |
社員 |
無限責任社員、有限責任社員 |
無限責任社員 |
|
設立費用の目安 |
25~45万円 |
6〜10万円 |
6〜10万円 |
6〜10万円 |
|
責任の範囲 |
有限責任(出資額が上限) |
有限責任(出資額が上限) |
無限責任社員は会社の負債を全額負担、有限責任社員は出資額が上限 |
無限責任(会社の負債を全額負担) |
|
定款の認証 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
|
議決権 |
原則として所有する株式数に応じる |
出資比率に関わらず平等 |
定款で自由に設定 |
定款で自由に設定 |
株式会社は、株式を発行し、株主から資金を調達して事業を運営する会社形態です。会社のオーナー(株主)と経営者が分離していることが特徴で、株主は出資した金額以上の責任を負いません。社会的信用度が高く、大規模な事業展開や将来的な上場を目指す場合に適しています。一方で、設立費用が高く、定款の認証手続きが必要になるなどの手間もかかります。
合同会社は株式会社と比べて設立費用が安く、手続きも比較的シンプルなため、近年設立件数が増加しています。出資者全員が有限責任である点は株式会社と同じですが、出資者である「社員」が経営を行うため、意思決定が迅速に行えるのが特徴です。小規模な事業や、経営の自由度を重視したい場合に適しています。
合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成される会社です。無限責任社員は会社が倒産した場合などに、個人の財産をすべて使ってでも会社の負債を弁済する責任を負います。リスクが大きいことから、設立件数は少なくなっています。
合同会社と株式会社の違いや向いているケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:合同会社と株式会社の違いは?向いている会社形態と会社設立で失敗しないためのポイント
株式会社設立の流れ
株式会社設立のおおまかな流れは以下の通りです。
- 基本事項の決定(会社名、事業目的、本店所在地、資本金など)
- 定款作成
- 公証役場で定款認証
- 資本金の払込み
- 法人設立登記申請
- 税務署や自治体への届出
会社の印鑑の作成や、登記申請に必要な役員の印鑑証明書などの取得も並行して行います。基本事項の決定から設立登記申請までは、短くても2~3週間かかるのが一般的です。法人の銀行口座開設や法人設立届などの提出は登記完了後に行います。
株式会社設立の際は、資本金のほかに25万円~45万円程度の費用がかかります。詳しくは以下の記事をご参照ください。
関連記事:株式会社の設立費用の目安と内訳は?資本金1円でも節約にならない理由と節約する方法を解説
合同会社設立の流れ
合同会社設立の流れは以下の通りです。
- 基本事項の決定(会社名、事業目的、本店所在地、資本金など)
- 定款作成
- 資本金の払込み
- 法人設立登記申請
- 税務署や自治体への届出
公証役場での定款認証は必要ありません。株式会社に比べて手続きが簡単と言われますが、専門知識がない方が自分で行うのはリスクも伴います。合同会社の設立前後にやることや失敗しないための対策は、以下の記事もお読みください。
関連記事:合同会社設立までの5つの流れは?設立に必要な書類とひとりで手続きをするデメリット
スムーズに会社設立するための相談所の選び方

会社設立の相談所は複数あり、どこへ相談するか迷う方もいるでしょう。相談先によって対応できる業務や料金が異なるため、「誰に頼んでも同じ」と思わずに慎重に検討することが大切です。ここでは、スムーズに会社設立し、設立後の事業を成功に導くための相談所の選び方を紹介します。
依頼する目的で選ぶ
司法書士、行政書士、税理士にはそれぞれの専門分野があるのは前述の通りです。登記を早く確実に終わらせたい場合は司法書士、許認可申請の必要がある場合は行政書士、設立後の経営も見据えた相談がしたい場合は税理士への相談をおすすめします。
専門家同士のネットワークがあるため、専門外の業務が必要な場合は他の専門家を紹介してもらえる場合が多いです。最初の相談所としては、あなたが依頼したい手続きや相談したい内容に対応できる専門家を選ぶとよいでしょう。
設立後のサポート内容で選ぶ
会社設立はゴールではなく、事業を成長させるためのスタートラインです。設立後のサポート内容も考慮して相談所を選びましょう。
司法書士は役員変更などの登記が必要な場面で、行政書士は許認可の更新や変更届が必要な場面で頼れる存在です。ただし、いずれも顧問契約の形で継続的なサポートを行うのは一般的ではありません。
税理士は記帳代行、税務申告、資金繰りや節税の相談など、会社の税務や財務に関して継続的にサポートできるのが特徴です。気軽に経営相談がしたい、本業に集中できる環境を整えたいと考えている場合は、税理士への相談がおすすめです。
相性で選ぶ
相談所を選ぶ上で、専門家との相性はとても重要です。信頼関係を築き、疑問や不安を気軽に相談できるかどうかが、その後の事業に大きく影響します。面談で以下の点を確認し、心から信頼できる相談先を見つけましょう。
- 自分の疑問や不安を気軽に相談できる
- 専門用語を避けてわかりやすく説明してくれる
- あなたの事業に対する考え方や将来のビジョンに共感してくれる
- 質問や相談に対して迅速かつ丁寧に対応してくれる
料金体系で選ぶ
会社設立の手続きにかかる手数料は相談所によって異なります。ホームページに記載されているのは最低料金の場合もあるため、料金体系を事前に確認すると安心です。可能な限り詳細な見積もりを提示してもらい、内訳や追加料金の有無も確認しましょう。
経験の浅い専門家が実績作りのために料金を安く設定している場合や、安い代わりにサービス内容が手厚くない場合もあります。サービス内容と料金が見合っているか、依頼したい内容が料金に含まれているかも重要な観点です。
実績で選ぶ
創業支援の件数や、これまでに支援した会社の規模・業種が、専門家の得意分野や信頼性を判断する材料になります。あなたの会社と似たような事例の経験があれば、業界の事情も理解した上で的確なアドバイスがもらえる可能性が高まります。ホームページに記載がない場合は、面談の際に率直に聞いてみるのもよいでしょう。
会社設立時の税務・経営に関するポイント
会社設立時に決める資本金・決算月・役員報酬は、その後の税負担や会社の成長に直接影響します。税理士と相談しながら、慎重に決めることが重要です。ここでは3つのポイントについて詳しく解説します。
資本金が税金に影響する
会社設立時に決める資本金の額は、実は設立後の税金に大きな影響を与えます。
期首の資本金が1,000万円未満の会社は、設立1期目と2期目の消費税が原則として免除されます。開業初期は売上が安定しない場合が多いため、免税期間を活用すると資金繰りの面で有利です。
売上の多寡にかかわらず課税される法人住民税の均等割は、資本金の額によって金額が変わります。例えば、京都市内で従業員数50人以下の会社では、資本金が1,000万円以下の場合は年間7万円ほどです。
資本金の額は交際接待費にも影響を及ぼします。資本金が1億円以下であれば、交際接待費を年間800万円まで損金として計上できる優遇措置が受けられます。
資本金は多いほどよい、少ないほどよいというものではなく、会社の事業規模や資金繰りの状況に合わせて設定するべきものです。資本金額の決め方については、以下の記事も参考にしてください。迷う場合は税理士に相談しましょう。
関連記事:中小企業の資本金の平均額は?資本金を増やさない理由と税金との関係
繁忙期や支出が増える時期の決算月を避ける
決算月とは、会社の事業年度の最終月です。通常、法人税などの申告・納付期限は決算月から2ヶ月以内です。決算月とその後2カ月間は、決算書作成や税務申告といった事務作業が集中する重要な時期です。
本業の繁忙期が決算期と重なると、経理作業と通常業務の板挟みになり、大きな業務負担となります。また、大きい支出がある時期に決算を迎えると、納税資金の確保も必要になり、資金繰りが厳しくなるリスクが高まります。事業が落ち着いている時期や、資金に余裕のある時期を決算月に設定するのが得策です。
法人化するタイミングと決算期の決め方については、以下の記事もご覧ください。
関連記事:法人化するタイミングは何月がいい?おすすめしない月と月の途中で法人成りするときのポイント
役員報酬にはルールがある
会社が役員に支払う報酬を経費(損金)として計上するには、一定のルールがあります。具体的には、事業年度を通じて毎月同額を支給すること、そして事業年度開始から3ヵ月以内に金額を決定することです。
途中で安易に役員報酬を変更すると、変更した部分が経費として認められず、法人税の課税対象になるリスクがあります。設立時に会社の業績や資金計画を十分に考慮して慎重に決定しましょう。
以下の記事では、役員報酬の相場や決め方を解説しています。
関連記事:中小企業の役員報酬の相場は?役員報酬が高すぎる中小企業の注意点と手取りをシミュレーション
参考:国税庁「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
石黒健太税理士事務所が京都の経営者に選ばれる理由

京都で会社設立や経営相談のパートナーをお探しの方は、ぜひ石黒健太税理士事務所にご相談ください。弊所は豊富な実績と幅広いサポートで、京都で多くの企業様にお選びいただいています。
200社を超える法人の創業支援の実績がある
弊所は京都を中心に200件以上の創業支援実績を誇り、顧問契約先の約7割を創業期からご支援しています。また、弊所自身が創業から5年で年商1億円を達成した成長企業であり、会社の立ち上げから事業を軌道に乗せるまでのプロセスを熟知しています。豊富な実績と実体験としてのノウハウがあるからこそ、経営者が直面する課題や悩みに寄り添ったご支援が可能です。
税務以外の経営支援に強い
弊所は通常の税務顧問業務はもちろん、税務以外の経営支援も行っています。会社を成長させるには、経営目標の設定や、目標達成に向けた経営戦略・財務戦略が重要です。
弊所はお客様の財務状況を分析し、専門知識がない経営者の方も会社の状況を正しく把握できるようサポートします。その他にも、クラウド会計ソフトの導入によるバックオフィス業務の効率化など、幅広い経営課題に踏み込んだ包括的なサポートが経営者から高く評価されています。
資金調達や金融機関対策に強い
創業期の会社にとって、資金調達は重要な課題です。弊所ではこれまで累計40億円超の資金調達を成功させています。
日本政策金融公庫や銀行とのネットワークを活かし、お客様に適した融資制度の選定や、より有利な条件での借り入れを可能にします。金融機関の考え方を理解した担当者が、事業計画書の作成から面談対策までサポートするため、融資申請の手続きも安心です。
石黒健太税理士事務所では、会社設立はもちろん、設立後の経営のご相談も受け付けています。会社の成長を加速するパートナーとして、多角的なご支援が可能ですので、お気軽にご相談ください。
まとめ
京都で会社設立の相談先を探す際は、司法書士、行政書士、税理士の専門分野を理解することが大切です。設立後の税務や経営まで見据えるのであれば、税理士が継続的なパートナーとして力になるでしょう。あなたの目的や事業内容に合った専門家を見つけ、会社の成長に向けた第一歩を踏み出しましょう。








