京都の後継者不足の現状

京都は、伝統産業や家族経営の中小企業が多い地域であり、経営者の高齢化とともに「後を継ぐ人がいない」という悩みが顕在化しています。近年の調査によると、京都府内の中小企業のうち4割超で後継者が不在です。
後継者問題がなかなか解消できない背景には、以下のような理由があります。
- 子や親族が事業を継ぎたがらない
- 後継者候補が育っていない
- 経営者自身が承継に向けた準備をしていない
- 事業承継の方法や相談先がわからない
代々世襲してきた企業でも、子どもに家業を継ぐ意思がなく、京都から出てしまったり他業種に就職してしまったりするケースが増加傾向です。技術の承継が必要な業種では、後継者の育成に数年から十数年の期間を要する場合もあります。継いでくれる人が見つからずに廃業を考える方も多いのが現状です。
参考:中小企業庁「令和5年度に認定支援機関等が実施した 事業承継・引継ぎ支援事業に関する事業 評価報告書」
後継者不足を放置するリスク
後継者不足は一朝一夕で解決できません。問題を先送りにすると、企業が大切にしてきた人材や技術が失われ、最悪の場合は事業の継続が困難になるリスクもあります。3つのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
従業員が不安になる
経営者が高齢になっても後継者が決まらない状況が続くと、従業員の間で「この会社は大丈夫だろうか」という不安が広がります。将来が不透明な会社では、従業員が前向きなキャリアプランを描けません。モチベーションが低下し、結果として離職を考える人が増える可能性があります。
結果として、優秀な人材から離職が始まり、退職の連鎖を招くこともあるのです。個々の従業員の役割が大きい中小企業では、1人の離職が事業全体に深刻な影響を及ぼしかねません。
貴重な技術やノウハウが失われる
京都には、他地域にはない独自の製造技術や職人の感覚に支えられた伝統工芸、家業に代々受け継がれてきたノウハウが数多く存在します。しかし、後継者がいなければ貴重な知識や技術は次世代に引き継がれることなく、やがて消えてしまうでしょう。
実際に、西陣織・京友禅などの織物産業や伝統工芸の分野では、職人が高齢化し技術の承継が危ぶまれています。伝統ある技術が失われることは一企業だけの問題ではなく、地域の文化や経済全体にとって計り知れない損失と言えるでしょう。
廃業せざるを得なくなる
後継者が見つからないという理由で、事業自体は黒字でも廃業に追い込まれるケースが増えています。
例えば、老舗の和菓子店で後継者が見つからず、惜しまれながら店を閉めることになったとします。これまで店を支えてきた従業員は職を失い、長年の付き合いがあった取引先も新たな販路や仕入れ先を開拓しなければなりません。廃業は、単に一つの会社がなくなるだけでなく、雇用や地域経済、サプライチェーン全体に広範囲な打撃を与えるのです。
経営者が引退を考えてからでは、事業承継の準備が間に合わない可能性が高いです。後継者の育成はもちろん、会社としても事業承継の準備を計画的に進める必要があります。将来に備えるためには、早めの事業承継対策が必須です。
関連記事:黒字倒産はなぜ起こる?9つの理由と人手不足倒産になる会社の特徴と前兆
事業承継の方法
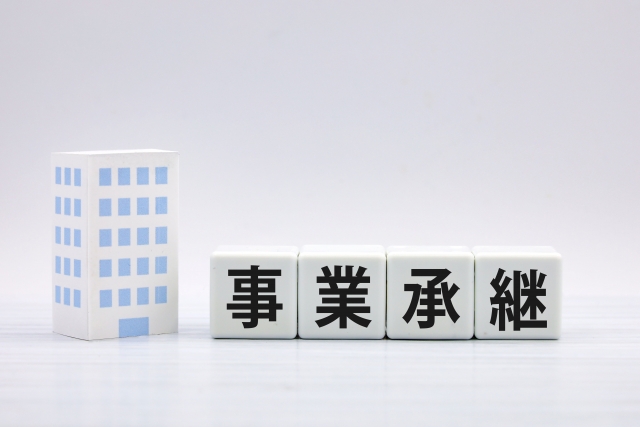
事業承継には主に3つの方法があります。企業の状況や後継者候補の有無によって、適切な選択肢は異なります。以下でそれぞれの方法の特徴を深掘りしていきましょう。
|
事業承継の方法 |
特徴 |
|
親族内承継 |
経営者の子や親族に事業を引き継ぐ方法 |
|
親族外承継 |
社内の従業員や役員など、親族以外の人材に引き継ぐ方法 |
|
第三者承継(M&A) |
外部の企業や個人に売却・譲渡する方法 |
親族内承継
親族内承継とは、経営者の子や親族に事業を引き継ぐ方法です。後継者との信頼関係のベースが築かれている場合が多く、社内外への説明もしやすいのが特徴です。
従業員として働いてきた親族が経営を継ぐ場合は、企業の経営理念や方針を受け継ぎやすく、従業員や取引先にとっても安心感があります。多くの中小企業が選ぶ承継方法であり、代々世襲してきた企業では受け入れられやすいのがメリットです。
一方で、親族に適任者がいないのに無理に承継させると、経営判断の遅延や失敗を招き、会社の業績が悪化するリスクもあります。また、会社の株式や事業用資産を引き継ぐ際の税負担のシミュレーションも重要です。税理士などの専門家に相談し、早期から対策を進めましょう。
親族外承継
親族外承継とは、社内の役員や幹部社員など、親族以外の人物に事業を引き継ぐ方法です。会社の幹部が育っていて、信頼できる人材がいる場合に適しています。企業の実情を理解した人材に承継できるため、経営の継続性が高いのが特徴です。また、優秀な人材が評価されて経営を担うようになると、他の社員のモチベーション向上にもつながる可能性があります。
後継者には経営者としての資質はもちろん、業種によっては高い技術力も求められる場合があります。後継者の育成には年単位の時間を要するため、人材戦略も含めた長期的な計画が必要です。
第三者承継(M&A)
第三者承継(M&A)とは、他企業や外部の経営者に事業を売却・譲渡する方法です。後継者が親族や社内にいない場合に事業を継続するための選択肢として注目されています。株式譲渡の場合、売却代金が直接個人の収入となるため、引退後の生活資金や新たな挑戦のための資金を確保できます。
ただし、M&Aは会社の理念や従業員を大切にしてくれる理想的な買い手を見つけるのが難しい場合があります。資産の評価や契約など税務や法務の専門知識が必要なため、専門家に相談しながら進めましょう。
京都の後継者不足の相談先
後継者不足は短期的な解決が難しい問題です。現時点で後継者がいない、または決まっていない企業の経営者の方は、専門家への相談をおすすめします。後継者不足の相談ができる専門家は以下のように複数あるため、目的に応じて選択するとよいでしょう。
|
相談先 |
メリット |
デメリット |
|
税理士 |
税務や相続に精通し、承継計画を具体化できる |
法務やM&A交渉は専門外 |
|
弁護士 |
契約書や合意書作成、争いの予防に強い |
税務や経営戦略の提案は対応できないことが多い |
|
金融機関 |
M&Aや資金調達支援が可能。外部ネットワークが広い |
自社利益が優先される提案となる場合がある |
|
京都府事業承継・引継ぎ支援センター |
公的機関で無料・中立的なアドバイスが受けられる |
個別のケースへの支援には限界がある |
|
京都産業21 |
地域企業支援に特化し、経営改善や事業再構築までサポート可能 |
専門的な承継手続きは外部との連携が必要 |
|
商工会議所 |
地元密着型のサポートで、各種専門家やセミナーの紹介が受けられる |
担当者によりサポート内容に差が出る可能性がある |
|
経営コンサルタント |
承継後の成長戦略や収益改善に強みがある |
費用が高額になりやすく、継続的な依頼には注意が必要 |
税理士
税理士は企業の税務や財務、相続の専門家であり、事業承継の計画段階から頼りになる存在です。承継計画の策定にあたり、株式や事業用資産の評価、相続税・贈与税のシミュレーションを行い、具体的な税金対策を提案できます。承継後の財務戦略や節税対策まで継続的にサポートできる点も強みです。
法務やM&A交渉は専門外ですが、弁護士などと連携して対応してワンストップで対応できる場合もあります。
弁護士
弁護士は事業承継における法的な側面全般に対応可能です。株式や事業用資産の譲渡に関する契約書の作成や、事業承継後の紛争予防などに強みを発揮します。また、M&A取引においては、法的リスクの洗い出しや契約交渉をサポートし、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を担います。ただし、税務や経営戦略については税理士との連携が必要な場合が多いです。
金融機関
銀行や信用金庫などの金融機関は、事業承継における資金調達の専門家です。事業用資産や株式を買い取る際の融資、M&Aにおける買収資金提供などの形で事業承継をサポートします。また、幅広い企業とのネットワークを活かし、M&Aのマッチング相手を探す支援も行います。
一方で、自社の融資商品やサービスを優先した提案となる可能性がある点には注意が必要です。複数の金融機関のサービスを比較検討するとよいでしょう。
京都府事業承継・引継ぎ支援センター
京都府事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置した公的な相談窓口です。後継者不在の不安から、具体的な承継方法の検討まで、専門のコーディネーターが無料で相談に応じてもらえます。個別の交渉や手続きの代行は行っていませんが、必要に応じて税理士、弁護士など外部の専門家の紹介が可能です。
京都産業21
京都産業21は京都府の産業振興を目的とした公的機関です。後継者問題だけでなく、中小企業の経営改善や新事業展開、事業再構築など、幅広い経営課題の解決を支援しています。専門家派遣制度を活用することで、経営戦略の策定や技術力の向上、マーケティング支援など、事業承継後の企業をさらに成長させるための助言を受けられるのが特徴です。
実際の承継手続きには外部の専門家との連携が必要ですが、承継後の事業のあり方について総合的に相談したい場合に適しています。
商工会議所
商工会議所は、地域に密着した中小企業の支援団体です。後継者不足に悩む経営者に対し、セミナーや相談会を通じて情報提供を行っています。地元の税理士や弁護士とのネットワークを活用し、専門家を紹介する機能も持ち合わせています。地域の中小企業の状況をよく理解しているため、地元の事情に合ったアドバイスを受けやすいのがメリットです。
ただし、担当者や所属する商工会議所によって、サポート内容や専門性の深さに差が出る場合があります。
経営コンサルタント
経営コンサルタントは、企業の成長戦略や経営改善に強みを持つ専門家です。後継者への承継後、どのように事業を伸ばしていくかという成長戦略の策定や、収益性の改善、新規事業の立ち上げなど、承継後の経営課題に特化したサポートが期待できます。
専門的な知識とノウハウで、経営改革を強力に推進できますが、一般的に費用が高額になりやすいというデメリットがあります。契約内容を明確にし、具体的な成果目標を設定した上で依頼することが重要です。
どの相談先を選んだとしても、実際の承継手続きの際には税理士や弁護士といった専門家との連携が必要な場合が多いです。税理士は、財務・税務・相続の知見を活かし、他の専門家との橋渡し役も担うため、最初の相談相手として適しています。
事業承継で税理士が果たす役割
事業承継は、会社の存続をかけた一大イベントです。税金や財務に関する複雑な課題を解決するにあたり、税理士は経営者の強力なパートナーとなります。相続税や贈与税の対策、企業価値の評価、最適な承継スキームの設計など、税理士が果たす役割は多岐にわたります。ここでは、事業承継における税理士の役割を承継方法別に解説します。
親族内承継の場合
親族間での事業承継では、相続税や贈与税の対策、資産の評価、遺産分割などが大きな課題です。税理士は次のような業務で経営者を支援します。
- 自社株や事業用資産の評価
- 相続税・贈与税の節税対策
- 事業承継税制の適用判断
- 長期的な承継スケジュールの作成
親族内承継で特に重要なのは、相続税や贈与税といった税負担と、後継者以外の親族への配慮です。会社の株式や事業用資産の評価額が不透明なままだと、相続人間に不公平感が生じ、後継者の経営権が不安定になるリスクがあります。税理士が第三者として具体的な数字を示すことで、親族の理解が得られやすくなるでしょう。
親族外承継の場合
社内の役員や従業員への承継では、後継者が株式を買い取るための資金調達や、退任する経営者との間での公正な条件設定などが重要です。税理士は以下のような支援を行います。
- 自社株の評価と移転スキームの構築
- 後継者への取り組み報酬設計と資金計画支援
- 退任に向けた経営者個人の資産設計
- 金融機関への説明資料の作成
税理士は客観的な観点から自社株の適正な評価を行い、公平な譲渡価格を算定します。また、後継者の資金計画や、退任する経営者個人の退職金や資産設計についてもアドバイスが可能です。税負担を最小限に抑える株式移転スキームを構築することで、スムーズな事業承継をサポートします。
第三者承継(M&A)
第三者承継(M&A)では、企業価値の算定や譲渡益課税対策など高度な専門知識が求められます。税理士は、売り手と買い手の双方にとって納得のいく取引を実現するため、以下のような形で関与します。
- 株式価値・事業価値の算定と提示
- M&Aスキームの設計と譲渡益課税対策
- デューデリジェンスへの対応
- 事業承継後の税務・会計対応支援
- 売却後の資金活用プランの作成
株式譲渡や事業譲渡といったM&Aスキームの中から、税負担を最小限に抑えられる最適な方法を提案します。また、買い手が行うデューデリジェンスに備えてリスクを洗い出し、買収価格の引き下げやM&Aの中止といったリスクを回避するのも税理士の重要な仕事です。売却後の資金活用プランニングの支援も可能です。
事業承継の相談先を選ぶポイント
前述のように、事業承継の相談先は複数あります。事業承継の成功は、信頼できる相談先を見つけられるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。相談先を選ぶ際には以下の4つのポイントを確認しましょう。
事業承継の実績が豊富か
事業承継の専門家を名乗っていても、実績が伴っていなければ自社の命運を安心して託すことはできません。逆に、実績が多い専門家は多様なケースから得たノウハウがあるため、より具体的案提案やアドバイスが期待できます。自社と同じ業界や同規模の事例を多く手掛けているかは確認しておきたいポイントです。
事業承継に強い専門家は、Webサイトに実績を掲載しているケースもあります。具体的な事例については面談の際に聞いてみるのもよいでしょう。
料金体系が明確か
事業承継は数年にわたる長期的なプロジェクトです。費用の見通しを立てるため、料金体系が明確な相談先を選ぶと安心です。着手金や中間報酬、成功報酬、成功報酬の算定方法など、どの段階でどのような費用が発生するのかを具体的に説明してくれるかどうかがポイントです。追加費用が発生する可能性も事前に確認しておきましょう。複数の候補から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
金融機関や専門家との連携ができるか
事業承継は、税務、法務、財務、労務など、多岐にわたる専門知識を必要とします。一つの専門家だけで完結するのは難しく、さまざまな分野の専門家との連携が欠かせません。相談先を選ぶ際には、弁護士や税理士、金融機関などとスムーズに連携できるかを確認しましょう。
ネットワークがしっかり構築されている相談先であれば、複雑な承継プロジェクトを一気通貫でサポートできるため、経営者の負担が大幅に軽減されます。
気軽に相談できるパートナーになるか
どんなに専門知識や実績が豊富でも、経営者にとって相談しづらい相手では良い結果が得られない可能性があります。初回の面談では、担当者の話を一方的に聞くだけでなく、あなたの質問や疑問に丁寧に答えてくれるか、想いを尊重してくれるかといった点をしっかりと見極めることが大切です。悔いのない事業承継を実現するために、経営者の想いに寄り添い、二人三脚でゴールを目指せるパートナーを見つけましょう。
後継者不足の悩みは京都の石黒健太税理士事務所にご相談ください!

後継者不足は短期での解決が難しい問題です。対応を先延ばしにするほど廃業のリスクが高まります。大切な従業員やこれまで培ってきた技術を守り、事業を次世代に承継するために、今から対策を講じることが重要です。
「後継者の候補がいない」「どのように承継したらよいかわからない」と不安を感じている経営者の方は、ひとりで悩まずに専門家へ相談しましょう。事業承継には税務、財務、法務などの多様な専門知識が必要なため、早期に信頼できる専門家と連携できるかどうかが成功の鍵です。
京都で後継者不足にお悩みの方は、石黒健太税理士事務所にご相談ください。私たちは単に事業承継の手続きをご支援するだけでなく、承継後の5年、10年先を見据えた成長戦略までご提案が可能です。








