【京都府内の税務署】管轄地域別の開業届の提出先一覧
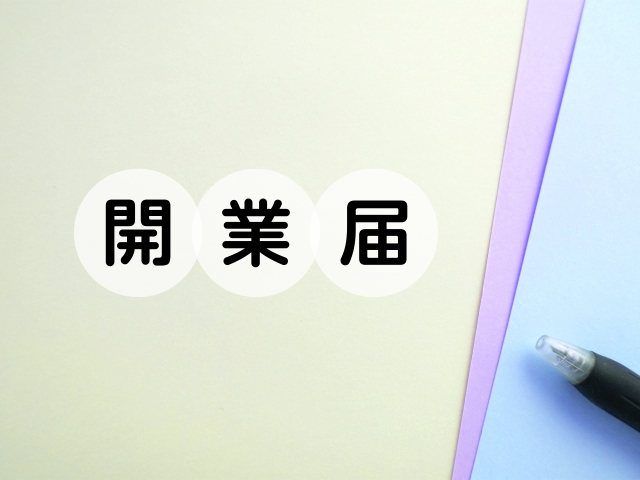
個人事業主の開業届は、原則として納税地を管轄する税務署に提出します。納税地は、原則として住所地ですが、自宅とは別の場所に事業所を設ける場合は、その事業所を納税地とすることも可能です。
たとえば、京都市右京区に住んでいる方の場合、原則として右京区を管轄する右京税務署が提出先です。確定申告書の提出や所得税などの納付も同様に、右京税務署に対して行います。ただし、事業所が下京区にある場合は、納税地を下京区として開業届を下京税務署に提出することも可能です。
京都府の税務署の管轄地域と住所は下記のとおりです。
|
税務署名 |
管轄地域 |
住所(書類の郵送先) |
書類送付先 |
|
右京税務署 |
右京区・西京区・向日市・長岡京市・乙訓郡 |
〒615-0007 京都市右京区西院上花田町10の1 |
住所と同じ |
|
宇治税務署 |
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・久世郡・綴喜つづき郡・相楽郡 |
〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3 |
〒661-8521 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室 |
|
上京税務署 |
北区・上京区 |
〒602-8555 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358 |
住所と同じ |
|
左京税務署 |
左京区 |
〒606-8555 京都市左京区聖護院円頓美町18 |
住所と同じ |
|
下京税務署 |
下京区・南区 |
〒600-8181 京都市下京区間之町五条下ル大津町8 |
住所と同じ |
|
園部税務署 |
亀岡市・南丹市・船井郡 |
〒622-8501 南丹市園部町小山東町平成台1号11 |
〒661-8521 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室 |
|
中京税務署 |
中京区 |
〒604-8482 京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎 |
住所と同じ |
|
東山税務署 |
東山区・山科区 |
〒605-0914 京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5 |
住所と同じ |
|
福知山税務署 |
福知山市・綾部市 |
〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目37番地 |
〒661-8521 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室 |
|
伏見税務署 |
伏見区 |
〒612-0084 京都市伏見区鑓屋町 |
住所と同じ |
|
舞鶴税務署 |
舞鶴市 |
〒624-0913 舞鶴市字上安久240 |
〒661-8521 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室 |
|
宮津税務署 |
宮津市・与謝郡 |
〒626-8571 宮津市字鶴賀2070-14 |
〒661-8521 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室 |
|
峰山税務署 |
京丹後市 |
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147番地12 |
〒661-8521 尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室 |
宇治税務署、園部税務署、福知山税務署、舞鶴税務署、宮津税務署、峰山税務署へ郵送で書類を提出する場合は、大阪国税局業務センター阪神分室宛となる点に注意が必要です。
石黒健太税理士事務所では、京都で開業する個人事業主をサポートしています。開業手続きや、開業後の経営についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
参考:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」
参考:国税庁「税務署所在地・案内(京都府)」
開業届はどこでもらえる?
個人事業主として事業を開始する際に必要となる開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、以下のいずれかの方法で入手できます。
税務署の窓口で入手する
税務署に直接出向いて開業届を受け取る方法です。記載内容について不明点がある場合は、その場で職員に質問できるため、初めて開業する人にとっては心強いでしょう。
書類を入手するだけでなく、必要に応じて事業内容や状況に合わせたアドバイスを受けられる点もメリットです。ただし、確定申告期間など繁忙期には窓口が混雑し、待ち時間が長くなる可能性があります。聞きたいことがある場合は時間に余裕をもって訪問するか、事前に電話で問い合わせるとスムーズです。
国税庁のHPからダウンロードして印刷する
国税庁の公式ウェブサイトから開業届のPDFファイルをダウンロードして、自宅やオフィスで印刷する方法です。インターネット環境とプリンタさえあれば、税務署へ出向く手間や交通費をかけずに税務署へ行かなくても、すきま時間で準備を進められます。
ただし、自分で記入する場合は、国税庁が出している記載例をしっかり確認し、記載漏れや記入誤りがないように注意しましょう。不明点がある場合は、税理士や税務署へ電話で相談するなどして、事前に疑問点を解消しましょう。
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
開業届の提出方法

開業届の提出方法は、窓口に持参・郵送・e-Taxの3つがあります。それぞれの方法には、開業する方の状況や優先事項に応じて、異なるメリットとデメリットが存在します。
窓口に持参して提出する
税務署の窓口に書類を持参する場合、その場で疑問点を確認できます。書類の書き方や添付書類に不安がある場合はその旨を窓口で伝えると、確実に手続きを進められるため、税務に不慣れな方も安心です。
また、提出する書類の控え(コピー)を保管しましょう。令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつは、廃止されています。当分の間は収受印の代わりに、窓口でリーフレットを受け取ることが可能です。開業届の控えは、事業開始を証明する書類として多くの場面で活用できるため、忘れずに受け取りましょう。
一方で、税務署の窓口は基本的に平日の日中しか開いていないため、時間を確保する必要があります。特に2~3月の確定申告の時期などは非常に混雑し、待ち時間が長くなることもあるので、余裕をもって訪問することをおすすめします。
郵送で提出する
記入した書類を郵送提出すると、税務署に行く手間がかかりません。ただし、書類の記載方法を提出時に確認できないため、不備があった際に修正の手間がかかったり、補正に時間がかかって提出期限を過ぎてしまったりするリスクがあります。国税庁のホームページで記入例を確認し、不明点があれば税務署に問い合わせておきましょう。
また、リーフレットを返送してもらうためには、提出用の書類とは別に、返信用封筒(切手貼付・住所氏名記載済)を同封する必要があります。控え用の書類は、収受印が廃止されているため郵送が不要です。
e-Taxで提出する
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、時間や場所を選ばずに提出できることがメリットです。税務署に足を運ぶ必要がなく、スマホとマイナンバーカードがあれば24時間いつでも手続きができます。
e-Taxで提出する場合、送信した書類の控えを電子データで確認・保存することができます。開業の証明が必要なときに紙を探す手間がかかりません。また、データでのやり取りのため、郵送時の紛失リスクや記載不備による再提出の手間が少ないという利点もあります。
e-Taxを利用したことがない場合、最初は操作に戸惑う方もいるでしょう。いつでもできるからといって期限ギリギリに提出するのではなく、余裕をもって提出しましょう。また、現在ほとんどのスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応していますが、念のため、ご自身のスマートフォンの機種が対応しているか確認しておくと安心です。
石黒健太税理士事務所では、開業届をはじめ、開業に必要な手続きを幅広くサポートいたします。手続きに不安がある方や、専門家に任せて手間を減らしたい方は、お気軽にご相談ください。
必要に応じて税務署に提出する書類一覧
開業届の他にも、開業のタイミングで必要に応じて税務署に提出する書類があります。以下の表を参照して、必要な書類は開業届と同時に提出すると手間が省けます。
|
書類名 |
概要 |
提出期限 |
|
所得税の青色申告承認申請書 |
確定申告を青色申告で行い、最大65万円の特別控除などを受けるために必要 |
原則として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで |
|
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
消費税の仕入税額控除を受けるための適格請求書(インボイス)を発行する場合に必要 |
登録を受けようとする課税期間の開始の日の15日前の日まで |
|
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
従業員を雇用し、給与を支払う場合に必要 |
給与の支払いを開始した日、または事務所等を開設・移転した日から1ヵ月以内 |
|
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 |
青色申告を行う個人事業主が、生計を一にする親族に支払った給与を必要経費とする場合に必要 |
青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日まで その年の1月16日以降に新規開業した場合や新たに専従者がいることとなった人は、その日から2ヵ月以内 |
それぞれの書類が必要となるケースや提出期限については、以下で詳しく解説します。
確定申告を青色申告で行うための書類
「所得税の青色申告承認申請書」は、所得税の確定申告を青色申告で行うための書類です。個人事業主が青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除をはじめ、赤字を翌年以降3年間繰り越せる純損失の繰越控除など、税制上の優遇措置を受けられます。
課税所得を圧縮することにより、所得税や住民税の負担を軽減できるため、開業の際に手続きをしておくことをおすすめします。
青色申告のデメリットは、複雑な複式簿記による記帳が義務付けられる点や、貸借対照表と損益計算書の作成が必要となる点です。しかし、近年の会計ソフトの普及により、実際の記帳作業は大幅に簡素化されています。簿記の知識がなく不安な場合は、税理士に依頼することも有効です。
提出期限は、原則として青色申告を適用したい年の3月15日までです。1月16日以降に新たに開業した場合は、開業日から2ヵ月以内に提出する必要があります。期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができず、自動的に白色申告となるため注意しましょう。
関連記事:京都の個人事業主におすすめな税理士の特徴は?費用の目安と相談できることを解説
インボイスを交付するための書類
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、いわゆる「インボイス登録」をして適格請求書を発行できる事業者となるための書類です。顧客が一般消費者ではなく事業者の場合は、検討が必要です。
消費税の納税義務がある事業者は、原則として売上とともに受け取った消費税額から仕入れの際に支払った消費税額を差し引いて納税額を計算します。これを仕入税額控除といい、原則として税額を差し引く分の仕入れ取引について適格請求書が必要です。インボイス登録をしていない事業者との取引は仕入税額控除の対象とならないため、取引先からインボイス登録を求められるケースもあります。
ただし、インボイス登録すると消費税の納税義務が生じます。課税売上高に関係なく納税義務が発生するため、消費税の負担が大きくなりがちです。免税事業者の場合と課税事業者の場合で事業のお金の流れが大きく変わる可能性があるため、事前にシミュレーションすることをおすすめします。
関連記事:インボイス制度後の個人からの仕入れはどうなる?消費税に与える影響と対策を解説
給料を支払う場合に必要な書類
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は従業員を雇用し、給与の支払いを開始する際に提出します。開業の段階で従業員を雇用する場合は忘れずに提出しましょう。
従業員に給与を支払う際は、支払う給与の金額や扶養人数などにより決められた所得税額を控除します。控除した所得税は事業主が預かり、税務署に納めます。月次の給与計算と所得税の納付、年末調整など、必要な事務処理を確認して漏れがないように注意が必要です。
提出期限は、給与の支払いを開始した日、または事務所等を新たに開設・移転した日から1ヵ月以内です。届出書の提出が遅れること自体へのペナルティはありませんが、届出をしないと源泉所得税の納付書がもらえません。
届出が遅れると結果的に源泉所得税の納付も遅れてしまい、延滞税や不納付加算税などのペナルティが発生するリスクがあります。従業員を雇用することになったら、余裕をもって提出準備を進めることが重要です。
家族の給料を経費にするための書類
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」は、青色申告を行っている個人事業主が、生計を一にする親族(配偶者や子どもなど)に支払った給与を事業の必要経費として算入するために必要です。
通常、家族への給与は事業の必要経費になりませんが、この届出書に記載して認められた範囲で経費算入できるようになります。本業としてあなたの事業を手伝ってくれる家族がいる場合、家族で所得を分散させることで世帯全体の税負担を最適化できることがメリットです。ただし、専従者給与の額が業務の内容や他の従業員の給与水準に照らして著しく高額にならないように注意しましょう。
提出期限は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。年の途中で開業した場合や新たに専従者がいることとなった人は、その日から2ヵ月以内に提出する必要があります。期限を過ぎるとその年の専従者給与は経費として認められなくなるため、忘れずに期限までに提出しましょう。
関連記事:専従者とパートはどっちが得?手取りのシミュレーションを解説
京都の開業届は石黒健太税理士事務所にご相談ください!

開業には多くの疑問や不安がつきものです。特に、開業届をはじめとする税務の手続きは専門知識が必要となり、慣れない作業に戸惑う方も少なくありません。困ったときは、早めに税理士に相談することを強くおすすめします。
石黒健太税理士事務所は、京都で多くの法人や個人事業主の開業をご支援しています。お客様の状況や事業のビジョンを丁寧にヒアリングし、開業時に必要な手続きのトータルサポートが可能です。複雑な手続きは税理士が代行するので、事業主の事務負担が減り、本業に専念できます。
また、開業後も、創業融資や補助金申請の支援、顧問税理士業務、財務戦略コンサルティングなど幅広いサービスで事業の成長を強力にサポートします。弊所自身も創業から5年で年商1億円を突破した成長企業であり、実践的な経営アドバイスができるのも強みです。








