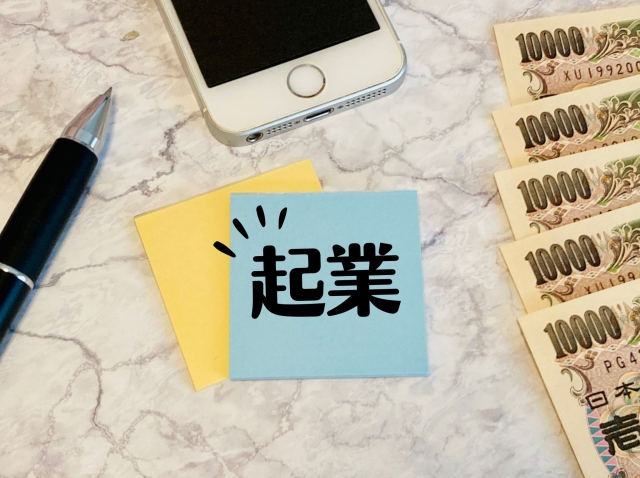京都の開業相談は誰にする?

開業を成功させるには、目的に応じた相談先を選ぶことが重要です。京都には商工会議所や金融機関、士業など開業支援の相談先が複数あります。以下で相談先ごとの特徴を紹介します。
|
相談先 |
特徴 |
|
京都商工会議所 |
開業準備から経営支援まで対応 |
|
金融機関 |
創業融資と資金繰りの相談窓口 |
|
税理士 |
税務・会計・資金計画を総合的に支援 |
|
司法書士 |
会社設立登記の専門家 |
|
行政書士 |
許認可申請手続きをスムーズに支援 |
京都商工会議所:幅広い相談がしたい方向け
開業準備を何から始めればよいかわからない初期段階の方から、すでに事業を開始した方まで、幅広い層の事業者を支援しています。特定の業種に限らず、開業に関する一般的な相談を受け付けているため、最初に相談する場所としても適しています。
個別相談だけでなく、創業塾や経営課題解決セミナーなどのイベントも豊富です。創業計画書の作成方法や販路開拓の手法など実践的な内容を学びたい方におすすめです。
地元企業や他の起業家とのネットワーク構築の場も提供しています。横のつながりを作っておくことで、地域に根ざしたビジネスを進めやすくなるでしょう。
金融機関:融資を考えている方向け
開業資金を自己資金だけでまかなえない場合も多いものです。特に、実店舗を構える場合や仕入れが発生する業種では、設備投資や運転資金をどう工面するかが大きな課題となります。
京都の地方銀行や信用金庫では地域密着型の創業支援を行っており、創業融資を検討している方の有力な相談先です。創業者向けの融資制度では、金利や返済条件の面で優遇される場合もあります。
ただし、融資を受けるためには明確な事業計画と収支の見通しが必要です。金融機関の担当者は計画の整合性や実現可能性を厳しく見ています。早期に相談し、必要な内容や資料を確認しておくことが成功のカギです。
税理士:事業計画から税金の悩みを相談したい方向け
税理士は、単なる税金の専門家ではありません。開業前後の資金管理や会計はもちろんのこと、長期的な経営戦略まで見据え、経営者の頼れるパートナーとして伴走支援を行います。
事業計画の策定にあたっては、資金調達、収支予測、損益分岐点など、財務的な視点から実現可能性の高い計画の策定が可能です。具体的な売上目標や経費の見込みをプロの視点で検証し、金融機関などの第三者に納得してもらいやすい内容に磨き上げます。
税務に関しては、開業時の手続きの代行に限らず、顧問契約を結ぶことで毎月のお金の流れをチェックし、キャッシュフローの最適化や資金繰りの改善について、きめ細やかな経営アドバイスを提供します。
司法書士:会社設立の手続きを相談したい方向け
株式会社や合同会社として開業する場合、法人設立登記が必要です。登記の前提として、会社のルールブックである定款の作成や出資金の払い込みなどの手続きを行います。さらに、印鑑証明書などの必要な書類を集めて登記申請する必要があります。登記手続きは煩雑で、書類に不備があると申請が却下されるリスクもあり、初めての方には難しいのが実情です。
司法書士は登記のプロフェッショナルとして、会社設立に必要な書類の作成から法務局への申請代行まで総合的にサポートします。会社の種類(株式会社、合同会社など)や事業内容に応じた定款の作成、出資金の払込証明の整理など、法律的に正確かつ効率的に進められるのが強みです。
関連記事:合同会社と株式会社の違いは?向いている会社形態と会社設立で失敗しないためのポイント
行政書士:許認可申請の相談がしたい方向け
飲食業、建設業、運送業など特定の業種では、営業するために許認可や免許が必要です。許認可の要件を満たすかどうかの確認や、申請書類の作成は複雑で負担が大きい手続きです。申請書を提出した後に、追加書類の提出などを指示されるケースも少なくありません。
行政書士は、許認可申請の専門家として、必要な書類の作成から申請代行までを一貫して引き受け、開業者の負担を大幅に軽減します。あなたが取得したい許認可の要件や審査のポイントを熟知している行政書士に相談することで、申請の成功率がぐっと上がるでしょう。
許認可の遅延は開業そのものの遅れにつながるため、開業を考えた段階で許認可申請についても準備を進めておくことをおすすめします。
税理士に開業相談するメリット
開業前の不安や疑問を解消するうえで、税理士は心強いパートナーです。以下では、税理士に開業相談することによって得られる具体的なメリットをご紹介します。
説得力のある事業計画書が作成できる
事業計画書は、事業の全体像や将来の展望をまとめた重要な書類です。金融機関から融資を受ける際や、補助金申請の際に提出を求められます。
審査の際は、事業に収益性や成長性が見込めるかといった点や、借り入れた資金を計画通りに返済できるかという返済能力も厳しく見られます。数字に基づいた実現可能性の高い計画は、第三者にも納得されやすいため、融資や補助金採択の可能性が高まるでしょう。
すぐに提出の予定がない場合も、経営者自身の事業のビジョンを言語化することで経営の方向性が見えやすくなります。融資申請に強い税理士に相談することで、金融機関の視点で売上予測や経費の見積もり、資金繰り計画などの数字面に説得力が生まれます。
関連記事:事業計画書のスムーズな作り方とは?わかりやすい方法を解説
法人と個人事業主の違いがわかる
開業にあたっては、法人を設立するか個人事業主でスタートするかを選択します。税務上の違いや社会保険の取り扱い、事業責任の範囲など、両者には大きな違いがあります。小規模な事業の場合、無理に法人設立せず、個人事業主として開業して一定の利益を上げられるようになってから法人に移行するのが一般的です。
税理士はそれぞれのメリット・デメリットを比較したうえで、事業内容や資金状況に合った最適な選択肢を提案してくれます。
関連記事:合同会社と個人事業主の違いは?兼任する注意点とスムーズに切り替える方法
税金対策を意識した開業ができる
開業当初から税金対策を意識しておくことで、無駄な出費を防ぐことができます。たとえば青色申告制度を活用すれば、個人の場合は最大65万円の控除を受けることができるほか、赤字の繰越控除などの恩恵もあります。
ただし、開業届の提出や青色申告承認申請書の提出期限があるため、早めの対応が不可欠です。税理士に相談すれば、スムーズに必要な申請が行えます。
参考:国税庁「青色申告制度」
開業の手間が削減できる
開業には、開業届や各種届出書の作成、金融機関とのやり取り、会計ソフトの選定など、多くの作業が伴います。税理士に依頼すれば、こうした煩雑な事務作業を任せられるため、事業の準備に集中することが可能になります。特に本業が忙しい方にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
開業後も継続してサポートを依頼できる
開業はスタートにすぎません。日々の記帳、毎月の試算表作成、資金繰りの見直し、確定申告など、経営者がやるべきことは山積みです。税務や財務の知識がなければ、会社の経営状態を正しく把握し、適切な経営判断を下すのは難しいものです。また、時間のない経営者にとっては、煩雑な事務が本業の妨げになることもあります。
信頼できる税理士と顧問契約を結ぶことで、帳簿の管理や申告書作成を任せられるだけでなく、専門家の視点から節税や経営のアドバイスを受けられます。
税理士に開業相談するデメリットは費用

開業時に税理士へ相談することには多くのメリットがありますが、デメリットを挙げるとすれば、費用がかかる点です。限られた自己資金の中から税理士への報酬を支払うのがためらわれる場合もあるでしょう。
税理士への開業相談は、初回相談を無料としている事務所が多数あります。2回目以降の相談は、顧問契約や特定のサービスの契約料金に含まれ、相談料は別途かからないケースが多いです。単発の相談として継続する場合は、1時間あたり5,000円~10,000円程度が相場です。
「会社設立支援パック」など、法人設立登記や開業届提出など開業時に必要な複数のサポートをセットにしたサービスを行っている場合もあります。サービス内容は事務所によって異なりますが、法定費用とは別に10万円~30万円前後の報酬が発生するのが一般的です。
顧問契約を結ぶ場合、月額顧問料として1~3万円程度が継続的に発生します。訪問回数や記帳代行の有無など、税務顧問サービスの内容を確認しましょう。
税理士報酬は決して少額ではないため、開業する段階での大きな支出に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、節税効果や資金調達の成功率アップを考慮すると、結果的に費用以上のリターンを得られることも珍しくありません。必要な部分だけスポットで依頼する、無料相談を活用するなど、無理のない範囲で専門家を味方につける工夫も可能です。
関連記事:京都の個人事業主におすすめな税理士の特徴は?費用の目安と相談できることを解説
開業相談するタイミング
開業に向けての相談は、いつ始めるのがベストなのでしょうか。多くの方が、ある程度決まってから相談しようと考えがちですが、それではかえって準備不足や手戻りを招いてしまうこともあります。開業しようと思い立った時が相談のタイミングです。
開業アイデアが浮かんだとき
まだ事業の形が固まっていなくても、起業したいと思った時が、最初の相談の好機です。自分のビジネスアイデアに収益性や将来性があるのか、専門家の視点でアドバイスをもらえます。
また、個人と法人のどちらが向いているか、資金はどれくらい必要かといった基礎的な知識を得られるため、具体的なアクションにつながります。アイデアが浮かんでも、ひとりで悩んでやっぱりやめようと諦めてしまうのはもったいないことです。
融資を申し込む前
創業融資を検討している場合は、融資申請の直前ではなく、事業計画書を作り始める前の相談をおすすめします。融資支援に強い税理士は金融機関の審査基準を熟知しているため、事業計画の立て方そのものにアドバイスが可能なためです。
たとえば、日本政策金融公庫の融資では、自己資金の割合や返済可能性、収支計画の現実性などが重視されます。事業主だけでは、熱意はあっても根拠ある数字を示すのが難しいため、融資審査に通らず、資金がショートするリスクもあります。税理士のサポートを受けることで、信頼性の高い事業計画書を提出でき、結果的に審査通過率が高まるでしょう。
会社を辞める前
開業はタイミングと準備が大切です。会社を退職してから動き出すのでは、精神的にも経済的にも大きなリスクを背負うことになります。退職時期を決める前に相談し、まずは開業後の事業の見通しをもちましょう。
会社を辞める前に相談することで、サラリーマンとして安定した収入を得ながら開業に向けた準備ができます。開業に必要な資金を把握し、積立を始めるのもよいでしょう。自己資金が多いほど、事業を始めてからの資金繰りに余裕が生まれます。
サラリーマンが開業するまでの5ステップ

会社を辞めて、自分のビジネスを始めたいと考えるサラリーマンの方は少なくありません。しかし、実際に開業に踏み出せる人はわずかです。その理由は、多くの人が何から始めていいかわからないからと言えます。ここでは、サラリーマンからの開業を成功に導くための5つのステップを紹介します。
ステップ1:ビジネスアイデアを具体化する
開業の第一歩は、自分が何をビジネスとしていくかを明確にすることです。誰も考えたことのない革新的なビジネスモデルを目指す必要はありません。これまでの経験やスキルを活かせる仕事は何か、誰の・どのような悩みを・どのように解決できるのかといった視点で考えるとわかりやすいでしょう。
専門家に相談する際は、ビジネスアイデアが完璧に形になっていなくても問題ありません。むしろ、専門家と一緒にアイデアを整理し、客観的な視点で事業化の可能性を検討することが、確実なスタートにつながります。
関連記事:起業したいけどアイデアがないときの対策は?起業アイデアが思いつかないときの対策と成功率を高めるポイント
ステップ2:資金調達をする
開業の際に立ちはだかるのが資金の壁です。業種や業態によりますが、開業の際には事務所や店舗の賃料、設備や備品の購入費、広告宣伝費などのまとまったお金が必要です。事業が軌道に乗るまでの運転資金や、生活費も確保しておく必要があります。
可能な限り、自己資金を用意するのが望ましいですが、自己資金だけではまかないきれない場合も珍しくありません。日本政策金融公庫や金融機関から融資を受ける選択肢もあります。京都府の起業支援事業費や中小企業向け制度融資などの活用も検討し、必要な資金を調達しましょう。
事業規模や業種などによって、必要資金が異なります。税理士などの専門家に相談して必要な資金の額を正確に見積もり、適切な資金調達方法を選択することをおすすめします。
関連記事:起業資金の最低額の目安は?起業資金不足の対策と50万円あれば始められるビジネス7選
ステップ3:事業形態を決める
個人事業主か法人か、法人を設立する場合は株式会社か合同会社かを選択します。将来の方向性に大きな影響を与えるため、慎重に検討すべきポイントです。
個人事業主は開業手続きが比較的簡単で、費用もほとんどかかりません。ただし、一定以上の利益が出るようになると税負担が増える可能性があります。法人と比べると社会的信用が低く、金額の大きい取引や融資が難しい場面もあります。
一方、法人化すると、節税対策の選択肢が広がる、取引先や金融機関からの信用が高まるというメリットがあります。ただし、設立費用や個人事業主にはないランニングコストも無視できません。
小規模な事業の場合は、まずは個人事業としてスタートし、事業が安定してきた段階で法人化する流れが一般的です。とはいえ、ベストな選択肢は状況によって異なるため、専門家に相談しながら決めると安心です。
関連記事:会社設立と個人事業主はどっちが得?法人と個人事業主の違いをわかりやすく解説
ステップ4:円満退社をする
サラリーマンの仕事と並行して開業準備を進めていたとしても、いずれは会社を辞めて本格的に独立するタイミングがやってきます。ここで大切なのが、円満に退職することです。
サラリーマン時代に築いた人間関係は、将来的な人脈やビジネスチャンスにつながる可能性もあります。退職時の印象が悪ければ、チャンスを自ら手放してしまうことにもなりかねません。
円滑に業務の引き継ぎが行えるように、退職の意思は期間に余裕をもって伝えます。引き継ぎや社内手続きを丁寧に進め、退職時にはお世話になった同僚や上司に感謝の気持ちを伝えましょう。
ステップ5:事業を始める
すべての準備が整ったら、開業の手続きを行い、事業をスタートさせます。個人事業主の場合は、税務署に開業届や青色申告承認申請書を提出します。法人の場合はまず設立登記申請を行い、登記が完了してから税務署などへの届出を行います。専門家と連携し、必要な手続きを漏れなくスムーズに進めましょう。
開業はゴールではなく、スタートラインです。事業が継続・成長していくためには、日々の経営判断や資金管理、集客戦略など、経営者としてやるべきことがたくさんあります。だからこそ、信頼できる専門家の存在が大きな支えとなるのです。
サラリーマンが開業を失敗しないためのポイント
現在サラリーマンとして働いている方が京都で開業して成功するために、抑えておきたいポイントがあります。どれもすぐに取り組める実践的な内容ですので、開業準備に役立ててください。
開業の目的をはっきりさせる
「あなたはなぜ開業するのですか?」と聞かれて即答できますか? スキルを活かしたい、自由に働きたい、もっと稼ぎたいなど、開業の動機は人それぞれですが、自分自身が目的を明確にもっていることが大切です。目的があいまいなまま開業してしまうと、経営者自身が事業の方向性を見失うリスクが高まります。
具体的に、誰のどのような課題を解決したいのか、そのために自分のどんな強みや経験を活かすのかといった点を深く掘り下げてみましょう。明確な目的があると、困難にぶつかっても信念をもって事業を続けていくための原動力となります。
副業や小さな規模からスタートする
サラリーマンを退職して起業するイメージを持っている方も多いかもしれませんが、副業から始める人も増えています。エンジニアやデザイナー、ECサイト運営などは、実店舗を持たずに小資本で始められるため、副業からでもスタートしやすい業種です。
サラリーマンの収入もあるため、売上をあげなければ生活していけないというプレッシャーがないことがメリットです。市場で何が求められているかを見極めながら、事業をじっくり育てていけるでしょう。
関連記事:副業サラリーマンが一人で会社を作るメリットは?会社員しながら社長になる注意点
家族の理解を得る
家族がいる場合、開業は自分だけの問題ではありません。サラリーマンを辞めて開業することで、家庭の収入やライフスタイルに直接的な影響を与えます。事前によく話し合い、家族の理解を得ておくことが成功の鍵です。
家族の反対を押し切って開業すると、家族に「こんなはずではなかった」と思われて関係が悪化してしまうおそれがあります。最初の半年は収入が減るかもしれない、仕事の時間帯が不規則になるかもしれないなど、現実的な話も正直に共有しましょう。
事前にわかっていれば、家族としても安心感が得られ、協力体制も築きやすくなります。家族の支えは、困難な時期を乗り越える上で大きな力になるはずです。
生活費と事業のお金をきっちり分ける
開業後に多いのが、お金の管理をきちんとしないことによるトラブルです。特に個人事業主の場合、家計の財布と事業の財布を分けて管理していないために、何にいくら使ったのかがあいまいになってしまうケースが見られます。
事業としてのお金の流れが見えないと、資金繰りが悪化したり、税務調査で経費が否認され追徴課税となったりするリスクがあります。売上がないわけではないのに、資金管理がずさんで事業継続が難しくなる場合もあるのが現実です。
たとえば、生活費と事業のお金をきっちり分けるには、開業と同時に、事業専用の銀行口座とクレジットカードを用意しましょう。日々の売上や経費はすべて記帳し、月単位で収支を見直す習慣をつけるとよいでしょう。
基本的な「お金の見える化」が、経営を安定させる第一歩です。もし自分で管理するのが難しいと感じる場合は、税理士に依頼することも有効な選択肢の一つです。
早めに専門家に相談する
開業は一生に何度もあることではないため、わからないことだらけなのは当然です。無理に自分で解決しようとせず、わからないことや不安なことがある場合は思い切って専門家に相談するのが近道です。
税務・法務・資金計画・補助金・許認可など、開業には想像以上に多くの手続きが必要です。必要な手続きを見落としてしまうと、経営上のリスクを背負うことになったり、事業開始が遅れたりする可能性があります。
開業を考え始めたら、税理士や司法書士、行政書士などの専門家に早い段階で相談しましょう。手続きの漏れを防ぐとともに、事務処理の手間やコストを削減し、経営者が安心して事業に集中できる環境を整えられます。
京都の開業は石黒健太税理士事務所にご相談ください!

石黒健太税理士事務所は、京都を拠点として200社以上の開業をご支援してきました。豊富な知見を活かし、事業計画の策定から金融機関への融資支援、法人設立の手続き、日々の税務・経営相談まで、一貫してサポート可能です。
弊所自身も開業から5年で年商1億円を突破した経験のある成長企業です。自らの経験に基づいた経営ノウハウで、税務・財務の面から実践的なアドバイスをいたします。
開業はスタートラインです。事業の継続と成長のため、開業後も経営者のパートナーとして事業の成長を加速させるべくご支援します。お電話やLINE、Chatworkでのお問い合わせも可能です。開業を考えている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。