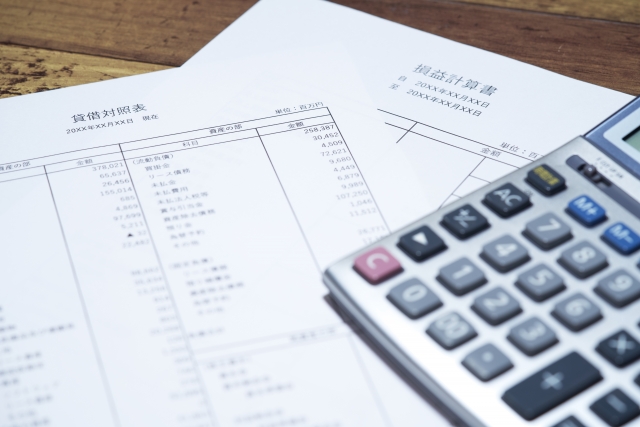京都府の産業の特色と税務調査の関係
京都には、観光地としての特性から「現金での支払いが多い業種」が多く存在しています。たとえば、個人経営の飲食店や土産物屋、旅館などです。これらの業種は、売上がレジに記録されずに処理されるリスクがあると税務署から見なされやすく、税務調査の対象になりやすい傾向があります。いわゆる現金売上の除外です。
国税庁が公表しているデータでは、「税務調査で不正が見つかりやすい業種」の統計が出ています。以下は、その上位10業種と特徴です。
|
順位 |
業種目 |
不正発覚割合 % |
特徴 |
|
1 |
バー・クラブ |
59.0 |
現金取引が多く、深夜営業や従業員の入れ替わりが激しい業界。帳簿が簡易であることも多く、売上除外が起こりやすい。 |
|
2 |
その他の飲食 |
42.3 |
個人経営が多く、レジ管理や帳簿記録が簡素。現金売上の除外がしやすいため、不正の温床になりやすい。 |
|
3 |
外国料理 |
38.8 |
外国人オーナーやスタッフが多く、帳簿管理が不慣れなケースがある。現金商売で、経費処理が不明確なことも。 |
|
4 |
土木工事 |
31.5 |
下請け・孫請けの構造が複雑で、外注費や支払調書の処理ミスが起きやすい。現金での支払いも多い。 |
|
5 |
美容 |
30.8 |
小規模店舗が多く、現金決済比率が高い。店販商品との売上区分や、スタッフ報酬の管理が不明瞭なことがある。 |
|
6 |
一般土木建築工事 |
29.5 |
規模が大きい分、契約金額のズレや売上の期ズレが発生しやすい。 |
|
7 |
職別土木建築工事 |
29.5 |
特定作業のみを請け負う形態が多く、外注先の管理が甘くなりがち。 |
|
8 |
廃棄物処理 |
29.2 |
現金取引・個別契約が多く、帳簿が簡易になりがち。契約の口頭合意も多く、書類不足が目立つ。 |
|
9 |
船舶 |
28.8 |
海外との取引や、複数国通貨のやりとりがある。活動地域が広く、帳簿が煩雑化しやすい。 |
|
10 |
その他の 道路貨物運送 |
28.8 |
個人事業主が多く、ガソリン代・車両費などの私的利用が混在しがち。記帳が簡略なケースも。 |
参考:京都府「統計で見る京都府の産業」
参考:国税庁「令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要」
京都府は観光業がさかんで、全国平均と比べて、宿泊業・飲食サービス業の「特化係数」が高い地域です。特化係数とは、ある地域で特定の産業がどれだけ集中しているかを示しています。
つまり、京都は飲食店や旅館、観光業関連のサービス業が多く集まる都市であり、それらは税務署が重点的に見る「不正発見割合の高い業種」に該当しやすいのです。特に京都市内の繁華街や観光地周辺では、小規模な飲食店や旅館などが集中しており、帳簿管理やレジ管理が不十分なケースも散見されます。
こうした背景から、京都で事業を行う方は、「自分の業種は税務署からどう見られているか」を意識し、普段から帳簿や領収書をしっかり残す、税理士に定期相談するなど、適切な準備が大切です。
税務調査が行われやすい時期の目安

税務調査は、ある日突然やってくるように思われがちですが、じつは調査が行われやすい時期があります。もちろん、正確な日付や月が決まっているわけではありませんが、毎年おおよそ「この時期に調査が増える」といわれるタイミングがあります。
税務調査が行われやすいとされている主な時期は、次の3つです。
9月〜11月(秋)
1年の中でも、税務調査が最も集中するのがこの「秋の時期」です。税務署の職員は6月に人事異動があり、その後の夏を経て業務に本格的に取りかかるのが9月以降と言われています。調査の準備が整い、本格的な訪問調査が始まるタイミングでもあるため、調査件数も多くなります。秋はまさに「税務調査シーズン」といえるでしょう。
4月~5月(確定申告後)
個人事業主の場合、確定申告が終わる3月はひとつの節目ですが、税務署にとっては「申告内容のチェック」が本格化する時期でもあります。そのため、4月~5月は、申告内容を確認した税務署が「不備や疑問点がある」と判断した案件に対して、調査の準備を始めるタイミングとなり、調査が多くなる時期といえるでしょう。
特に、前年と比べて売上や経費に大きな変動があった場合や、申告書の記載に不自然な点がある場合などは、調査対象として選ばれやすくなります。確定申告が終わったからといって安心せず、提出後もしばらくは気を引き締めておくことが大切です。
決算期の数ヶ月後
法人の場合、決算が終わって申告書を提出した「数ヶ月後」も注意が必要です。提出された申告書の内容を税務署がチェックし、「不自然な点がある」「過去との比較で違和感がある」などと判断されると、その後に税務調査の連絡が来ることがあります。たとえば、3月決算の会社なら、調査の連絡が来るのは6月〜9月頃になるケースが多いでしょう。
税務調査の対象に選ばれやすい会社の特徴
税務調査は、完全にランダムで行われるわけではありません。実際には、「調査の必要性が高い」と判断された会社から選ばれます。では、どんな会社がその対象になりやすいのでしょうか?代表的な5つのパターンを紹介します。
売上が急激に伸びている
売上が大きく伸びていることは、ビジネスの成長を示す良いサインです。しかし、税務署の目線では、「何か申告ミスや隠れた所得があるのでは?」と疑われるポイントにもなります。
たとえば、前年度の売上が1,000万円だったのに、今年は急に2,000万円になっていたとすると、「理由は正当なのか?帳簿に不正がないか?」と、調査の対象にされやすくなります。
特に、経理の体制が整っていない中小企業では、売上と経費の記録にずれが出やすいため注意が必要です。
関連記事:売上高は決算書のどこを見る?売上高と売上の違い・経営者が決算書に強くなる方法
同業他社と比べて経費率が高い
税務署は、同じ業種内での「平均的な経費率」を把握しています。そのため、他社と比べて明らかに経費率が多い場合、「不自然な経費の計上があるのでは?」と疑われます。
たとえば、飲食店で売上の割に仕入れや人件費が異常に多い、というケースでは、家事関連費(プライベートの支出)を経費として計上している可能性があると見なされやすいのでしょう。
もちろん正当な理由があれば問題ありませんが、説明できるように証拠を残す(領収書やメモなど)ことが重要です。
経費率などは、定期的に見直すと異常値に気づくことがあります。月次報告を利用して、自社の状況を随時確認することが重要です。
関連記事:月次報告とは?経理初心者が月次決算をするメリットと会社の成長を加速させるポイント
過去に申告漏れなどを指摘されたことがある
一度、税務調査でミスや申告漏れが指摘された場合、「再び同じことをしていないか?」という視点で定期的にチェックされる対象になります。いわばマークされている状態です。
とくに、前回の調査で悪質なミス(意図的な除外など)があった場合は、短期間で再調査が入ることもあります。そのため、一度指摘されたら「しっかりと改善しているか」を書類や数字で示すことが大切です。
申告内容に不審な点がある
税務署は、毎年提出される申告書をチェックしています。その中で、次のような「不自然な点」があると調査の対象となるでしょう。
・売上がゼロなのに経費だけが大量にある
・毎年赤字が続いているのに、事業が継続している
・申告書の記載ミスや添付書類の不足が多い
これらは、「何か隠しているのでは?」という疑念を持たれる原因となります。間違いや記入漏れを防ぐためには、プロのチェックを受けるのも一つの手です。
税理士が関与していない
個人や小規模法人などで、税理士に依頼せず、自分で申告を行っているケースもあります。しかし、その場合、税務署としては「帳簿の作り方が甘い可能性がある」と見ることもあるでしょう。
税理士が関与している申告は、一定の信頼性があると判断されやすくなります。逆に、税理士がいないと「プロのチェックが入っていない分、ミスやごまかしがあるかも」と疑われやすくなるかもしれません。
税務調査への不安を減らすためにも、日頃から税理士と連携を取り、正確な帳簿管理や申告を行うことが大切です。京都で信頼できるパートナーをお探しなら、石黒健太税理士事務所にお気軽にご相談ください。初めての方でも安心してご利用いただけます。
関連記事:会社が税理士を雇わないリスクは?税理士なしで法人決算をする方法と費用を抑えるポイント
税務調査で特にチェックされる項目

税務調査では、帳簿や書類全体を細かく見るというよりも、「チェックポイント」となる項目に重点を置いて確認が行われます。ここでは、特に指摘されやすい項目と、その注意点について解説します。
売上の計上漏れと期間のズレはないか
税務署が特に気にするのが「売上のごまかし」です。たとえば、ある取引を本来の月ではなく、翌月や翌期にズラして計上している場合、「期間のズレ」として問題視されます。また、そもそも売上自体が計上されていなければ、脱税とみなされる可能性もあります。
【注意点】
・請求書の発行日、入金日、納品日などを正確に管理する
・帳簿と実際の取引が一致しているか定期的に確認する
・月末・期末の売上は特に注意してチェックする
棚卸に不正な操作がされていないか
「棚卸(たなおろし)」とは、期末時点で手元にある商品や材料の在庫を数えることです。これを意図的に多くしたり少なくしたりして利益を操作するケースは、税務署に注目されます。
たとえば、在庫を少なく見せれば「仕入が多かった=利益が少ない」となり、納税額を減らせます。これが不正とされるのです。
【注意点】
・実際に在庫を数える「実地棚卸」を行う
・数量や金額の根拠を明確に記録する
・現物と帳簿の数字が一致しているか定期的に確認する
プライベートな経費が混在していないか
事業で使ったものだけが「経費」として認められます。プライベートな支出(家族の食事、旅行、個人の買い物など)を経費にしてしまうと、税務署から厳しく指摘されます。
たとえば、仕事で使う車にかかったガソリン代のうち、実際は家族のドライブにも使っていた場合、その分は経費になりません。
【注意点】
・経費の使用目的をメモしておく
・クレジットカードやスマホなどは事業用と私用で分けて使う
・領収書だけでなく「使途」の説明もできるようにする
修繕費と資本的支出の区別は適切か
修理や設備投資にかかるお金には、「修繕費」と「資本的支出」の2種類があります。修繕費はその年の経費になりますが、資本的支出は固定資産として数年にわたって経費化(減価償却)されるものです。
たとえば、車の壊れた部分の部品交換は「修繕費」ですが、車のエンジンを新しく取り替えた場合は「資本的支出」とされることがあります。
【注意点】
・修理や改修の内容を記録し、内訳を把握しておく
・請求書の明細を確認し、どちらに該当するか判断する
・判断に迷ったら税理士に相談する
役員報酬や役員賞与は適切か
役員に支払うお金(報酬や賞与)は、金額・支払い方法・タイミングが厳密に決まっていないと、経費として認められないことがあります。
とくに「役員賞与」は、事前に届出を出していないと全額が経費として否認されるケースも多く、注意が必要です。
【注意点】
・役員報酬は毎月同額で支払い、変更は議事録を残す
・役員賞与を出す場合は「事前確定届出給与に関する届出」を税務署に提出する
・非合理な増減や突発的な支払いは避ける
関連記事:中小企業の役員報酬の相場は?役員報酬が高すぎる中小企業の注意点と手取りをシミュレーション
給与とみなされる外注費はないか
外注費として処理しているお金でも、実質的に従業員のような働き方をしている場合、「給与」とみなされ、源泉徴収漏れを指摘されることがあります。
たとえば、勤務時間や仕事内容が社員と同じような外注先がいた場合、税務署から「これは外注じゃなく給与では?」と判断されるため注意しましょう。
【注意点】
・外注先とは業務委託契約書を交わしておく
・勤務時間や指揮命令の有無に注意する
・完全に業務を任せているかを整理し、立場を明確にする
収入印紙は貼付されているか
契約書や領収書の中には、一定金額以上の場合に「収入印紙」を貼る義務があるものがあります。これを忘れると、過怠税(ペナルティ)を課せられることがあります。
たとえば、5万円以上の領収書には原則として印紙が必要です(ただしクレジットカード払いは例外)。
【注意点】
・契約書・領収書の種類ごとに印紙が必要か確認する
・印紙税がかかる金額の基準(例:5万円以上の領収書)を把握する
・印紙の貼り忘れがないように定期的に書類を見直す
参考:国税庁「クレジット販売の場合の領収書」
税務調査の不安解消は日頃の準備が大切

「税務調査」と聞くと、不安になったり身構えてしまう方も多いと思います。でも実際は、きちんと日頃から準備していれば、必要以上に怖がる必要はありません。
ここでは、調査に備えてどんなことを心がけておけばよいのか、4つのポイントで解説します。
不正をしていなければ心配することはない
まず大前提として、不正な申告や意図的なごまかしをしていなければ、税務調査はそれほど恐れるものではありません。調査が入ると聞くと「何か見つかるのでは」と不安になってしまう方も多いと思いますが、正しく帳簿をつけ、きちんと申告していれば、堂々としていて大丈夫です。
税務署の職員も敵ではなく、あくまで「正しく申告されているかを確認する」ために調査を行っているだけです。あわてず、落ち着いて対応することが大切です。
取引を正確に記録し帳簿をきちんと作成する
税務調査では、帳簿の内容が最も重視されます。取引の金額や内容が正確に、かつわかりやすく記録されているかどうかがチェックされるのです。記録があいまいだったり、後から無理やり帳尻を合わせたような帳簿では、税務署に「本当にこの申告は正しいのか?」と疑われやすくなります。
日々の売上や経費をできるだけリアルタイムで記帳し、必要に応じて内容をメモなどで補足しておくことが重要です。また、会計ソフトを活用することで、記録ミスの防止や見直しもスムーズになります。
証拠書類を整理し保管する
帳簿と同様に重要なのが、取引の内容を裏付ける証拠書類の存在です。たとえば、領収書やレシート、請求書や納品書、契約書、そして銀行の振込明細や通帳のコピーなどは、実際にその取引があったことを示す大切な証拠になります。これらの書類は、紙で保存しても、スキャンしてデジタルで保存することも可能です。
大切なのは、いざ調査のときにすぐに取り出せるよう、年度別や取引先別に整理しておくことです。普段から整頓しておけば、いざというときにも慌てずに済みます。
税理士に日頃から相談できる体制を作る
もっとも安心できるのは、わからないことがあればすぐに相談できる税理士が身近にいることです。たとえば、「これは経費にしてよいのか?」「この処理方法で問題ないか?」といった日常の疑問をその都度解決できる環境があれば、大きなミスや申告漏れを防ぐことができます。
さらに、税理士が申告書の作成に関与していると、税務署も「専門家が関与しているなら問題ないだろう」と判断しやすくなり、調査対象から外れるかもしれません。
連絡が取りやすく、気軽に相談できる税理士を選び、月に一度など定期的に帳簿をチェックしてもらう仕組みを作ることで、調査があった場合でもスムーズに対応できるでしょう。税務調査時には、税理士が同席して対応してくれることもあり、大きな心の支えになります。
京都で税務調査に不安がある方は石黒健太税理士事務所にご相談ください!

税務調査は、どんなに正しく申告していても「突然やってくる」ことがあります。そのため、事前に備えておくことがとても重要です。「自分の帳簿は大丈夫だろうか?」「税務署に説明できるか不安」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ石黒健太税理士事務所にご相談ください。
石黒健太税理士事務所では、京都で数多くの税務調査対応を行ってきた実績があり、調査に関するアドバイスはもちろん、帳簿や証拠書類のチェック、調査当日の立ち会いまで、しっかりとサポートいたします。初めて税務調査を経験する方でも安心して対応できるよう、丁寧にご説明いたします。
不安なままひとりで悩まず、プロの力を借りて万全の準備をしておきましょう。お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。あなたの大切な事業を、税務の面からしっかりサポートさせていただきます。
まとめ
税務調査と聞くと、誰しも不安になるでしょう。しかし、不正がなければ必要以上に心配する必要はありません。大切なのは、日頃から正しい帳簿をつけ、証拠書類をしっかり保管しておくこと。さらに、疑問があればすぐに相談できる税理士の存在が、あなたの大きな安心材料になります。
京都で事業を営む方は、現金取引が多い業種も多いため、税務調査の対象になりやすい傾向があります。不安を抱えたままにせず、早めに準備し、信頼できる税理士と一緒に体制を整えておくことが大切です。
「うちは大丈夫?」と少しでも気になった方は、ぜひ石黒健太税理士事務所までお気軽にご相談ください。あなたの不安を安心に変えるサポートを、全力でいたします。