会社設立と個人事業主はどっちが得?
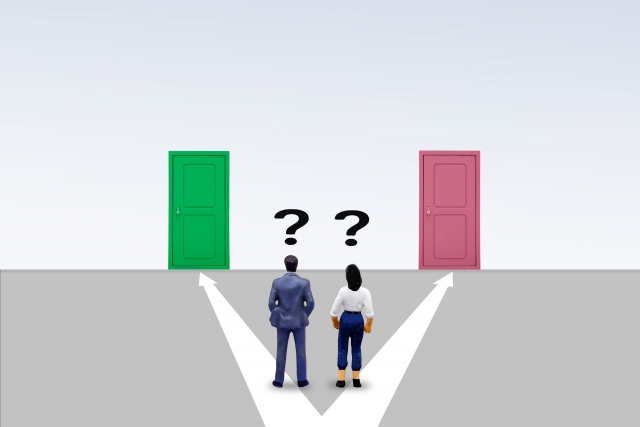
「会社を設立した方が節税になる」と耳にしたことがある人もいるでしょう。しかし、会社設立が本当に得かどうかは人によって異なります。課税所得や将来の事業展開、従業員の有無などによって、最適な事業形態は変わるからです。特に、法人と個人事業主では税制の仕組みが大きく異なるため、慎重な比較検討が必要です。
会社設立が得なケース:課税所得が900万円を超えている
課税所得が900万円を超えるケースでは、一般的に会社設立の方が得だと言われています。個人と法人で適用される税率に大きな差があるからです。
個人事業主は所得税がかかります。所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率も高くなります。所得が900万円を超えると税率が一気に33%になり、納税額が大きく跳ね上がります。税率が一律10%の住民税も加えると、900万円を超えた所得には、所得額の40%以上を納税する計算です。
所得税の税率
|
課税所得 |
税率 |
控除額 |
|
〜195万円未満 |
5% |
0円 |
|
195万円〜330万円未満 |
10% |
97,500円 |
|
330万円〜695万円未満 |
20% |
427,500円 |
|
695万円〜900万円未満 |
23% |
636,000円 |
|
900万円〜1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
|
1,800万円〜4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
|
4,000万円〜 |
45% |
4,796,000円 |
一方、法人には法人税がかかります。資本金1億円以下の普通法人の場合、年間所得800万円以下の場合は税率15%、年間所得800万円超の場合も一律23.2%です。法人住民税・法人事業税などを加味すると、所得の30%程度の納税額になるでしょう。
以上のことから、一定の所得以上になると、個人よりも税負担が軽くなる可能性があることがわかります。所得金額によっては会社を設立することで年100万円以上の節税につながるケースもあります。
参考:国税庁「所得税の税率」
参考:国税庁「法人税の税率」
個人事業主が得なケース:赤字が続いている
一方で、赤字が続いている段階では個人事業主のままでいる方が負担が少ないでしょう。法人は、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割を毎年納める義務があります。金額は資本金額や従業員数によって異なりますが、7万円程度が一般的です。
事業所得のみの個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税は発生しません。収入が安定しない時期や創業直後など赤字が予想される場合は、維持コストの低い個人事業主のままで様子を見る方がリスクが少ないと言えます。
法人化のシミュレーションが大切
会社設立と個人事業主のどちらが得かを知るためには、収入・経費・家族構成・将来の事業計画など、さまざまな条件を加味したシミュレーションが欠かせません。たとえば、年間所得が何円を超えたら法人の方が税金が安くなるか、役員報酬をいくらに設定すると個人と法人の所得のバランスがよくなるかなど、具体的な検討には専門的な知見が不可欠です。
法人化するべきかお悩みの個人事業主の方は、ぜひ石黒健太税理士事務所へご相談ください。会社設立の実績豊富な専門家がシミュレーションを行い、あなたに合ったアドバイスをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
以下の記事では、個人事業主と会社設立で手取りにどのくらいの差が生じるのかを実際にシミュレーションしています。
関連記事:個人事業主と法人化はどっちが得?シミュレーション結果を解説
法人と個人事業主の違いをわかりやすく解説
個人事業主と法人では、税金や手続きの仕組み、社会的な信用など、さまざまな面で大きな違いがあります。両者の違いを正しく理解した上で比較検討することが大切です。ここでは、法人と個人事業主の主な違いをわかりやすく解説します。
|
内容 |
法人 |
個人事業主 |
|
税金の種類 |
法人税、法人住民税、 |
所得税、住民税、個人事業税など |
|
赤字を繰り越せる |
最大10年間(青色申告) |
最大3年間(青色申告) |
|
経費の範囲 |
広い(社宅や役員報酬なども可) |
限定的 |
|
設立費用 |
約6万円〜25万円 |
ほぼ0円 |
|
事業承継の難易度 |
株式譲渡などで比較的スムーズ |
個人の資産や名義変更が必要 |
|
責任範囲 |
有限責任 |
無限責任 |
|
社会的な信用 |
高い(法人格に対する信頼) |
低い |
|
経営者が加入できる |
社会保険(健康保険、厚生年金) |
国民健康保険、国民年金(原則) |
|
申告書の作成 |
複雑。 |
比較的簡易。 |
|
青色申告特別控除額 |
なし |
最大65万円(要件あり) |
税金の種類
法人の場合に発生する主な税金は、法人税・法人住民税・法人事業税です。法人税の均等割は、たとえ利益が出ていなくても負担する必要があります。
一方、個人事業主の場合、所得に応じて所得税・住民税・事業税が課税されます。事業の利益が少ない間は税率が低く済みますが、所得が増えると税率も上昇する点に注意しましょう。前述のとおり、一定以上の利益が出る場合は法人化した方がトータルの税負担を抑えられるケースもあります。
赤字を繰り越せる期間
事業で赤字が出た場合、その損失を将来の黒字と相殺できる損失の繰越制度があります。法人では青色申告をしていれば、赤字を最大で10年間繰り越すことができます。一方、個人事業主では、青色申告をしている場合でも赤字を繰り越せる期間は3年が上限です。
創業初期に赤字を出し、その後徐々に黒字化していくタイプのビジネスでは、10年間の繰越が可能な法人の方が節税効果が高いと言えるでしょう。
経費の範囲
法人では、自宅の一部を社宅として使用し、会社名義で家賃を支払うケースや、役員報酬、生命保険料、退職金の積立金などを経費として計上できる場合があります。うまく活用することで、法人の課税所得を圧縮し、節税につなげることが可能です。
個人事業主は、経費とプライベートの支出との線引きが重要になります。たとえば、自宅兼事務所で事業を行っている場合でも、家賃のどの程度を事業用として経費にできるのかを厳密に計算する必要があります。経費の自由度は法人に比べて限定的です。
設立費用
法人を設立する場合、定款の作成・認証や登録免許税などの費用がかかります。株式会社では最低20万円、合同会社では最低6万円程度必要です。法人設立の手続きは煩雑なため、専門家に依頼するのが一般的です。
一方、個人事業主として開業する場合は、一般的には税務署に個人事業の開業届出書を提出するだけで完了します。費用もかからないため、初期コストと手続きの手軽さでは個人事業主の方が圧倒的に有利です。
事業承継の難易度
将来的に自分の事業を家族や第三者に引き継ぎたいと考えている場合、法人の方が事業承継のハードルは低くなります。法人の場合、事業主体と経営者は別人格のため、経営者が交代しても法人としての契約関係や資産・負債に影響がありません。
対して個人事業主は、事業に関わる財産、契約、許認可が個人名義なので、他人に引き継ぐ際は名義変更などの手続きが煩雑になります。事業主本人の信用が前提となっている場合、承継先が同様の信用を得るまでに時間がかかることもあります。
社会的な信用
取引先や金融機関からの社会的な信用にも差があります。法人は登記簿により設立が公的に証明されており、資本金や役員などの情報も明確です。そのため、金融機関からの融資、補助金申請、大手企業との契約などの場面で信頼されやすくなります。
個人事業主の場合、事業の実態が第三者から見えづらく、特に事業開始間もない場合は信用が得にくい場面もあります。特にBtoB取引が多い業種や、将来的に大規模な資金調達や大手企業との取引を視野に入れている場合には、法人化することで信頼性が高まり、ビジネス幅の広がりが期待できるでしょう。
経営者が加入できる保険制度
法人化することで、経営者自身も社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるため、老後の年金額や医療保障が手厚くなるというメリットがあります。
個人事業主は、原則として国民健康保険と国民年金に加入します。保険料の負担は法人に比べて安く済む場合もありますが、将来受け取る年金額や保障内容は限られています。
法人役員も個人事業主も、小規模企業共済や中小企業退職金共済、経営セーフティ共済など、退職金の準備や万が一の備えとして活用できる制度があります。社会保険料の負担と将来への備えのバランスも検討しておくと安心です。
法人化が向いている人

法人化には節税効果や社会的信用の向上といったメリットがありますが、すべての人にとって得とは限りません。個人事業主のままでいる方がメリットが大きい場合もあります。ここでは、どのような人が法人化に向いているのか、その特徴と理由を具体的に解説します。
課税所得が900万円を超えそうな人
先述のとおり、課税所得が900万円を超える場合、個人の所得税の税率よりも法人税の税率が低くなります。ある程度の利益が出るようになった段階で法人化すれば、トータルの税負担を抑えられる可能性が高いでしょう。
特に、売上や利益が安定していて今後も高水準が見込まれる場合には、法人化による節税効果が大きく、個人事業主のままでいるよりも手元に残るお金が増える傾向があります。
手元にお金が残らず、毎年の税金の負担が大きいと感じる方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:個人事業主が税金貧乏になる理由は?対策とお金の残し方を解説
事業を拡大したい人
取引先の拡大、新サービスの立ち上げなど、事業を次のステージへ進めることを考えているなら、法人化のメリットは大きいでしょう。法人化することで社会的信用が高まり、資金調達や取引先との契約の際に有利になる可能性があります。
クラウドサービスの法人契約や、助成金・補助金の申請においても、法人のほうが選択肢が広がります。事業の拡大を視野に入れている場合は、法人化が将来の成長のための土台作りになるでしょう。
優秀な人材を確保したい人
人材採用の面でも法人が有利と言えます。特に正社員採用の場合、安定性や福利厚生面で法人の方が候補者から選ばれやすく、求人媒体やハローワークでの掲載に有利に働きます。
社名を掲げた採用ブランディングも可能になり、「この会社で働きたい」と思ってもらえる土壌作りが可能です。優秀な人材を集めたい、長期的にチームで事業を育てていきたいという方には、法人化によって得られるメリットは大きいと言えるでしょう。
法人化が向いていない人
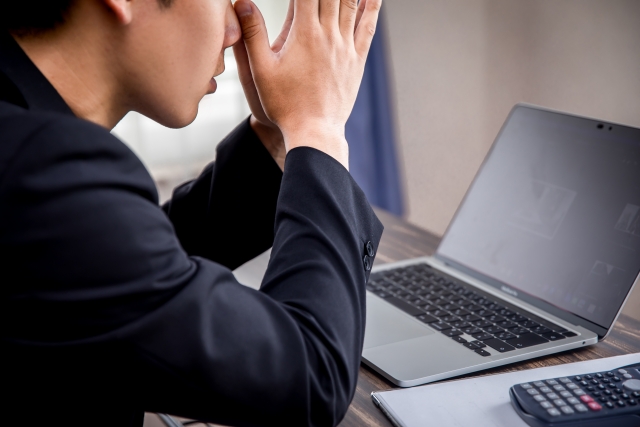
収入の安定性や事業の将来像によっては、あえて個人事業主のままでいる方が得策な場合もあります。ここでは、法人化に向いていないと考えられるケースとその理由について詳しく解説します。
収入が安定していない人
売上に波がある場合や、開業直後で収益が読めない状況では法人化に適したタイミングとはいえません。法人は、利益が出ていなくても法人住民税の均等割などのコストが毎年かかります。また、赤字の場合も決算書の作成や法人税などの申告が必要となり、税理士への依頼費用も発生します。
個人事業主であれば、利益が出なければ税金も発生せず、青色申告特別控除なども活用しやすいため、法人に比べてランニングコストは格段に低く抑えられます。まずはある程度安定して利益が出せる状態を確保してから法人化を検討する方が、経営の負担を軽減できるでしょう。
小規模な法人、いわゆる「マイクロ法人」を設立する際の注意点や、設立して後悔しないための対策は以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:マイクロ法人が後悔すると言われる理由は?売上なしマイクロ法人の注意点を解説
稼いだお金を自由に使いたい人
法人化すると、事業で稼いだお金は会社のお金として扱われ、経営者が自由に使うことはできません。経営者個人に還元するには、一般的には役員報酬として受け取る、または配当を出す必要があります。
一方、個人事業主は事業の利益はそのまま事業主のお金のため、自由に使える点が魅力です。急な家計の出費や生活費にこれまでどおり柔軟に対応したい場合は、個人事業の方がストレスが少ないでしょう。「お金の使い方を自分の裁量で決めたい」と考える人にとっては、法人化は煩雑で不自由に感じられる可能性があります。
事業承継を考えていない人
事業を子や親族に引き継ぐ予定がなく、自分一代で終わらせるつもりであれば、無理に法人化する必要はありません。なぜなら、法人には解散や清算といった手続きが必要であり、廃業時にも一定の費用や手間がかかるからです。
個人事業主であれば、税務署へ廃業届を出すだけで比較的スムーズに事業をやめることができます。また、設備や事業資産が少ない事業の場合は、あえて法人化してまで引き継ぐ必要がないケースも多いです。事業の規模や将来の展望を見据えたうえで、あえて法人化しないという選択も立派な経営判断です。
個人事業主があえて法人化しない理由や、法人化に失敗しないための方法については以下の記事をご覧ください。
関連記事:個人事業主はあえて法人化しない方がいい?節税にならないと言われる理由と法人化する年収の目安
ひとりで法人化手続きをして失敗するケース
制度や仕組みを十分に理解しないまま法人化の手続きを進めると、思わぬトラブルや負担に直面するリスクがあります。法人化後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、実際に起こりやすい失敗例を紹介しながら、注意すべきポイントを紹介します。
ケース1:初年度から消費税の課税事業者になった
課税事業者とは、消費税の納税義務がある人を指します。個人事業主のときは消費税を納めていなかったのに、法人化したとたんに納税義務が発生するケースがあります。これは、資本金の額やインボイス制度への登録が関係しています。
新しく法人を設立すると、1年目と2年目は原則として消費税の納税は免除されます。基準となる前々事業年度の課税売上高がないためです。しかし、法人設立時の資本金を1,000万円以上や、インボイス登録(適格請求書発行事業者登録)をする場合は、設立初年度でも課税事業者となります。
免税事業者のままでいようと考えていたのに消費税の納税義務が発生し、資金繰りが苦しくなってしまうケースも少なくありません。法人化の際には、課税事業者になるタイミングやインボイス登録など消費税に関する戦略的な判断が必要です。法人化に伴う消費税の免除期間については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:法人成りすると消費税の免除がなくなる?免除期間を長くするポイントと個人事業主への影響
ケース2:社会保険料の負担が増えて手取りが減った
法人化すると、事業主自身が会社役員として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があります。従業員がいない1人社長の場合も同様です。個人事業主の時の国民健康保険・国民年金と比べ、全体の社会保険料が割高になる可能性があります。
社会保険料は会社と本人で折半して支払う仕組みのため、自分の手取りが減るだけでなく、会社としての負担が大きくなる点が重要です。役員報酬を適切に設計しないと、思ったよりも自由に使えるお金が少なくなってしまうため、「こんなはずじゃなかった…」という失敗につながりやすいのです。
社会保険料は毎月必ず発生するため、法人化による固定費の増加としてきちんと把握しておきましょう。社会保険料の計算については、以下の記事も参照してください。
関連記事:1人社長の社会保険料はいくら?具体的な計算方法と役員報酬8万円の社会保険料の金額
ケース3:株式会社を選べばよかった
法人の形態は主に合同会社(LLC)と株式会社の2つがあり、設立費用や運営の自由度、対外的な信用力などが異なります。最近では設立費用が安く、柔軟な運営ができる合同会社も増えていますが、後になって「株式会社にしておけばよかった」と後悔するケースもあります。
たとえば、資金調達や取引拡大、採用などの面で、株式会社の方が有利になるかもしれません。特に、株式発行による資金調達は株式会社にしかできません。合同会社から株式会社へ後から変更することも可能ですが、余計な手間や費用がかかります。
自分の事業の将来像を明確に描いたうえで、適切な会社形態を選ぶことが大切です。どちらにするか迷う場合は、専門家にアドバイスを求めましょう。石黒健太税理士事務所では、会社設立に強い専門家があなたのお悩みを解決します。法人化のタイミングや事業形態の選択に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
合同会社と株式会社の違いや会社設立で失敗しないためのポイントをより詳しく知りたい場合は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:合同会社と株式会社の違いは?向いている会社形態と会社設立で失敗しないためのポイント
税理士に法人化を相談するメリット

法人化した方がよいのかわからない、手続き方法がわからないといったお悩みがある場合は、税理士に相談してアドバイスやサポートを受けるとよいでしょう。税理士に法人化を相談する具体的なメリットを3つ紹介します。
法人化のタイミングがわかる
法人化の重要なポイントはタイミングです。法人を設立してしまうと、法人化しなければよかったと思うことがあっても、簡単には元に戻せません。
事前に税理士に相談することで、現在の事業の規模や税金の状況、将来的な成長予測を基に最適な法人化のタイミングを提案してもらえます。たとえば、課税所得が増えてきた場合や、事業拡大を考えた場合など、税理士はそれぞれの状況に応じた適切な時期を見極めたアドバイスが可能です。
関連記事:個人事業主が法人化するデメリットは?法人化するタイミングと専門家に相談するメリット
法人化の手続きがスムーズになる
法人化のためには、設立登記や税務署への届出、社会保険の手続きなど、事務作業が山積みです。ひとりですべて行うと時間と手間がかかる上に、専門知識がないと正しく手続きができないリスクもあります。
税理士は税務関係の書類作成や提出を代行できます。また、会社設立に強い税理士であれば、提携する司法書士や社労士に必要な手続きを依頼できる場合があり、法人化を確実かつスムーズに進められるでしょう。
会社設立後の会計処理や税金の申告も任せられる
法人の会計処理や税務申告は複雑です。個人事業主の時は自分で申告していた人も、法人の会計や税務を自力で行うのは難しい場合が多いでしょう。
これらの業務を税理士に任せることで、経営者は本業に集中するというのも合理的な選択です。正確な申告や帳簿管理により、税務調査が入った場合も適切に対応できることが期待できます。
法人化のお悩みはお気軽にご相談を!
個人事業主と法人化のどちらを選ぶべきかは事業規模や状況によって異なります。法人化のタイミングや手続き、税務処理などは複雑なため、専門家である税理士のアドバイスを受けることが成功の鍵です。

法人化を検討しているけれど、どのように進めればよいか分からない方や、具体的な手続きについて不安がある方は、石黒健太税理士事務所へご相談ください。会社設立の実績豊富な税理士が法人化のタイミングや手続きについて、あなたに合わせたアドバイスをいたします。お電話での相談も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。








