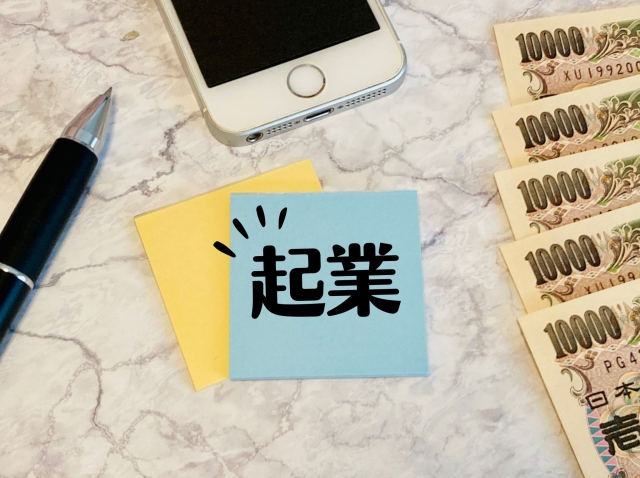50代が独立するには?起業するために必要なこと

50代は、若い世代に比べて社会人としての経験が豊富で、家庭がある人も多くなります。これまでの経験や人脈を大いに活用し、リスクを抑えながら着実に進めることが成功のカギです。ここでは、独立に向けた具体的なステップを見ていきましょう。
ステップ1:独立する目的と自分らしい働き方を明確にする
独立を成功させるために、まずは独立する目的や自分の望む働き方を明確にしましょう。単に「会社を辞めたい」「自由になりたい」という理由だけでは、長続きしません。自分が信念をもって立ち上げるビジネスであれば、困難に直面した時も乗り越えられるでしょう。
また、収入の安定性や働き方の自由度、社会貢献など、自分にとって何を優先するのかを明確にすることで、独立後のビジネスモデルを考える際の指針になります。
ステップ2:目的にあったビジネスモデルを考える
次に、目的を実現するためのビジネスモデルを構築します。50代での独立は、未経験の分野に挑戦するよりも、これまでの経験やスキルを活かせるビジネスがおすすめです。長年培った専門知識やスキルは、独立する際に大きなアドバンテージになります。
必ずしも、会社員時代と同じ職務内容で独立する必要はありません。たとえば、補助金の制度設計を担当していた公務員が補助金コンサルタントになる、マーケターが専門知識を活かして講師業を始めるなど、さまざまな選択肢があります。
また、独立後の収益モデルも重要なポイントです。単発の仕事ばかりではなく、定期契約のクライアントを獲得する、サブスクリプション型のサービスを提供するなど、持続可能なビジネスモデルを考えることが大切です。自分に合ったビジネスアイデアが思いつかないときは、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:起業したいけどアイデアがないときの対策は?起業アイデアが思いつかないときの対策と成功率を高めるポイント
ステップ3:家族の理解を得る
家庭がある人にとって重要なのが、家族の理解を得ることです。あなたの収入が家計を支えているならば、安定した収入が得られる会社員を辞めて独立することは、家族にとっても一大事です。住宅ローンの返済や子どもの教育費など、家計への影響を考えると、配偶者や家族の同意なしに独立するのは難しいでしょう。
家族の理解を得るためには、独立後の収入の見通しやリスクについても正直に話すことが重要です。「最初の1年間は収入が不安定になるかもしれない」「生活費のためにこの程度の貯蓄を確保している」など、具体的な計画を伝えることで、家族も安心しやすくなります。
ステップ4:具体的な事業計画書を作成する
経営者として事業を進めていくためには、事業計画が不可欠です。商品・サービスの概要、ターゲット顧客・市場分析、競合分析、マーケティング戦略、資金計画など、ビジネスの基本的な要素を整理しましょう。行き当たりばったりではなく、計画に沿って事業を進めることで成功する可能性が高まります。
金融機関への融資申請や、助成金・補助金申請の際に、事業計画書の提出を求められます。事業計画書は自分のビジネスの概要を第三者に伝える重要なツールでもあるため、説得力があり実現性の高い内容であることが大切です。
事業計画書の作成には、経営や会計の専門知識が必要です。自分で作成するのが難しい場合は税理士などの専門家に依頼できます。以下の記事では、事業計画書を税理士に依頼する場合の費用相場や税理士に依頼するメリットを解説しています。
関連記事:事業計画書を税理士に依頼する費用の目安は?10〜15万円が相場
ステップ5:独立に必要な資金を準備する
事業を始めるための資金は業種によって大きく異なります。店舗を構える場合は、店舗の賃貸借契約やリフォーム、設備投資などで数百万円以上かかることもあります。一方、オンラインを活用して自宅を拠点として仕事をする場合は、大きな初期費用はかからないでしょう。
独立したばかりの時期は売上が少ないことを想定して、業種にかかわらず、事業が軌道に乗るまでの運転資金を3~6ヵ月分用意しておくと安心です。
また、法人を設立する場合は設立費用がかかります。定款認証、設立登記の際の登録免許税、資本金などの必ず発生する費用は、株式会社の場合は最低20万円、合同会社の場合は最低6万円が目安です。運転資金や設立費用など、独立に必要な資金を把握し準備しましょう。
起業資金については以下の記事も参考にしてください。
関連記事:起業資金の最低額の目安は?起業資金不足の対策と50万円あれば始められるビジネス7選
独立が会社への裏切りと思われないためのポイント
独立は、あなた個人のキャリアにとっては前向きな選択です。しかし、やり方を間違うと会社に「裏切り」と捉えられてしまうリスクもあります。勤務先の会社を円満に退職し、スムーズに独立するために注意すべきポイントを押さえておきましょう。
顧客を連れていかない
現在の勤務先で担当している顧客を連れて行くのはやめましょう。あなたが会社員として出会った顧客は、あなた個人ではなく会社の顧客です。顧客情報は会社の資産であり、退職者が無断で持ち出すことは法的にも問題になる可能性があります。特に、競業避止義務や守秘義務に違反した場合、訴訟に発展するリスクも考えられます。
独立して顧客を獲得する際は、あくまでもゼロから信頼関係を築く姿勢が大切です。あなたが以前勤めていた会社の顧客が自発的にあなたのサービスを求めてくれる場合は問題ありませんが、こちらから積極的に勧誘するのは避けたほうがよいでしょう。
同僚を連れていかない
新しいビジネスに協力してくれる人がいるのは心強いですが、同僚を連れていくのはリスクが高い行為です。短期間で複数名の戦力を失うことは、勤務先の会社にとって大きな痛手です。「従業員を引き抜かれた」と大きな反発を招くおそれがあります。
また、独立した事業が軌道に乗るまでは収入が不安定になりやすく、待遇面でもこれまでと同じようにはいかないかもしれません。人件費を払わなければならないあなたも、収入が安定しない相手も、「こんなはずじゃなかった」とお互い後悔する事態になりかねません。
まずは自分ひとりで事業を立ち上げ、収益が安定してからフェアな形で人材を採用する方が、後々のトラブルを避けられるでしょう。
丁寧な引き継ぎと円満退社を心掛ける
勤務先に対して感謝の気持ちを伝えるとともに、丁寧な引継ぎを行うことが大切です。円満に退職することで、独立後に元いた会社と何らかのつながりが生まれた際も、お互いに気持ちよく仕事ができます。
まず、退職の意思を伝えるタイミングを慎重に考えましょう。50代の場合は管理職に就いていたり、重要な顧客を担当していたり、会社の中で影響力が大きい場合も少なくありません。就業規則で定められている期間にかかわらず、後任の選任や引き継ぎの時間を考慮して、できるだけ早めに伝えるとよいでしょう。
引き継ぎの際も、業務マニュアルを作成する、引き継ぎミーティングを行うなど、後任者にも顧客にも安心してもらえるように努めることが大切です。
50代から独立できる仕事3選

50代は若い世代とは異なり、豊富な業界経験や専門知識、人脈があることが強みです。これまでの経験や人脈は、独立後のビジネスで活かすことができます。また、自分の強みを活かせる分野を選ぶと、より安定的な収入を得やすいでしょう。以下では、50代から独立できる仕事を3つ紹介します。
コンサルタント
コンサルタントは、特定の分野の専門知識や経験を活かし、企業や個人の課題解決を支援する仕事です。経営戦略、人事、マーケティング、ITなど、さまざまな分野で活躍するコンサルタントがいます。
特に50代は、長年にわたる実務経験を通じて、専門知識や業界特有の深い知見、幅広い人脈を築いている方が少なくありません。これらの積み重ねこそが、クライアントにとっては何にも代えがたい貴重な知見や、的確なアドバイスを生み出す源となるのです。
最新の知識やトレンドに精通した20代や30代の若手コンサルタントとは異なる、深みのあるコンサルティングを行うことで、クライアントに安心感と信頼感を与えられるでしょう。
人材紹介
人材紹介業は、企業の抱える人材ニーズと、求職者が持つスキルや経験、キャリアへの志向性の架け橋となる仕事です。企業に対しては、組織の成長戦略に合った人材を、求職者に対しては、能力を活かせるキャリアプランに沿った仕事を紹介することで、双方の持続的な成長を支援します。
人材紹介会社のコンサルタントが独立するケースでは、業界知識や採用・求職のノウハウ、企業や候補者とのネットワークを既にもっているため、事業の立ち上げがしやすいでしょう。IT・医療・金融など特定の専門領域の知見が豊富な人が、特定の業界専門の人材紹介業を始めるケースもあります。
長年の社会人経験で培われた、人の個性や能力を見抜く力、コミュニケーション能力を活かせば、企業と求職者の双方から信頼される人材紹介エージェントとして活躍できるでしょう。
コーチング
コーチングは、クライアントの目標達成や能力開発を、対話を通じてサポートする仕事です。ティーチングのように知識や方法を教えるのではなく、クライアント自身が持つ潜在能力を引き出し、自律的な成長を促します。
経営層やマネージャーへのコーチングやキャリアコーチングなど、ビジネス領域だけでなく、ウェルネス(健康増進)、教育、スポーツなど活躍の場は多岐にわたります。50代の方は仕事やプライベートでさまざまな経験を積んでいるため、クライアントの悩みや課題を理解して寄り添うことができ、信頼関係を築きやすいでしょう。
コーチングは対面で行う場合もあれば、オンラインで行う場合もあります。オンラインの場合は、遠方のクライアントにもサービスを提供できるのがメリットです。コーチングの資格を取得していると信頼性が高まり、クライアントを獲得しやすくなるため、独立後もスキルを磨くことが重要です。
独立に向いている50代の特徴
独立に向いている50代には、以下のような特徴があります。
・業界経験と専門知識が豊富
・広い人脈をもっている
・安定した生活基盤と経済力がある
・自己管理能力が高い
50代は長年の経験を活かして独立できることが強みです。特に、コンサルタントや教育・指導に関わる仕事では、経験に裏打ちされた豊富な知識がクライアントからの信頼獲得に繋がるでしょう。また、これまで築いてきた取引先や顧客、同僚との人脈が、独立後にも活かすことができます。
独立のためには知識や経験だけでなく、資金力も重要です。50代になると、子どもが大きくなったり、ある程度の貯蓄ができたりして、独立後に収入が不安定になるリスクを取る余裕ができる人も出てきます。経済的な不安が少ない人や、日々のタスクを効率的にこなすのが得意な人も、独立に向いていると言えます。
独立に向いていない50代の特徴
一方で、50代での独立が向いていないと考えられる人の特徴もいくつかあります。
・リスクをとることに不安を感じる
・経験を活かせるビジネスが思いつかない
・人脈が乏しく、人付き合いが苦手
・自己管理が苦手で自由な働き方に適応できない
上記のような特徴に当てはまる人は、会社員のほうがメリットが大きい可能性があります。
たとえば、50代まで会社員を続けたのだから、ここで独立してリスクを冒すことはない、という考え方もあります。あるいは、あまり人付き合いが得意ではなく、顧客獲得や経営者としての人脈作りに気が進まないと感じる人もいるでしょう。会社に管理されていた方が働きやすいという人がいるのも事実です。
ただし、当てはまる特徴があったからといって、独立できないわけではありません。十分に自己分析を行い、対策を講じることで、成功できる可能性は十分にあります。不安や疑問があって独立に踏み切れない場合は、専門家に相談するのもひとつの方法です。
石黒健太税理士事務所では、50代で独立したい方の起業相談を受け付けています。ひとりで悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。
50代からの独立開業に失敗しないためのポイント

50代で独立する際には、いくつかのポイントがあります。以下のようなポイントを抑えることで、成功する可能性が高まります。
・独立前から準備を始める
・周りの意見や助言を受け入れる
・健康が維持できる働き方にする
・お金と税金の知識を身につける
・謙虚な姿勢で常に学び続ける
・一人で抱え込まない
・気軽に相談できる協力者や専門家を見つける
ここでは、50代からの独立開業に失敗しないためのポイントについて解説します。
独立前から準備を始める
思い立ったが吉日、独立を決めたら準備を始めましょう。会社員を続けながらでもできることは多くあります。まずは業界の動向や市場調査を行い、自分のビジネスモデルを確立しましょう。競合と差別化するための戦略も重要です。事業計画は独立する前に綿密に練っておくことをおすすめします。
資格があることで顧客が獲得しやすくなる業種であれば、資格取得のための勉強をすることも独立準備のひとつです。以下の記事では起業をスムーズに進めるためのステップを紹介しています。何から始めてよいかわからない場合は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:起業するにはまず何から始める?スムーズに進めるための5つのステップと成功する人の特徴
周りの意見や助言を受け入れる
50代で独立を目指す場合、自分の経験や知識が豊富である分、視野が狭くなりがちです。しかし、他の視点を取り入れることで、自分では見落としていたチャンスやリスクに気づけることもあります。ひとりで悩まずに、周囲の人に気軽に相談してみましょう。
逆に、周囲の意見や助言を受け入れないと、市場のニーズに合わないビジネスモデルで失敗したり、ビジネスチャンスを逃したりする可能性があります。特に、税務や法務などの分野での失敗はペナルティを伴う場合もあり、リスクが高いものです。自分の専門知識が乏しい分野は、信頼できる専門家のアドバイスを受けて柔軟に対応することが、独立を成功に導く鍵です。
健康が維持できる働き方にする
独立すると自分のペースで仕事ができるようになります。会社員のころと比べて楽になるかと思いきや、逆に働きすぎてしまうことも珍しくありません。働きすぎて体調を崩してしまうと、仕事の効率も落ち、ビジネスの運営にも影響が出てしまいます。
独立を成功させるためには、健康を維持するための生活習慣が大切です。適度な運動、栄養バランスの取れた食事、十分な休息などを心がけ、長期的に安定した仕事のペースを作ることが必要です。ビジネスの成功は、経営者である自分自身の体調管理にかかっていると言っても過言ではありません。
お金と税金の知識を身につける
独立後のお金の管理は、会社から給与をもらう場合とは大きく異なります。売上は毎月同じとは限りません。売上や経費を確認して、経営状態を把握するのも経営者の重要な仕事です。また、帳簿の管理や申告を正しく行うことも求められます。
特に、キャッシュフローや税金などの基礎知識を身につけましょう。健全な経営のためには、税理士などの専門家に相談しながら、適切な処理を行うことが大切です。「売上はあるはずなのに資金繰りが厳しい…」と悩まないためにも、独立前にある程度の知識を得ておくと安心です。以下の記事では、お金がない会社の特徴や経営を安定化するための対策を解説しています。
関連記事:お金がない会社の特徴とお金が残らない本当の理由は?経営を安定化するための改善策
謙虚な姿勢で常に学び続ける
これまでの経験や知識をもとに独立する場合でも、独立後も学び続ける姿勢が大切です。50代になると学びを後回しにしがちですが、市場の変化は速く、新しい情報や技術を取り入れないと取り残されてしまいます。
専門分野の知識をアップデートすることはもちろん、経営者として必要なスキルを磨くのも経営にプラスになるでしょう。
一人で抱え込まない
独立して間もない経営者は仕事が多いものです。売上の管理や請求書作成、記帳など、会社員時代は事務や経理の部署に任せていたような事務も行う必要があります。しかし、せっかく独立したのに事務に追われて本来のビジネスに手が回らなくなってしまったら本末転倒です。
必要に応じて外部の協力者を見つけることが大切です。たとえば、業務の一部をアウトソーシングしたり、専門家にアドバイスを求めたりして自身の負担を軽減し、できる限りビジネスに専念できる環境を作ることが大切です。
気軽に相談できる協力者や専門家を見つける
独立して仕事を始めると、自分の知識だけでは解決できない問題が出てくることがあります。その際に、気軽に相談できる協力者や専門家を見つけておきましょう。
税理士、弁護士、マーケティングの専門家など、自分が信頼できる人脈を作っておけば、困ったときにすぐにサポートを得られます。また、外部のアドバイスを受けることで、新たな視点を得てビジネスを改善することも可能です。
以下の記事で税理士の選び方のポイントを解説しています。初めての税理士選びで選ぶ基準がわからない方はぜひ参考にしてください。
関連記事:企業の成長が加速する税理士の選び方は?依頼する目的から選ぶ税理士の選び方とポイント
独立のお悩みはお気軽にご相談を!
50代は、長年の社会人経験で培った専門知識や経験を活かしやすい年代です。まずは会社員を続けながら、自分のビジネスモデルを具体化してみましょう。あなたのビジネスプランをより万全なものにするために、専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。また、独立してからも経営について気軽に相談できる相手を見つけておくと安心です。
独立する際には、会社に「裏切った」という印象を与えないよう、感謝の気持ちを伝え、丁寧に引継ぎを行うことが大切です。顧客や同僚を連れて行く行為はトラブルの原因になるリスクがあるため控えましょう。円満に退職すれば、後々、会社員時代の縁がビジネスにとってプラスになることもあるでしょう。

石黒健太税理士事務所では、起業の実績が豊富な税理士があなたの独立のお悩みを丁寧に伺い、解決いたします。お電話での相談も可能です。小さなことでもお気軽にお問い合わせください。