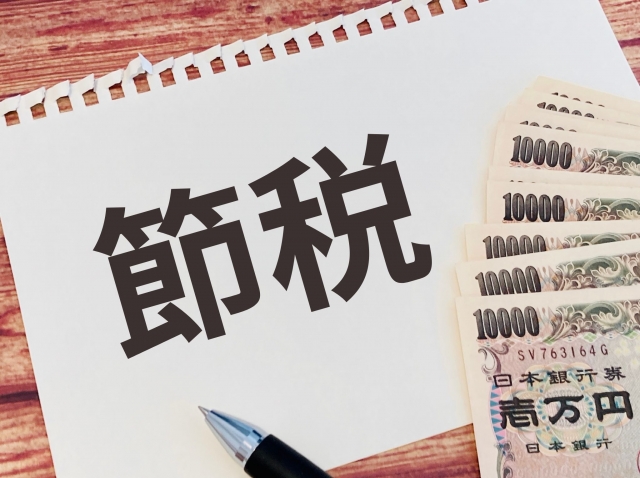法人成りが節税になると言われる理由

法人成りをすると、支払う税金の種類や、適用できる控除などが変わります。また、法人は個人事業主よりも税制上の経費が多いため、今よりも税金の負担が抑えられる可能性があります。法人成りが節税になる理由は、以下の5つです。
・所得税と法人税の最高税率が異なるから
・配偶者控除・扶養控除が適用できるから
・経費の範囲が広がるから
・消費税が最大2年間免除されるから
・赤字を最大10年間繰り越せるから
内容をくわしく解説します。
理由1:所得税と法人税の最高税率が異なるから
個人事業主の場合、事業活動で得た所得には「所得税」が課せられます。しかし、法人成りすると、所得税ではなく「法人税」が課せられることになります。所得税と法人税には、様々な違いがありますが、特筆すべきなのは税率でしょう。
所得税の場合、適用される最高税率は45%です。一方、普通法人の法人税の最高税率は23.2%です。高額所得者の場合は、法人税率を適用することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。
【最高税率の比較】
|
所得税 |
最高45% |
|
法人税(資本金1億円以下の普通法人の場合) |
最高23.2% |
ただし、所得額によっては、所得税の税率を適用した方が、納める税金が安い可能性があります。これは、所得額が一定額を超えるまでは、「所得税の税率<法人税の税率」となるためです。くわしくは後ほど解説します。
参考:国税庁「所得税の税率」
参考:国税庁「法人税の税率」
理由2:配偶者控除・扶養控除が適用できるから
青色専従者として、給与を受け取っている親族は、控除対象配偶者や扶養親族になることができません。これは、青色申告のルールのため、親族に支払う給与の大小は関係ありません。
しかし、法人成りした場合、会社の事業に従事する親族には、一般的には役員報酬を支払うことになります。そして、報酬を受け取る親族は、年間収入103万円以内などの要件を満たせば、控除対象配偶者や扶養親族になることが可能です。
配偶者控除・扶養控除が適用できれば、事業主本人の所得税は節税できます。親族に支払う給与が少額の場合は、法人成りを行うことで、税金の負担が抑えられるでしょう。
参考:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
理由3:経費の範囲が広がるから
個人事業主の場合、プライベートと事業の両方で使う物は、案分計算によって経費計上できる金額を決定します。しかし、法人成り後は、事業で使う物は法人名義にすることで、案分計算が不要になります。自宅を社宅にする場合などは、減価償却が利用できるため、長期にわたり、全額を経費にすることが可能です。
また、法人では、事業主本人の給与や賞与、退職金などついても経費にできます。経費が増えれば、所得が圧縮できるため、節税に繋がるでしょう。
ただし、交際費の取り扱いには注意が必要です。個人事業主の場合、交際費の計上には上限がありませんでしたが、法人の場合は上限が設けられています。接待などが多い事業者は、法人成りによって、経費にできる金額が減る可能性があることを知っておきましょう。
理由4:消費税が最大2年間免除されるから
一般的に、課税売上高が1,000万円を超える個人事業主が法人成りすると、消費税が最大2年間免除される可能性があります。これは、同じ事業者であったとしても、法律上、法人と個人が別人と見なされるからです。個人事業主で得た収入は、個人の実績のため、法人成り後の消費税には影響を与えないのです。
ただし、すでに消費税を納めている課税事業者の場合は、法人成りの手続きの中で消費税が発生する恐れがあるため注意が必要です。以下の記事では、法人成りしたときの消費税の取り扱いについて解説しています。消費税の支払いで損をしたくない人は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:法人成りすると消費税の免除がなくなる?免除期間を長くするポイントと個人事業主への影響
理由5:赤字を最大10年間繰り越せるから
個人事業主が赤字を繰り越せる期間は、最大3年です。一方、法人の場合、赤字の繰り越しは最大10年間まで可能になります。法人は、繰越期間が長期のため、黒字のときに相殺しやすく、上手く活用できれば大きな節税に繋がるでしょう。
ただし、赤字の時期は、税金の負担が増える恐れがあります。詳細は後述しますが、法人の場合、赤字でも負担が必要な税金があるのです。また、将来の黒字と相殺するために、わざと赤字経営を行うことは大変危険です。赤字経営によって、倒産のリスクが高まります。
現時点で赤字の場合は、法人成りの前に事業を安定化させることが大切です。個人事業主の赤字は、法人に引き継ぐことはできませんし、会社設立には費用が発生するため、資金も必要です。
事業の安定化でお困りの方はぜひ当事務所へご相談ください。利益を最大化するためのアドバイスやサポートが可能です。もちろん、法人成りのお悩みも受け付けております。
ご相談はお電話でもできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
法人成りが節税にならないとどうなる?
法人成りは、税金面で必ずしも得できるわけではありません。冒頭でもお伝えした通り、法人成りによって得られる節税効果には個人差があります。予想していたよりも節税できず、費用対効果が低いと感じる人も珍しくありません。
ここからは、法人成りで節税できなかったときのデメリットなどを中心に解説します。「法人成りはやめておけばよかった」と、後悔しないためにも、紹介する内容はしっかり理解しておきましょう。
赤字でも税金の負担が増える
法人成りすると、法人住民税を支払わなければなりません。法人住民税とは、事務所等を有する市区町村と都道府県に納める税金のことで、「法人税割」と「均等割」の2つの要素で構成されています。
法人住民税の均等割は、資本金等の金額と従業員の人数に応じて負担額が決まる仕組みです。そのため、赤字・黒字に関係なく、納税義務が発生します。納税額については、少なくとも約7万円必要で、赤字の場合、納税資金を確保できないことも珍しくありません。
赤字でも納税が必要な点は、法人のデメリットと言えるでしょう。
個人成りに負担がかかる
個人事業主の方が納める税金が安い場合、法人から個人事業主に切り替える方法である「個人成り」を検討することになるでしょう。しかし、個人成りは簡単ではありません。様々な手続きが必要で、費用もかかります。
【個人成りの手続き】
・会社の清算と解散
・事業の資産を個人に売却
・法人名義の口座や資産について名義変更
・各行政機関に開業と廃業関係の届出を提出
会社の清算・解散手続きでは、法務局での登記と官報への掲載が必要です。法務局で行う、解散登記と清算人の選任登記は、計4万円ほどの費用がかかります。官報への掲載料も4万円程度かかるのが一般的です。つまり、解散の手続きでは、合計8万円以上の費用が発生するのです。
また、事業に関する届出だけでなく、事業主本人に関する届出も提出しなければなりません。個人事業主に戻る場合、社会保険から国民健康保険へ、厚生年金から国民年金に切り替える手続きが必要です。これらの手続きは事業と並行して行わなければならないため、かなりの負担となります。
個人の生活費が不足するかもしれない
法人の運営は、個人事業主のときよりもコストがかかります。法人におけるコストの代表例が、社会保険料の負担です。個人事業主の場合は、原則として従業員が常時5人以上いなければ、社会保険に加入する必要がありませんでした。
しかし、法人の場合は、従業員の人数に関係なく、社会保険の加入が必須になります。社会保険は労使折半の制度です。従業員が増えるほど、会社が負担する社会保険料額も増加します。
会社のコスト負担が増えると、事業主本人に回せるお金が減る可能性があるため注意が必要です。また、事業主については、役員報酬を設定しますが、通常は決めた金額は決算期を迎えるまで変更できません。そのため、役員報酬を少額に設定した場合、結果として事業主本人の生活費が不足する恐れがあるのです。
詳細は後述しますが、役員報酬の金額は、個人の所得税と社会保険料に影響を与えます。報酬が少額だと生活費に困る可能性がありますが、高額だと税や保険料の負担が増え、手取りが減るかもしれません。役員報酬は、会社の利益と個人の負担を考慮した、適切な金額設定が大切です。
当事務所では、役員報酬に関するご相談も受け付けております。税務上のリスクや、会社の利益を踏まえた上で適切な金額をご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお電話でも可能です。
関連記事:法人化に後悔する5つのケースとは?法人化が後悔する人の特徴と対策
法人成りが節税になるケース

一般的に、以下のケースに当てはまる人は、法人成りで節税できると言えます。
・課税所得が900万円を超える
・課税売上高が1,000万円を超える
・専従者に少額の給与を支払っている
個人事業主が納める所得税と、法人が納める法人税では、課税方式が異なります。所得税では、累進課税制度が採用されているため、所得額に応じて段階的に税率が高くなります。一方、法人税では、比例課税方式が採用されており、所得額に関係なく一定税率で課税されます。
そして法人成りで節税できるのが、課税所得が900万円を超えるタイミングです。課税所得が900万円を超えると、法人税の税率が所得税の税率を下回るため、法人成りする方が納める税金が安くなるでしょう。
【課税所得900万円超の適用税率】
|
所得税 |
33%~(45%が上限) |
|
法人税(資本金1億円以下の普通法人) |
23.2%(上限) |
また、前述した通り、課税売上高が1,000万円を超えるタイミングでの法人成りは、消費税が最大2年間免除される可能性があります。
その他、専従者に少額の給与を支払っているケースも、法人成りによって節税できるでしょう。法人成りをすれば、事業に従事する家族に役員報酬を支給でき、その金額を損金算入できます。損金算入できれば、法人の所得が圧縮できるため、法人税などの節税が可能です。
また、家族への役員報酬を少額に設定することで、配偶者控除や扶養控除が適用され、事業者本人の課税所得を抑えることもできます。そうすれば、法人の税金と個人の税金、ダブルで節税が可能なのです。
法人成りが節税にならないケース
税金面で得しやすい法人成りですが、節税にならないケースもあります。法人成りが節税にならないケースは、以下の通りです。
・事業での利益が少ない
・事業が不安定な状態が続いている
・取引先からインボイスの発行を求められている
・1,000万円以上の資本金を用意して会社設立を行う
前述した通り、所得税率が法人税率を上回るのは課税所得が900万円を超えるタイミングです。そのため、事業が不安定だったり、利益が少なかったりする人は、個人事業主でいる方が納める税金が安い可能性があります。
また、一般的に、課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業者となります。しかし、適格請求書発行事業者となる場合や、資本金1,000万円以上の法人を設立する場合は、課税売上高に関係なく、原則的に消費税の課税事象者となるのです。
法人成り後に、取引先からインボイスの発行を求められるケースや、営業許可の申請で高額な資本金の用意が必要になるケースもあるでしょう。このような場合は、消費税が免除されず、課税となってしまうため、消費税については節税にならないと言えます。
法人成りに失敗しないためのポイント

法人成りが失敗と感じる主な理由には、「コストが経営を圧迫している」「お金が自由につかえない」などが挙げられます。前述したした通り、法人から個人事業主に戻るには、費用も手間もかかります。法人成りに失敗しないためにも、以下のポイントは押さえておきましょう。
・事前にしっかりとシミュレーションをする
・法人成りのタイミングを見極める
・法人成り後のランニングコストを把握する
・役員報酬の仕組みを理解する
・専門家に相談する
内容をくわしく解説します。
事前にしっかりとシミュレーションをする
個人事業主と法人では、支払う税金の種類や、適用される税率が異なります。そのため、法人成りした後に「思ったより節税できなかった」と後悔することも珍しくありません。法人成りの節税効果には個人差があるため、事前にしっかりとシミュレーションし、比較・検討することが大切です。
また、シミュレーションは、納税額だけでなく手取りについても行いましょう。個人事業主と法人の経営者では、負担する社会保険料の金額が違うため、手取り額も変わります。税金の損得だけで判断せず、手元にどれくらいのお金が残りそうかも考えてみましょう。
以下の記事では、個人事業主と法人のケース別に手取り額を算出しています。シミュレーションの参考になるので、ぜひご覧ください。
関連記事:個人事業主と法人化はどっちが得?シミュレーション結果を解説
法人成りのタイミングを見極める
多くの個人事業主は、税金の損得で法人成りを検討します。しかし、税金面だけで法人成りを考えるのは早計と言えます。法人成りの適切なタイミングは、将来の展望などによっても変わるため、一概には言えません。
例えば、事業を成長させたい場合、法人として信用力を高めた方が得できるかもしれません。信用力が高まれば、大規模な取引や融資が可能になるため、個人事業主でいるよりも、事業が急成長できる可能性があります。
節税よりも事業の継続・成長の方が重要です。法人成りには、税金面以外にも様々なメリットがあるため、メリットを最大限活用できるタイミングを見極めましょう。以下の記事では、法人化のメリット・デメリットをくわしく解説しています。
関連記事:個人事業主が法人化するデメリットは?法人化するタイミングと専門家に相談するメリット
法人成り後のランニングコストを把握する
法人は、個人事業主よりもランニングコストが高くなる傾向があります。法人成り後のランニングコストには、以下が挙げられます。
・社会保険料
・税理士顧問料
・役員の就任や退任にかかる登記費用
・決算公告費用
・株主総会の開催費用
これらの費用の中で、毎月発生するのが社会保険料と税理士顧問料です。社会保険料は労使折半のため、従業員に支払う給与が高額な場合や、従業員の人数が多い場合などはかなりの負担となります。税理士顧問料の相場は、月3万円程度ですが、契約内容などによって異なります。
また、株式会社の場合は決算公告費用や株主総会の開催費用は、毎年発生するコストです。コストの負担によって経営を圧迫するケースは珍しくないため、法人成り後は早急な事業の安定化が求められます。
役員報酬の仕組みを理解する
役員報酬とは、取締役や監査役などの役員に支給する報酬のことです。報酬額は、株主総会や定款などで決定しますが、決定後は原則として、次の決算期まで変更できません。役員報酬が高額な場合、個人の税金や社会保険料の負担が増え、結果として手取りが減る恐れがあります。
また、前述した通り、役員報酬については、損金算入が可能なため、節税に繋がります。ただし、損金として認められるには、次のいずれかの支払い方法を選択しなければなりません。
・定期同額給与…毎月同額の報酬を支給
・事前確定届出給与…指定日に報酬をまとめて支給(税務署への届出が必須)
・業績連動給与…会社の利益に連動して報酬を支給(適用には条件あり)
このように、役員報酬には様々なルールがあります。ルールを知らなかった場合、損金算入ができず、節税できない恐れがあるため注意が必要です。以下の記事では役員報酬についてくわしく解説しています。
関連記事:1人社長が儲かると言われる理由は?役員報酬を決めるときの注意点と1人社長が抱える悩み・リスク
専門家に相談する
法人成りでは、法務局への登記申請や、各行政機関への届出など、様々な手続きが必要です。知識がない人にとってはハードルが高く、手続きが頓挫することも珍しくありません。
また、役員報酬や資本金などのお金関連のこともしっかり準備する必要があります。役員報酬と資本金は、税金の計算にも影響を与えます。シミュレーションをしていないなどの準備不足の場合、納める税金が高くなるなどの失敗にも繋がるでしょう。
税金やお金に関するお悩みは、税理士への相談がおすすめです。税理士への相談は、「正確なシミュレーション結果がわかる」「高い節税効果が得られる」などのメリットがあります。
法人成りのお悩みはぜひ当事務所へお任せください。創業などのスタートアップに携わった優秀なスタッフがサポートいたします。ご相談はお電話でも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
法人成りを専門家に相談するメリット

法人成りについて相談できる専門家には、「司法書士」「行政書士」「税理士」がいます。それぞれの違いについては以下の通りです。
・司法書士…会社設立の専門家で、法務局への登記申請などを相談できる
・行政書士…行政手続きの専門家で、許認可の申請などを相談できる
・税理士…税金の専門家で、税務関連の手続きや節税対策、経営に関する相談ができる
会社設立は、予想以上に手間と負担がかかります。事業との両立が難しくなり、法人成りの期間に収入が減る事業者がいることも事実です。これらの専門家に相談することで、事業に専念できる以外にも、様々なメリットが得られます。
ここからは、専門家に相談することで得られるメリットをくわしく解説します。
失敗のリスクを減らせる
法人成りの際は、資本金の準備や定款の作成、設立登記など様々な手続きが必要です。これらの手続きに漏れがあると、当初の時期から設立が遅れてしまうなどの失敗を招く恐れがあります。わからないことがあれば一人で悩まず、専門家に相談しましょう。
また、法人成りにおける失敗は、設立手続きに関するものだけではありません。ランニングコストが節税額を上回ってしまうなど、金銭面に関する失敗もあります。金銭的な問題は、今後の経営に悪影響を及ぼす恐れがあるため、税理士に相談しながら事前に対策を講じることが大切です。
法人と個人どちらが有利かわかる
節税以外にも比較すべきポイントがあります。そのひとつに、決算の難易度などが挙げられます。法人は、決算で作成する書類も多い上、決算内容について株主総会での承認が必要です。一連の作業を面倒に感じ、「個人事業主のままでいれば良かった」と考える事業者もいるでしょう。
大切なのは事業の継続です。法人と個人どちらが最適な選択かは、将来の展望・事業の現状などによっても異なります。人によっては、個人でいる方が有利になったり、得になったりするケースもあるため、詳細は税理士などの専門家に相談しましょう。
関連記事:個人事業主はあえて法人化しない方がいい?節税にならないと言われる理由と法人化する年収の目安
法人成り後もサポートが受けられる
法人成りを行うと、社会保険料の納付や、税務署への提出書類が増えるなど、新たな事務手間が発生します。これらの事務作業には、会計や税務、労務に関する知識が必要です。法令やルールに違反するとペナルティを科せられる恐れがあるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
また、法人成り後は、融資や税金対策などの準備も必要です。これらの準備が不足する場合、資金の枯渇が生じ、経営難に陥る可能性が高まります。税理士に相談することで、事業開始も資金面に関するサポートが得られるため、早期の段階で事業の安定化が図れるでしょう。
法人成りのお悩みはお気軽にご相談を!
法人成りは、個人事業主よりも税制上の優遇が多いため、節税しやすいのがメリットです。しかし、運営コストや事務手続きなど、個人事業主とは異なるポイントが多くあります。法人成りの選択を後悔しないためにも、手続きの前に専門家に相談することをおすすめします。

法人成りのお悩みは当事務所にお任せください。当事務所は、200件以上の創業支援実績があり、経営・税務に関するサポートが可能です。お電話でもご相談ができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。