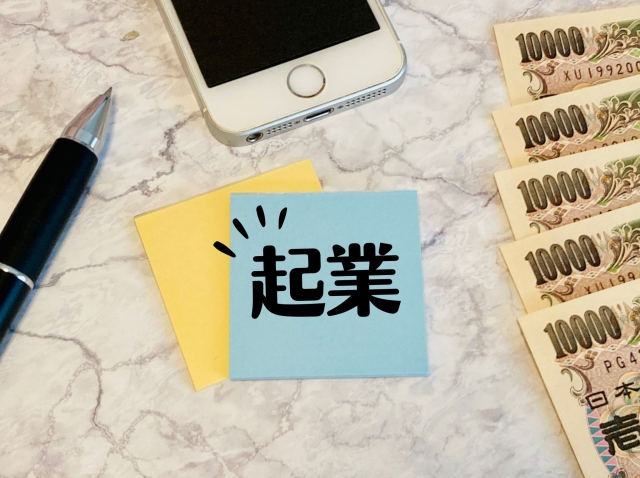大学生の強みが活かせる起業のやり方とアイデア

大学生は社会人と比べて経験が浅いと言われる一方で、社会人にはない大きな強みをもっています。時間の自由度、自由な発想力、豊富な人脈など、大学生の強みを活かした起業のやり方とアイデアを紹介します。
学生のネットワークを活かす
大学には多様な学生が集まっています。学部やサークル活動で培ったネットワークを活かし、ビジネスパートナーや顧客など、起業に必要な人脈を広げることが可能です。たとえば、情報系の学生とデザイン系の学生が協力してアプリやWebサービスを立ち上げるなど、それぞれの専門知識やスキルを活かすことで起業を実現しやすくなります。
さらに、大学の起業サークルなどのコミュニティに参加すると、志の高い仲間や先輩とつながることができます。実際に成功した起業家を招いた勉強会が開かれることもあり、ビジネスのノウハウを学び、具体的なアドバイスをもらえる良い機会です。
大学の研究室や教授と連携する
大学は、最先端の研究や専門知識の宝庫です。研究室や教授と連携することで、高度な技術や知識を必要とする分野で独自のビジネスを始めることができます。たとえば、環境科学の研究室と連携して、持続可能な社会を実現するための新しいビジネスモデルを構築したり、医学研究の成果を応用して、人々の健康をサポートするアプリを開発したりすることが考えられます。
自分の研究をもとにビジネスを展開する場合は、研究室の設備や資料などを活用することで、初期投資を抑えながら高度な研究開発が可能になります。学生起業家にとって、大学のリソースを利用できることは強力な武器となるでしょう。
学生ならではの視点を活かす
大学生は、デジタルネイティブ世代で、SNSやインターネットから常に最新のトレンド情報を取り入れています。既存の枠にとらわれない自由な発想力で、社会人が見落としがちなニーズや課題を発見し、新たなビジネスを展開できる可能性があります。
また、SNSなどを活用して低コストで効果的なプロモーションを行い、多くの人々に自社製品やサービスをアピールしている学生起業家もいます。
学園祭でアピールする
学園祭には学内外から多くの人が集まるため、自分のビジネスやアイデアを広く知ってもらう絶好のチャンスです。製品の販売、デモンストレーション、ワークショップなど、事業のフェーズや業種に適した方法でアピールしましょう。
製品を直接売るだけではなく、来場者からのフィードバックを収集できるため、マーケティングの側面でもメリットがあります。来場者や他の出展者との交流を通じて、新たなビジネスチャンスやコラボレーションの可能性を見出すこともできるでしょう。
大学生の起業はやめとけと言われる理由
大学生の起業は多くの課題やリスクも伴うため、周囲の人からやめとけと言われることもあるでしょう。学生起業家が直面するリスクを理解し、課題に対応することが大切です。
ビジネスの基礎知識や実務経験が不足しているから
大学生は、社会人としての経験が少ない場合が多く、ビジネスの基礎知識や実務経験が不足しがちです。ビジネスを成功させるためには、市場調査、財務管理、マーケティング、法務など幅広い知識とスキルが求められます。
インターン生やアルバイトとして実際に企業で働くことで、起業を考えている分野の業界知識や社会人としての基本的なビジネススキルを身につけることができます。大学の起業支援プログラムやセミナーも積極的に活用しましょう。
起業資金が不足しがちだから
大学生は社会人に比べて貯蓄が少ないケースが多く、起業資金が不足しがちです。自己資金だけで起業できるケースは少なく、一般的には金融機関からの融資や投資家からの出資など、外部からの資金調達が必要となるでしょう。しかし、実績のない大学生の資金調達は簡単ではありません。
専門家に相談して金融機関や投資家を説得できる綿密な事業計画を策定し、資金調達の可能性を高めることが重要です。同時に、クラウドファンディングや助成金など、大学生でも利用しやすい資金調達手段も検討するとよいでしょう。
関連記事:起業資金の最低額の目安は?起業資金不足の対策と50万円あれば始められるビジネス7選
学業との両立が難しくなるから
起業すると、事業に多くの時間を割く必要があり、学生の本分である学業との両立が難しくなる可能性があります。学業がおろそかになると、卒業が遅れたり、就職活動に影響が出たりするリスクもあるため、履修や卒業論文・卒業研究などの予定と照らし合わせ、無理のない計画を立てましょう。
大学の教授やキャリアセンターに事前に相談し、学業と起業の両立に関するアドバイスを受けることも有効です。
精神的な負担になるから
起業にリスクはつきもので、経営者は常に不安やプレッシャーを感じるものです。特に起業したばかりの頃は、わからないことが多い中で、思うように顧客を獲得できなかったり、売上をあげられなかったりすると精神的に大きな負担になります。
精神的な負担を軽減するためには、信頼できる相談相手や仲間を見つけ、悩みを共有することが重要です。また、適度な休息を取り、心身のリフレッシュを図ることも大切です。
成功する保証がないから
起業は、誰もが必ず成功する保証はありません。どれだけ準備や努力を尽くしても、失敗する恐れはあります。失敗のリスクを考え、あなたのためと思って「やめとけ」と言う人もいるかもしれません。周りに止められても起業するのは、起業のリスクを十分に理解した上で、それでも挑戦したいという強い思いがある人たちばかりです。
起業の成功率を高めるには、専門家に相談することが効果的です。
石黒健太税理士事務所は、専門家として大学生の起業をサポートします。税金のことに限らず、事業計画の策定や資金調達のサポート、経営に関するアドバイスなど、起業家のパートナーとしてさまざまなサポートを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。
関連記事:学生が起業するメリットとデメリットは?起業した方がいい人の特徴と成功するためのポイント
大学生起業の成功例

大学生が在学中に起業し、成功を収めた企業もあります。大学生の起業が成功した事例として、3つの有名企業を紹介します。
株式会社リブセンス
株式会社リブセンスは、2006年に当時大学1年生だった村上 太一氏が設立した企業です。成功報酬型の人材紹介サイト「マッハバイト」や日本最大級の転職口コミサイト「転職会議」などを運営しています。
村上氏は、早稲田大学1年生の時に受講した「ベンチャー起業家養成基礎講座」のビジネスプラン発表会で、現在のリブセンスの主力事業である成功報酬型の求人情報サービス「ジョブセンス(現マッハバイト)」の原型となるビジネスプランを発表し、最優秀賞を獲得しました。このプランを実現するために設立したのがリブセンスです。
リブセンスは、独自のビジネスモデルと優れた技術力により、設立からわずか数年で急成長を遂げ、東証一部上場を果たしました。村上氏の事例は、大学生が起業する際のロールモデルとして、今も多くの学生に勇気を与えています。
株式会社Gunosy
株式会社Gunosyは、当時東京大学大学院生だった福島 良典氏、吉田 宏司氏、関 喜史氏の3人が2012年に立ち上げた企業です。ユーザーの興味や関心に合わせてパーソナライズされたニュースや情報を配信するアプリ「Gunosy」などを運営しています。
創業者の3人は在学中に人工知能の研究を行い、その技術を応用してGunosyを開発しました。当初は起業を目的としておらず、技術を使って面白いプロダクトを作りたいという思いや、SNSを見ている中で時間の無駄を感じたことがサービス立ち上げのきっかけとなったといいます。
Gunosyは、学生が持つ専門的な知識や技術が、新しいサービスを生み出す力になった典型例と言えるでしょう。
株式会社Labit
株式会社Labitは、2011年当時、慶應義塾大学に在学中だった鶴田 浩之氏が大学の仲間と創業した企業です。
学生ならではのアイデアをもとに、大学生向けのスケジュール管理サービス「すごい時間割」などを開発。2011年の東日本大震災時には、Webサイト「prayforjapan.jp」を立ち上げ、国内外から多くのアクセスを集めました。現在はGunosyの連結子会社となっている「ゲームエイト」も、元はLabitの一事業として始まったものです。
Labitは、学生ならではのアイデアを活かし、仲間どうしで起業して成功を収めた事例と言えるでしょう。
大学生起業の成功率を高めるポイント
大学生の起業は簡単ではありません。アイデアや情熱は大切ですが、それだけでは事業を継続していくのが困難なケースもあります。成功率を高めるには成功のためのポイントを押さえ、地道に準備を進めることが大切です。
ビジネスに必要なスキルと知識を学ぶ
組織に所属する場合とは異なり、自分自身で起業する場合はビジネスに関することすべてが自分の仕事です。経営者として必要なスキルと知識は多岐にわたります。
ビジネスに必要なスキルの一例
・コミュニケーション能力
・プレゼンテーションスキル
・組織運営、マネジメントスキル
・時間管理能力
・財務や資金調達に関するの知識
・マーケティングに関する知識
・会計や税務の知識
・会社設立、契約、知的財産権などの法律知識
書籍やインターネット、セミナーなどを活用して、積極的に学びましょう。また、必要なスキルをすべて身につけてから起業しようと思うときりがありません。実務の中で磨かれるスキルもあるため、起業してからも学び続ける姿勢が大切です。
事業を通して成し遂げたい明確なビジョンを持つ
なんのために起業するのか、どのような事業を通して何を成し遂げたいのか、明確なビジョンを持つことが大切です。具体的な道筋を描いていれば、困難な状況に陥ったときに同軌道修正していくかの経営判断をする指針となります。
また、資金調達やアライアンスなどで第三者に自社のビジネスについて明確なビジョンを語れると、協力を得やすくなるメリットがあります。市場における自分の立ち位置や強み、社会のニーズを把握し、自分の事業がどのように社会に貢献できるかを考えることも大切です。
スモールビジネスからスタートする
最初から大きな事業に挑戦するのではなく、まずは小さな規模から始めることをおすすめします。スモールビジネスから始めることで、リスクを抑えながら経験を積むことができます。
たとえば、アプリ開発・運営、オンラインストア、フリーランスとしての活動などが挙げられます。業界知識を得て経験を積みながら、顧客のニーズや市場の動向に合わせて徐々に事業を拡大していくことで、成功するケースもあります。
関連記事:個人事業主として起業するには何が必要?毎月やることと向いている性格を解説
しっかりとした事業計画を作成する
事業計画は、事業の目標や戦略、資金計画などをまとめたものです。事業計画をしっかりと作成することで、目標達成までの道筋が明確になります。
事業計画書の主な内容
|
記載事項 |
内容 |
|
事業概要 |
事業の概要、創業の経緯など |
|
ビジネスモデル |
商品・サービスの内容や特長、マーケティング戦略など |
|
市場分析 |
ターゲット顧客や競合他社の分析、自社の優位性 |
|
資金計画 |
必要な初期投資や運転資金、資金調達の方法 |
|
収支計画 |
売上や経費の予測 |
創業時の資金調達の際には、事業計画書が重要な資料となります。説得力のある計画を策定するために、専門家のサポートを受けることも有効です。
関連記事:事業計画書のスムーズな作り方とは?わかりやすい方法を解説
信頼できる相談相手や仲間を作る
起業に悩みはつきものです。一人で抱え込まず、誰かに相談しましょう。仲間内では解決できない専門的な課題は、大学の教授、先輩起業家、税理士、経営コンサルタントなどそれぞれの領域の専門家に相談すると具体的なアドバイスが得られます。起業家コミュニティや交流会などに参加し、同じ志を持つ仲間を見つけることも有効です。
石黒健太税理士事務所は、起業家のサポートを得意としています。税理士に相談するのはハードルが高いと感じるかもしれませんが、税金のことだけでなく、事業計画や資金調達など経営に関する相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
関連記事:税理士は無料相談でどこまで対応してくれる?電話相談はおすすめできない理由と有意義にするポイント
大学生の間にスムーズに起業するやり方

起業したいけれど何から始めていいかわからない方のために、大学生の間にスムーズに起業する方法を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:アイデアを固める
起業の第一歩は、具体的なビジネスアイデアを固めることです。単に「儲かりそう」というだけでなく、自分が情熱をもって事業を継続していけるかも重要なポイントです。必ずしも突飛なアイデアである必要はなく、自分の得意分野や、自分が貢献したい社会課題などをベースに考えるとよいでしょう。
次に、ターゲットとする市場の規模や成長性、顧客層を分析します。競合となるサービスや商品を調査し、差別化できるポイントを探しましょう。実際に顧客となりうる人にインタビューしたり、アンケートを実施したりして、アイデアのニーズを検証します。プロトタイプ(試作品)を作成し、実際に使ってもらってフィードバックを得ることも有効です。
関連記事:起業したいけどアイデアがないときの対策は?起業アイデアが思いつかないときの対策と成功率を高めるポイント
ステップ2:起業の準備をする
アイデアが固まったら、具体的な起業準備を進めます。焦って事業を始めるのではなく、しっかり事業の基盤づくりをすることが大切です。
必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、事業計画書を策定しましょう。創業者自身が思い描くビジネスを言語化し整理するとともに、他者に伝える材料となります。また、ここで具体的な計画を立てることで、準備するべき資金の金額も見えてきます。
関連記事:起業するにはまず何から始める?スムーズに進めるための5つのステップと成功する人の特徴
ステップ3:資金調達をする
法人設立費用などの起業に必要な資金を自己資金だけでは賄えない場合は、外部からの資金調達を検討しましょう。大学生向けの起業支援プログラムなど、学生起業家でも利用できる助成金や融資制度もあります。
たとえば、日本政策金融公庫などの金融機関からの融資、国や地方自治体の補助金や助成金、クラウドファンディングなどの方法です。どの方法でも、安定して事業を継続していける見込みがあるだけでなく、アイデアやストーリーを効果的に伝え、共感してもらうことが重要です。条件や申請方法などを確認し、自分に適した方法を選択しましょう。
ステップ4:起業する
個人事業の場合は、税務署に開業届を提出するだけで事業を始められます。株式会社や合同会社のような法人は、会社設立登記が必要なため、個人事業を始める場合に比べて時間と費用がかかります。
登記申請は司法書士に依頼することも可能です。また、株式会社と合同会社はそれぞれ異なる特色があるため、どちらを選ぶか迷ったら専門家に相談すると安心です。
関連記事:縁起がいい会社名・成功しやすい会社名の決め方は?注意すべき基本ルールと決まらないときの対策
ステップ5:起業後の手続きをする
起業後のタイミングで必要な手続きをきちんと済ませましょう。申請が遅れると法律違反になったり、税制上のメリットを受けられなかったりするリスクがあります。
起業後の手続きの例
|
提出先 |
提出する書類 |
|
税務署 |
個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業の場合) 法人設立届出書(法人の場合) 青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合) 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合) |
|
都道府県・市区町村 |
法人設立届出書(法人の場合) |
|
年金事務所 |
新規適用届 被保険者資格取得届 |
|
労働基準監督署 |
労働保険 保険関係成立届 労働保険 概算保険料申告書 |
|
銀行 |
法人名義の口座開設 |
|
所轄の官公庁 |
許認可申請書(必要な業種の場合) |
上記のほかに、日々の会計記帳や給与計算など継続して行う事務作業も発生します。取引先や従業員との契約書の作成も必要です。手続きをもれなく正確に行いたい場合や、申請や届出の手間を減らしたい場合は、専門家に依頼するのも有効な手段です。
起業の悩みはお気軽にご相談を!
大学生の起業は、柔軟な発想力や行動力を活かせる一方で、ビジネスの経験値や資金力に課題があります。起業成功の道のりは決して容易ではありませんが、専門家のサポートも活用しながら綿密な準備と計画を進めることで実現できます。

起業のお悩みがある方は、ぜひ石黒健太税理士事務所にご相談ください。専門家があなたのビジネスアイデアの実現をサポートいたします。電話での相談もできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。