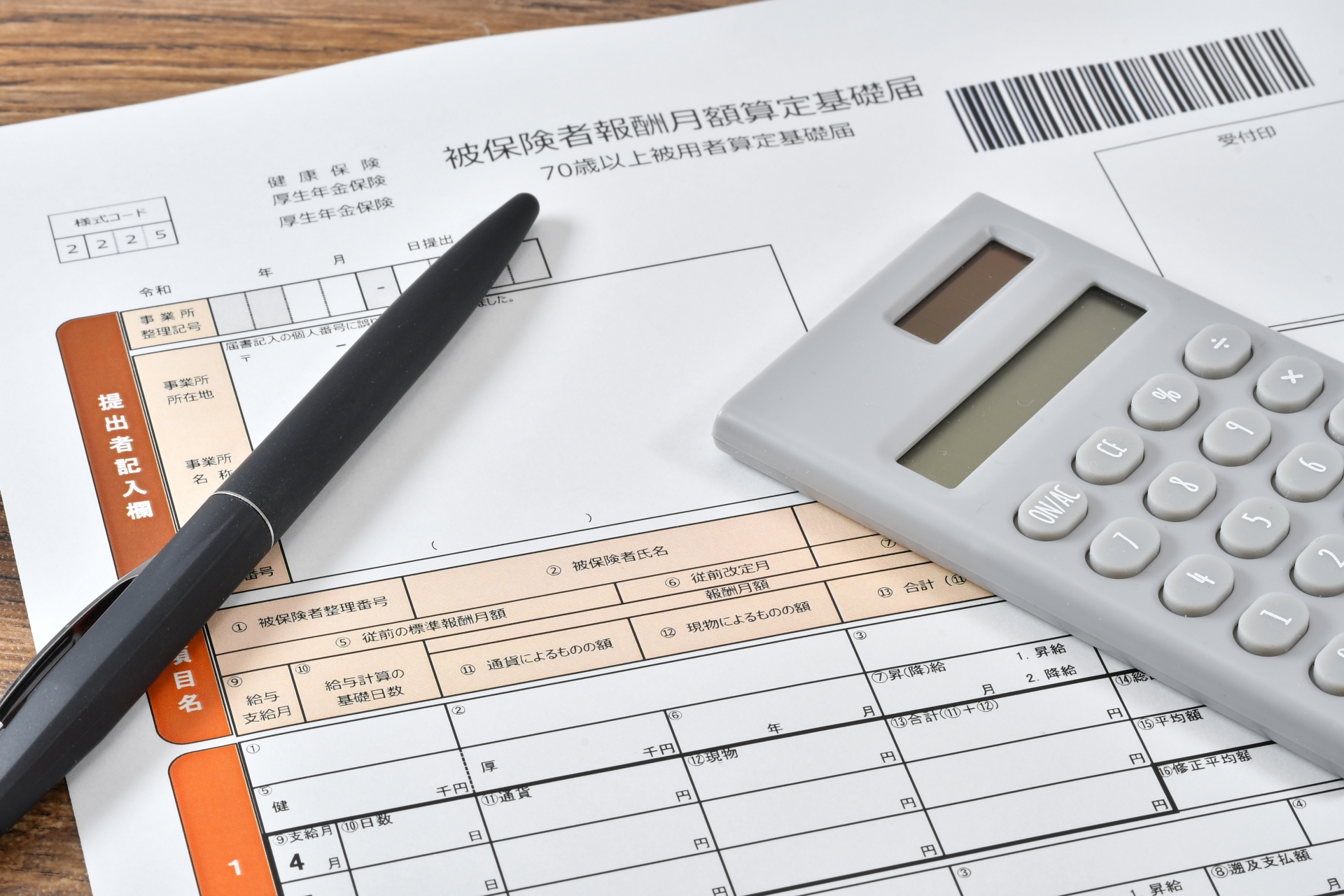1人社長の社会保険料はいくら?

社会保険料とは、病気や怪我のときの給付にかかる「健康保険」と、公的年金制度である「厚生年金」などにかかる保険料のことです。社会保険料では、会社から支給される報酬の額から「標準報酬月額」を算出し、その額に保険料率をかけて計算します。
そのため、社会保険料の金額は、報酬によって異なり、報酬額が多いほど保険料額も増加する傾向があります。また、社会保険料の金額は、会社と個人で折半するので、保険料額が高額になるほど、会社が負担する金額も増加するので注意が必要です。
役員報酬が2万円、5万円、8万円のケースで支払う社会保険料の金額は、それぞれ以下の通りです。
|
役員報酬の金額 |
社会保険料 |
|
2万円 |
21,921.4円(個人負担額 10,961円) |
|
5万円 |
21,921.4円(個人負担額 10,961円) |
|
8万円 |
23,927.4円(個人負担額 11,964円) |
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合を想定
※全国健康保険協会(協会けんぽ)の京都府の税率を使用
それぞれの内訳などについて、くわしく解説していきます。
役員報酬2万円の社会保険料
役員報酬を月額2万円に設定した場合、健康保険料と厚生年金保険料の合計(社会保険料額)は以下の通りです。
【折半する前の全体の保険料額】
|
健康保険料 |
5,817.4円 (標準報酬月額 58,000 × 健康保険料率 10.03%) |
|
厚生年金保険料 |
16,104円 (標準報酬月額 88,000 × 厚生年金保険料率 18.300%) |
|
合計 |
21,921.4円 |
また、個人の負担額は、全体の保険料の半額となります。
【個人の負担分】
|
健康保険料 |
2,909円(端数切り上げ) (標準報酬月額 58,000 × 健康保険料率 10.03% ÷ 2) |
|
厚生年金保険料 |
8,052円 (標準報酬月額 88,000 × 厚生年金保険料率 18.300% ÷ 2) |
|
合計 |
10,961円 |
そして、全体の保険料から個人の負担分を差し引けば、会社の負担額が算出できます。
【会社の負担分】
|
健康保険料 |
2,908円(端数切り捨て) (全体の健康保険料5,817.4円-個人の負担分2,909円) |
|
厚生年金保険料 |
8,052円 (全体の保険料16,104円-個人の負担分8,052円) |
|
合計 |
10,960円 |
また、個人と会社で折半した金額に端数が生じるときは、個人の負担分の端数について、通常は50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ処理を行います。そのため、個人と会社の負担額が必ずしも同額になるわけではないので知っておきましょう。ただし、労使間で特約がある場合などは、端数を切り捨てることができます。
参考:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
参考:日本年金機構「保険料の計算方法について」
役員報酬5万円の社会保険料
役員報酬を月額5万円に設定した場合、健康保険料と厚生年金保険料の合計(社会保険料額)や、個人・会社の負担額は以下の通りです。
【折半する前の全体の保険料額】
|
健康保険料 |
5,817.4円 (標準報酬月額 58,000 × 健康保険料率 10.03%) |
|
厚生年金保険料 |
16,104円 (標準報酬月額 88,000 × 厚生年金保険料率 18.300%) |
|
合計 |
21,921.4円 |
【個人の負担分】
|
健康保険料 |
2,909円(端数切り上げ) (標準報酬月額 58,000 × 健康保険料率 10.03% ÷ 2) |
|
厚生年金保険料 |
8,052円 (標準報酬月額 88,000 × 厚生年金保険料率 18.300% ÷ 2) |
|
合計 |
10,961円 |
【会社の負担分】
|
健康保険料 |
2,908円(端数切り捨て) (全体の健康保険料5,817.4円-個人の負担分2,909円) |
|
厚生年金保険料 |
8,052円 (全体の保険料16,104円-個人の負担分8,052円) |
|
合計 |
10,960円 |
役員報酬が月額5万円のケースと月2万円のケースでは、負担する社会保険料の金額は同じになります。これは、保険料の計算に用いられる「標準報酬月額」が同じ金額だからです。
健康保険と厚生年金保険では、報酬の月額ごとに等級が決められています。等級が高ければ、標準報酬月額も高額になりますが、一番低い等級(等級1)は、報酬月額が63,000円未満の人が対象です。
つまり、月額63,000円未満の報酬であれば、社会保険料の負担額は最低額に抑えられるのです。報酬が月5万円であっても、月2万円のケースと同様に社会保険料は最低額になります。
役員報酬8万円の社会保険料
役員報酬を月額8万円に設定した場合、標準報酬月額の等級が上がるため、これまで紹介したケースよりも社会保険料の金額が増加します。全体の保険料額、個人・会社の負担額については、以下の通りです。
【折半する前の全体の保険料額】
|
健康保険料 |
7,823.4円 (標準報酬月額 78,000 × 健康保険料率 10.03%) |
|
厚生年金保険料 |
16,104円 (標準報酬月額 88,000 × 厚生年金保険料率 18.300%) |
|
合計 |
23,927.4円 |
【個人の負担分】
|
健康保険料 |
3,912円(端数切り上げ) (標準報酬月額 78,000 × 健康保険料率 10.03% ÷ 2) |
|
厚生年金保険料 |
8,052円 (標準報酬月額 88,000 × 厚生年金保険料率 18.300% ÷ 2) |
|
合計 |
11,964円 |
【会社の負担分】
|
健康保険料 |
3,911円(端数切り捨て) (全体の健康保険料7,823.4円-個人の負担分3,912円) |
|
厚生年金保険料 |
8,052円 (全体の保険料5,817.4円-個人の負担分2,909円) |
|
合計 |
11,963円 |
報酬が月8万円の場合、健康保険の標準報酬月額の等級は「3」に該当します。等級が上がったことにより、月2万円・月5万円のケースよりも、社会保険料の全体額が2,000円ほど上昇したことがわかります。
ただし、あくまで一例です。介護保険の第2号被保険者となる場合や、お住まいの都道府県によっては、適用する税率が異なります。より正確な結果が知りたい場合は、自身の状況に置き換えてシミュレーションすることが大切です。
当事務所では、社会保険料などのコストを踏まえた役員報酬のご相談が可能です。お電話でもご相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
1人社長の社会保険料を計算する方法
1人社長の場合、事業活動だけでなく、総務や経理の仕事もこなさなければなりません。ここからは、社会保険料をスムーズに計算するための3ステップを解説します。
ステップ1:標準報酬月額を決定する
ステップ2:保険料を調べる
ステップ3:社会保険料を計算する
これらのステップは、社会保険料のコストを把握した上で、役員報酬の金額を決定したい人にも参考になるでしょう。順番に解説していきます。
ステップ1:標準報酬月額を決定する
会社員の給与などは、残業代や手当などで毎月変動しますが、月ごとに保険料を計算するのは事務が煩雑です。そこで、社会保険制度では、事業主が支払った報酬や賃金などの金額に応じて区分分け(等級の設定)を行い、仮置きの数値である「標準報酬月額」を使って保険料を計算します。
また、標準報酬月額は主に、以下の時期で決定します。
・資格取得時決定(社会保険に加入した時期)
・定時決定(毎年7月ごろ)
・随時改定(昇給などで急激に賃金や報酬額が変わるとき)
・育児休業時終了時改定(育児等を理由に報酬額が変わるとき)
標準報酬月額は、月の報酬や賃金などをもとに、どの等級に属するか確認して決定します。そして、標準報酬月額は見直しのために、毎年1回「定時改定」と呼ばれる処理が必要です。
定時改定では、4月〜6月までに受け取った報酬の平均額を等級に当てはめて、標準報酬月額を決定します。この処理では、加入している保険者に対して、「算定基礎届」を提出しなければなりません。以下の記事では、定時決定に必要な算定基礎届について解説しています。
関連記事:算定基礎届とは?書き方や出さなかったらどうなるか解説
ステップ2:保険料を調べる
標準報酬月額から納める保険料額を調べるには、保険料額表を参照しましょう。保険料額表とは、等級や標準報酬月額ごとに納める社会保険額が一覧になっている表です。保険者のホームページに掲載されているため、確認してみてください。
また、全国健康保険協会(協会けんぽ)については、こちらから確認いただけます。健康保険の運営は、各都道府県の協会支部が行っているため、閲覧の際は、お住まいの自治体を選ぶように注意しましょう。
ステップ3:社会保険料を計算する
社会保険料を計算するときは、「健康保険料」と「厚生年金保険料」で保険料率が異なるため、分けて計算を行いましょう。それぞれの金額は、以下の式で求めることができます。
【折半する前の全体の保険料額の算出方法】
|
健康保険料の計算式 |
標準報酬月額×健康保険料率 |
|
厚生年金保険料の計算式 |
標準報酬月額×厚生年金保険料率 |
【個人負担分の保険料額の算出方法】
|
健康保険料の計算式 |
標準報酬月額×健康保険料率÷2 |
|
厚生年金保険料の計算式 |
標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2 |
適用する税率は、40歳~64歳の人とそれ以外の人で異なります。40歳~64歳に該当する人は、介護保険の第2号被保険者として、健康保険料に上乗せする形で介護保険料を納付しなければなりません。適用する税率の詳細は、保険料額表に記載があるので確認しましょう。
社会保険料は会社が半分負担する
役員報酬の金額を決めるにあたり、個人負担の社会保険料が気になる方も多いでしょう。しかし、社会保険料は会社と折半して納める仕組みのため、シミュレーションの際は、会社負担分を考慮する必要があります。
また、会社負担分を考慮できていない場合、社会保険料の納付によって現金が不足するなど、経営にまで影響を及ぼす恐れがあり危険です。会社運営のコストには、事業に関連するものだけでなく、税や社会保険料なども含まれます。
社会保険料の負担は、会社の利益に直結するため、負担額のシミュレーションを行い、売上とのバランスを図ることが大切です。当事務所でも税や社会保険料の負担を考慮したシミュレーションが可能です。お電話でもご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
関連記事:個人事業主と法人化はどっちが得?シミュレーション結果を解説
1人社長の会社が社会保険の加入を無視するとどうなる?

「他に従業員がいなければ、社会保険に加入しなくてもいいだろう」と、考える人も多いでしょう。しかし、会社などの法人の場合、社長1人しかいなくても社会保険の強制適用事業所となるため、加入手続きが必須になります。
ここからは、社会保険の加入を無視するとどうなるのか、解説していきます。
年金事務所から加入要請や警告文が届く
社会保険に加入しないままにしておくと、年金事務所から加入要請の連絡が入ります。そして、連絡も無視した場合、指導や警告文が入ることになります。さらに、警告文を無視すると、最悪の場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される恐れがあるため注意が必要です。
また、罰則を科せられると、資金の減少だけでなく、社会的信用の低下も招きます。社会的信用は、融資や取引などで重視されるポイントです。事業活動を円滑に行うためにも、社会保険の加入は期限内に行いましょう。
参考:日本年金機構「法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。」
強制加入によって保険料が徴収される
社会保険の加入手続きを無視すると、年金事務所などによって強制加入の手続きが取られます。そして、納めていない保険料については、過去2年に遡って請求されることになります。請求を遡及されたことで支払う保険料が高額となり、資金繰りが悪化するケースも珍しくありません。
また、遡って請求された保険料については、一括納付が原則です。一括納付の納期を過ぎると、延滞金などのペナルティが発生し、未納を放置すると、財産の差押え処分の対象になる恐れがあります。差押え処分では、融資元や金融機関に連絡が入る可能性があり、信用失墜を招くことにも繋がります。
参考:地方厚生局
助成金が受けられない
助成金とは、主に労働環境を改善する目的で、国や自治体が支給するお金のことです。助成金には、様々な種類がありますが、「キャリアアップ助成金」などは、要件を満たす事業所や労働者であれば、社会保険の加入が助成金を受ける要件となっています。そのため、未加入の場合、助成金を受け取ることができません。
また、助成金は、融資と違って返済の必要がないため、資金繰りの改善に有効な手段と言えます。「困ったときに受け取れない」といった状況を避けるためにも、期限内に手続きを行いましょう。
創業時の社会保険の手続きをスムーズにする方法
これから創業するにあたり、社会保険の手続きが分からない方も多いでしょう。創業時の社会保険の手続きは、会社を設立してから5日以内に行わなければなりません。期限が短く、準備物も多いため、慌ててしまうことも珍しくありません。
ここからは、スムーズに社会保険の手続きを行う方法について紹介します。
必要書類を準備する
創業時には、社会保険の適用事業所の届出と、健康保険・厚生年金保険の加入手続きが必要です。手続きは、事業所を管轄する年金事務所で行います。そのときに、以下の書類が必要になるため、前もって準備しておきましょう。
・健康保険 厚生年金保険新規適用届
・法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
・健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届(配偶者など被扶養者がいる場合)
年金事務所窓口への持参が困難なときは、郵送や電子申請でも対応が可能です。また、従業員を雇う場合は、上記の手続きとは別に、ハローワーク(労働基準監督署)で雇用保険・労働保険の手続きも必要です。
参考:日本年金機構「新規適用の手続き」
社会保険労務士に依頼する
社会保険労務士とは、労働や社会保険に関する専門家です。労務管理や社会保険制度に精通しているため、依頼することで書類の提出を代行できるのがメリットです。依頼すれば、事業に専念しやすくなるので、スピード感を持って創業できるでしょう。
また、社会保険や雇用保険の代行は、社会保険労務士にしか認められていない独占業務でもあります。他の専門家では取り扱いできないため、社会保険など、ピンポイントの業務を相談したい方は、社会保険労務士がおすすめです。
創業を得意とする専門家に相談する
創業時には、資金不足や役員報酬の決定、税金対策など様々な悩みがつきまといます。しかし、前述した社会保険労務士では、労務や社会保険などのピンポイントな分野しか相談できません。そのため、幅広い分野でサポートを得たいなら、創業を得意とする専門家に相談するのがベストです。
創業を得意とする専門家には、実績のある税理士などが挙げられます。税理士は、経営に関する問題、融資・補助金などのサポート、税や社会保険のコストなど、様々な相談が可能です。
特に、創業時の役員報酬は、事業開始後の手取りや手元資金に影響する項目です。役員報酬額をいくらにすれば得になるかなど、具体的な提案を求めるなら、創業の実績がある税理士を選びましょう。以下の記事では、税理士選びの基準などについて解説しています。
関連記事:企業の成長が加速する税理士の選び方は?依頼する目的から選ぶ税理士の選び方とポイント
役員報酬の悩みはお気軽にご相談を!
社会保険料がいくらになるかは、設定する役員報酬の金額によって異なります。また、社会保険料の納付は、毎月発生するコストです。役員報酬を決めるときは、会社が負担する社会保険料の金額を考慮した上で検討する必要があるでしょう。

役員報酬でお悩みでしたら、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、創業などのスタートアップに携わった実績が200件以上あり、あなたに最適なご提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。ご相談はお電話でも対応しております。