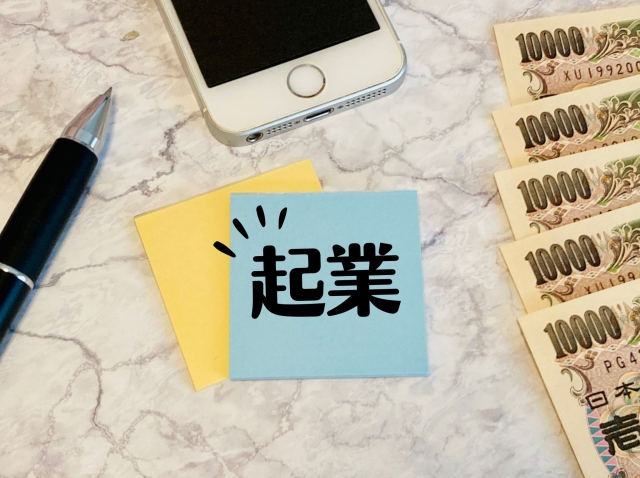起業資金の最低額の目安

起業形態には、個人事業主と法人があります。個人事業主とは、法人設立を行わず、個人で事業を営む人のことを指します。また、法人には複数の種類があり、種類によって費用面や手続きに違いがあるので注意しましょう。
ここからは、個人事業主、合同会社、株式会社の3種類について、起業資金の最低額の目安を紹介します。
個人事業主:0円から起業できる
個人事業主になるには、税務署に開業届を提出する必要があります。この届出の作成や提出には費用がかからないため、0円から起業することが可能です。ただし、あくまで手続き上の費用です。機材の購入費や事務所の賃料などが発生する場合は、別途資金が必要です。
また、個人事業主と混同されやすい言葉に「フリーランス」があります。フリーランスとは、特定の会社に属さず、個人で仕事を請け負う働き方のことです。フリーランスでも、事業所得を得るなら、開業届の提出は必須です。
そして、個人事業主の手続きは開業届だけではありません。所得税の確定申告で青色申告を希望する場合は、原則として開業後2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。青色申告は、白色申告に比べて税制上の優遇が多いため、節税対策に最適です。
以下の記事では、個人事業主として起業するときに必要な手続きなどをくわしく紹介しています。
関連記事:個人事業主として起業するには何が必要?毎月やることと向いている性格を解説
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
合同会社:6万円以上が目安
合同会社とは、出資者と経営者が同一の会社形態のことです。合同会社の設立費用は、6万円以上が目安で、株式会社設立よりも費用が安く抑えられます。合同会社設立で発生する費用は、以下の通りです。
・登録免許税…6万円~
・定款の収入印紙代…4万円(電子定款の場合は不要)
会社の設立には、法人登記と定款の作成が必須です。登録免許税は、法人登記の際に課せられる税金です。資本金の金額によって異なりますが、最低6万円の納付が必要になります。
また、定款は紙か電子で作成します。紙の定款は、4万円の収入印紙の貼り付けが必要ですが、電子定款は収入印紙が不要です。費用を抑えたい場合は、電子定款を選ぶと良いでしょう。ただし、電子定款の作成には、電子署名ソフトの導入など環境の整備が必要です。
関連記事:自分で合同会社を設立するときの費用の目安と内訳は?設立後にかかるランニングコストと注意点
株式会社:20万円以上が目安
株式会社とは、株式を発行して資金を集める会社形態です。会社の所有者は株主で、実際の経営は代表取締役が行います。株式会社の設立費用は、20万円以上が目安で、合同会社よりも資金が多くかかるのが特徴です。株式会社設立で発生する費用には、以下があります。
・登録免許税 15万円~
・定款の収入印紙代 4万円(電子定款の場合は不要)
・定款の認証手数料 3~5万円
・定款謄本手数料 約2千円
株式会社の登録免許税は、最低15万円の納付が必要です。また、定款の手続きも合同会社とは異なります。株式会社の場合、作成した定款は、公正証書役場で「定款認証」の手続きが必要です。定款認証では、3万円以上の手数料が発生します。
合同会社よりも手続きに費用や手間がかかる株式会社ですが、株式によって多くの人から出資を受けやすいなどのメリットがあるのも事実です。起業にかかる費用以外にも、事業や経営時に得られるメリットやデメリットも把握した上で、起業形態を選びましょう。
関連記事:株式会社の設立費用の目安と内訳は?資本金1円でも節約にならない理由と節約する方法を解説
個人事業主と法人設立で迷ったら専門家に相談する
事業開始後は、仕入れにかかる費用や取引先への支払い、税金の納付など、様々なコストが発生します。特に、税金の支払いは最終的な手取りを左右する重要な要素です。節税対策が不十分な場合、多額の税金によってキャッシュフローが悪化することも珍しくありません。
事業で発生する税金の種類は、個人事業主と法人で異なります。法人は個人事業主よりも納める税金の種類が多く、経費として認められる費用も多いです。そのため、一般的には法人の方が節税になると言われています。
しかし、法人のメリットは、すべての人が享受できるわけではありません。課税対象となる所得や、事業規模などによっては、法人でも十分な節税効果が得られない可能性があります。起業後は、簡単に形態の変更ができないため、選択を後悔することも珍しくありません。
起業形態は、将来の展望、事業規模に合わせた選択が大切です。コストを抑えたい方や、事業での手取りを増やしたい方は、専門家に相談しましょう。当事務所でもご相談可能です。お電話でもご相談できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
関連記事:自社にあった税理士の探し方は?気をつけることを税理士目線で解説
起業資金として最低限は確保したい費用
起業にかかる費用について、くわしく知りたい方も多いでしょう。業種によっても様々ですが、最低限として以下の費用は確保しておきましょう。
・会社設立にかかる費用
・パソコンやプリンターの購入費用
・事業を運営するための運転資金
これらの費用が確保できないケースでは、「社会的信用が得られない」「事業の継続が困難になる」などのデメリットが生じるかもしれません。内容をくわしく解説します。
会社設立にかかる費用
会社を設立して起業するケースでは、前述した登録免許税や、定款に関連する費用に加え、資本金の準備も必要です。資本金の設定額は自由に決められますが、経営や事業を行う際の元手になるため、必要額は事前に確認しておきましょう。
また、業種によっては、国や自治体からの許認可が必要なものもあります。特に、建設業などの特定の業種では、許可を得る際に高額な資本金を求められます。許認可が得られなければ事業が成り立たない恐れがあるため、これから始めるビジネスに許認可が必要かは調べておきましょう。
以下の記事では、中小企業の資本金の平均額や、税金や許認可との関係についてくわしく解説しています。会社設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:中小企業の資本金の平均額は?資本金を増やさない理由と税金との関係
パソコンやプリンターの購入費用
起業後は、個人事業主や法人問わず、帳簿付けや在庫管理などの業務が発生します。これらは紙で管理することも可能ですが、多くの時間や労力がかかります。作業効率を向上させるためにもパソコンやプリンターは、必須であると言えるでしょう。
また、パソコンなどの電子機器は、型落ち品だとWindowsなどのOSのバージョンが古く、使いづらい可能性があります。セキュリティリスクや不具合が生じるリスクも高まるため、販売から年数が経っている機器は避けた方が良いでしょう。
業務を滞りなく遂行するなら、パソコンは10万円以上のモデルを、プリンターは1〜3万円のモデルから選ぶのがおすすめです。これらの購入費用は、個人事業主や法人どちらも経費になり、価格によっては減価償却できます。購入時の領収書は必ず保管しておきましょう。
事業を運営するための運転資金
運転資金とは、事業の継続に必要な資金のことです。事業には、仕入れのコストや、賃料、光熱費の支払いなど、様々な支払いが生じます。しかし、事業が軌道に乗るまでは、売上からこれらの支払いを賄えないことも多いため、運転資金を投じる必要があるのです。
運転資金の目安は、一般的に月商の3ヶ月程度の金額です。ただし、建設業や製造業などは、設備投資などが多いため、運転資金も高額になる傾向があります。事業の運営に必要な運転資金が不足する場合は、融資で補う方法もあります。くわしくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:運転資金の融資が受けられる金融機関は?資金不足を解消する方法を解説
50万円あれば始められるビジネス7選

多額の起業資金を用意するのは難しい方も多いでしょう。起業資金がかさむ理由には、高額な設備投資や、店舗などの賃料の支払いが挙げられます。これらの費用を抑えることができれば、少額で起業することが可能です。
ここからは、50万円以下で始められるビジネスを厳選して紹介します。
・Webライター
・オンライン講師
・ECサイトの運営
・アフィリエイト
・動画編集
・家事代行サービス
・ソーシャルメディア運用代行
内容をくわしく解説します。起業のアイデアにもなるので、ぜひ参考にしてください。
Webライター
Webライターとは、インターネット上のWebメディアの記事やコラム、文章を執筆する仕事です。執筆だけでなく、内容のリサーチや構成の作成なども業務に含まれます。仕事を獲得する手段としては、クラウドソーシングサイトや求人情報サイトを利用するのが一般的です。
Webライターで必要な初期費用には、以下が挙げられます。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンの購入費
・作業スペースの賃料(自宅で事業を行う場合は不要)
必要資金の目安は、10万円前後です。自宅で事業を行う場合や、すでにパソコンを所有している場合は、0円での起業もできます。文章を書くことが好きな方や知識欲が強い方、初期費用を最小限に抑えたい方などにおすすめの仕事です。
オンライン講師
オンライン講師とは、インターネット上で自分が持つスキルを生徒に指導する仕事です。学生向けの家庭教師や英会話のレッスン、楽器の演奏指導など自分の得意なことを仕事にできるのが魅力と言えます。オンライン講師で必要な初期費用には、以下が挙げられます。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンの購入費
・Webカメラやマイクの購入費(パソコンに内蔵している場合は不要)
・作業スペースの賃料(自宅で事業を行う場合は不要)
自宅で起業する場合は、10万円~30万円が目安です。一方、作業場所を借りる場合は、追加で20万円以上の費用が必要になるでしょう。人に教えることが好きな方や、専門的な知識を有する方におすすめの仕事です。
ECサイトの運営
ECサイトの運営とは、インターネット上で商品の販売活動を行う仕事のことです。具体的には、オンラインショップなどを立ち上げ、販売促進や集客、在庫の管理などを行います。実店舗を持たない代わりに、全国規模でビジネスできるのがメリットと言えます。
ECサイトの運営では、以下の初期費用が必要です。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンの購入費
・ECサイトの構築費
・サーバー費用
・商品の仕入れ費用
・倉庫の賃料(自宅で在庫を保管する場合は不要)
ECサイト構築の主な方法には、他社のプラットフォームを利用する方法と、自分でプログラムする方法があります。自分でプログラムする方法は、専門知識が必要で、費用も高額になりやすいです。費用を抑えるなら既存のプラットフォームを利用すると良いでしょう。
既存のプラットフォームや倉庫の賃料などがない場合は、50万円以下が資金の相場です。しかし、梱包や配送を他者に委託するなど、事業規模が大きい場合は、100万円程度必要になります。顧客対応に自信のある方や、数字やトレンドに強い方におすすめの仕事です。
アフィリエイト
アフィリエイトとは、ブログやSNSで企業の商品などを紹介し、成果に応じた報酬を得る仕事です。主な業務内容には、ブログやSNSの記事投稿、PR文章や素材の作成、訪問者の行動などの分析が挙げられます。
また、広告には、美容や家電など様々な種類があるため、自分の好きなことを発信しながら収入を得ることができるのは魅力と言えます。ただし、読者やファンを獲得するまでには時間を要します。収益化の達成には、長期的な視点と忍耐力が必要です。
アフィリエイトでは、以下の初期投資が必要です。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンの購入費
・ブログの構築費用(SNSの場合は不要)
・サーバー費用(SNSの場合は不要)
パソコンやインターネット環境などが整っている場合は、2万円以下で起業できます。また、InstagramなどのSNSを利用する場合は、0円での起業も可能です。低リスクでビジネスを始めたい方や、作業が好きな方におすすめの仕事です。
動画編集
動画編集では、映像のカットや加工などの編集、BGMの挿入などを行います。仕事獲得の手段としては、クラウドソーシングサイトなどを介して、YouTuberや企業から業務委託を受ける方法が一般的です。CM作成や研修動画の作成など、案件の種類も幅広く、需要の高い仕事と言えます。
動画編集では、以下の初期費用が必要です。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンの購入費
・動画編集ソフトの導入費
動画編集で起業するときの目安は、20万円〜30万円です。動画編集ソフトを動かす際は、大量のデータ処理が行われます。そのため、低スペックのパソコンだと、動画処理がフリーズするなどのデメリットが生じます。
動画処理に適したパソコンの価格は、20万円以上が相場のため、他の職業に比べてパソコンの購入費用が高くなる傾向があるので注意しましょう。細かい作業が好きな方や、デザイン力がある方におすすめの仕事です。
家事代行サービス
家事代行サービスとは、個人宅で料理や掃除などの家事全般を行う仕事です。共働き世帯や高齢者世帯など、家事を行うことが難しい家庭を支援します。特別なスキルを必要としないため、仕事にブランクのある主婦でも活躍できるでしょう。
家事代行サービスでは、以下の初期費用が必要です。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンの購入費
・車の購入費用
・事務所の賃料(自宅で事業を行う場合は不要)
家事代行サービスでは、依頼主宅への移動手段として車が必要です。自宅を事務所として利用する場合や、自家用車を使用する際は、50万円以下で起業できます。家事が得意な方や、気配り上手な方におすすめの仕事です。
ソーシャルメディア運用代行
ソーシャルメディア運用代行とは、企業や個人の代わりに、InstagramやYouTubeなどのSNSの運用を行う仕事です。具体的な仕事内容としては、SNSへの投稿や企画の立案、分析、コメントへの返信などを行います。
ソーシャルメディア運用代行では、以下の初期費用が必要です。
・インターネットやWi-Fiの通信費
・パソコンやスマホの購入費
・作業スペースの賃料(自宅で事業を行う場合は不要)
起業にかかる費用の目安は、10万円〜20万円です。パソコンやインターネットなどの環境が揃っており、自宅で起業する場合は、0円での起業も可能でしょう。SNSの操作が得意な方だけでなく、情報収集が好きな方や、流行に敏感な方にもおすすめの仕事です。
起業資金が不足しているときの対策

理想とする事業やビジネスモデル、売りたい商品が決まっていても、具現化するには資金が必要です。中には、資金が足りず、どのように工面すれば良いか悩む方もいるでしょう。ここからは、起業資金が不足しているときの対策について、以下の7つを紹介します。
・融資を検討する
・副業で資金を増やす
・助成金や補助金を活用する
・初期費用を抑える
・個人事業主から始める
・在庫を抱えないビジネスモデルにする
・専門家によるアドバイスやサポートを受ける
内容について、くわしく解説します。
融資を検討する
手っ取り早く多額の資金を調達するなら、融資の検討がおすすめです。融資には、金融機関からの借入や、日本政策金融公庫が実施する創業融資など様々な種類があります。中でも創業融資は、預貯金などの自己資金がなくても申し込みが可能です。
ただし、融資額が少なくなったり、審査が厳しくなったりするなどのデメリットもあります。融資を希望する際は、事業規模や業種、自己資金の有無などを考慮して、自分に合った融資制度を選ぶことが大切です。以下の記事では、融資についてくわしく解説しています。
関連記事:女性起業家は自己資金なしでも融資を受けられる?融資以外で資金調達する方法とスムーズに起業するための対策
副業で資金を増やす
サラリーマンなどの本業をしながら、副業で稼ぐ方法もおすすめです。副業から始めることで資金面以外にも、以下のメリットが得られます。
・スキルや必要な知識が身につく
・人脈が構築できる
・本業収入もあるので事業が継続しやすい
副業で培ったスキルや人脈は、起業後にも活かせます。また、事業が軌道に乗るまでは時間がかかり、金銭面でストレスを抱えることも珍しくありません。副業から始めれば、本業収入も得られるため、収入が少ない間も安心して事業を行うことが可能です。
事業が軌道に乗り、資金が増えたタイミングで起業することもできるため、資金を増やしながら起業を目指したい方は、副業から始めてみましょう。
助成金や補助金を活用する
助成金や補助金は、国や自治体が掲げる政策目標に合致する事業者に対して支給するお金のことです。融資と混同されやすいですが、融資との大きな違いは、原則的に返済が不要なことです。国や自治体が掲げる政策に関連した事業を行う場合は、利用を検討してみましょう。
また、助成金や補助金には、審査があるため、事業計画書などの書類の準備が必要です。制度の概要や支給金額、必要書類などについては、国や自治体のホームページで確認してみましょう。
初期費用を抑える
事業に必要な機材などが高額な場合、自宅にある物を使ったり、レンタルサービスを活用したりすることで、初期費用を抑えられます。他には、少人数で規模の小さい事業を行うスモールビジネスの検討もおすすめです。初期費用が抑えられれば、低リスクで起業できるでしょう。
また、初期費用や事業に必要な資金の見積もりが適正かを判断するには、事業計画書の作成が大切です。事業計画書とは、頭の中にあるビジネスを言語化してまとめた書類です。事業で必要な支出や売上の見積もりができるため、資金不足について精度の高い予想ができます。
事業計画書の作成については、以下の記事で紹介しています。作成されていない方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:事業計画書のスムーズな作り方とは?わかりやすい方法を解説
個人事業主から始める
先ほどもお伝えした通り、個人事業主の開業手続きは0円でできます。そのため、資金が不足している場合は、法人よりも低資金で起業できる個人事業主がおすすめです。
また、社会的信用などを考慮して法人を設立したい方もいるかもしれません。そのような場合は、事業が軌道に乗ってから法人へ変更する「法人成り」の手続きを取ることも可能です。
ただし、法人成りには、適切なタイミングがあります。タイミングを誤ると、多額の税金が発生するなどのデメリットが生じるので注意しましょう。以下の記事では、法人成りについてくわしく解説しています。
関連記事:法人成りとは?手続きの流れと必要な準備・費用について解説
在庫を抱えないビジネスモデルにする
在庫を抱えないビジネスモデルでは、仕入れなどの初期費用を抑えられるだけでなく、在庫リスクがないと言ったメリットがあります。在庫リスクとは、商品が売れ残ることで生じる商品価値の低下や、保管コストの増加などを指し、キャッシュフローが悪化する原因にもなります。
しかし、在庫の過剰削減は、納品までに時間がかかるなどのデメリットが生じるのも事実です。起業の際は、アフィリエイトや動画編集のような、在庫を持たないビジネスモデルを検討してみましょう。
関連記事:40代が独立開業しやすい仕事の条件は?低資金で開業できる仕事と失敗しないためのポイント
専門家によるアドバイスやサポートを受ける
融資や補助金の申請では、書類の作成などで専門的な知識が必要なことも多いため、思うように手続きが進まないこともあるでしょう。融資や補助金の申請については、専門家に相談し、アドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
専門家への相談では、以下のメリットが得られます。
・融資や補助金の審査が通過しやすくなる
・実情に合った融資制度を教えてくれる
・資金調達がスムーズで早く起業できる
資金調達の代表的な専門家には、税理士が挙げられます。税理士には、融資や補助金の申請を支援してきた経験やノウハウがあるため、サポートが得られれば、資金が調達しやすくなり、スムーズな起業が可能です。
当事務所でも、資金調達に関するご相談が可能です。お電話でも受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
関連記事:企業の成長が加速する税理士の選び方は?依頼する目的から選ぶ税理士の選び方とポイント
起業資金の悩みは気軽に相談を!
起業資金の目安は、個人事業主や法人などの起業形態や、業種によっても異なります。自宅にある物を使うなど、条件が揃えば0円での起業も可能でしょう。
しかし、起業に必要な資金は、手続きにかかる費用や機材などの購入費だけではありません。事業が軌道に乗るまでには時間がかかるため、運転資金の準備も必要です。資金不足が生じると、事業の継続が困難になる恐れがあるため、十分な資金を確保しておきましょう。

起業資金のお悩みは当事務所へお任せください。当事務所では、200社以上の創業支援経験があります。融資や補助金などの支援も得意としており、スムーズな資金調達が可能です。お電話でもご相談できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。