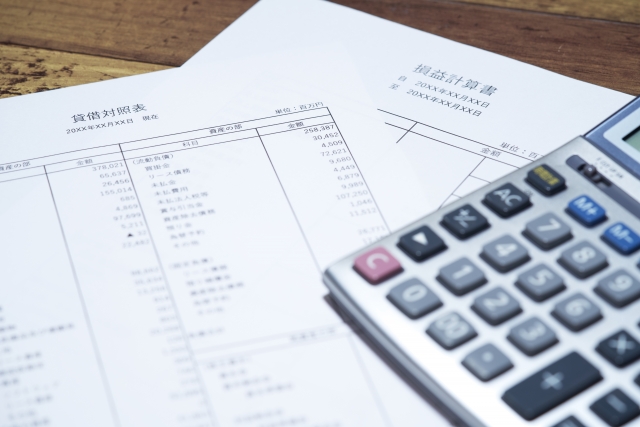インボイス制度後の個人からの仕入れの概要

インボイス制度を簡単に説明すると、インボイス(適格請求書)でやりとりを行うことです。インボイスを発行できるのは、税務署に登録しているインボイス発行事業者のみです。免税事業者ではインボイスを発行できません。
ここからは、インボイス制度における個人からの仕入れの概要を解説します。
原則として仕入税額控除ができない
消費税は消費者の代わりに事業者が負担して納めますが、仕入れや流通する中でも消費税は発生しています。それぞれが受け取った消費税を納めた場合、1つの商品に対して重複して消費税を納めることになってしまいます。
そのため、消費税を納めるときの計算では、消費者から受け取った消費税の金額から「仕入税額控除」という、仕入れなどで支払った消費税の金額を差し引く仕組みがあります。仕入税額控除によって、消費税の重複を避けることができ、納付額も抑えられるのです。
しかし、インボイス制度の開始に伴い、仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存が必須となりました。インボイスに対応していない個人からの仕入れでは、仕入税額控除が受けられないため、消費税の納税額が増えてしまい、利益の減少に繋がるのです。
インボイスの有無における消費税への影響は、後ほど行うシミュレーションにてくわしく解説します。
参考:国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」
帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられるケースがある
原則的に仕入税額控除を受けるにはインボイスでの取引が必要です。しかし、請求書等の交付を受けることが難しい場合などの以下のケースでは、帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けることが可能です。
・3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
・インボイスの記載事項が記載された入場券等が使用の際に回収される取引
・古物営業を行う者がインボイス発行事業者でない者から古物の買い取る取引
・質屋がインボイス発行事業者でない者から質物を取得する取引
・宅建取引業者がインボイス事業者でない者から建物を購入
・インボイス発行事業者でない者から再生資源や再生部品を購入
・3万円未満の自動車販売機や自動サービス機から商品を購入
・郵便切手類のみを対価とした郵便・貨物サービス
・従業員に支給する通常必要と認められる出張費
また、帳簿の保存では、原則的に以下などの内容について記載が必要です。
①仕入先の氏名や住所(名称や所在地)
②課税仕入を行った年月日
③仕入れた資産や役務の内容
④支払対価の金額
⑤帳簿のみの保存で認められる仕入れに該当する旨
仕入税額控除について、帳簿の保存のみで適用するケースでは、「3万円未満の自動販売機による飲料の販売」など、総勘定元帳の摘要欄に帳簿の保存のみで良いとする理由を記載しましょう。
参考:国税庁「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」
インボイスがない個人から仕入れた時の対処法

インボイスがない個人からの仕入れの場合、どのように対処すれば良いか悩む方も多いでしょう。インボイスがない時の仕入れでは、主に以下の対応を行うことになります。
・経過措置による一定割合の仕入税額控除を適用する
・少額特例に該当するか検討する
内容をくわしく解説します。
2029年9月30日までは経過措置がある
インボイス制度後の激変緩和の対応として経過措置が設けられています。2029年9月30日までは免税事業者などの個人からの仕入れについては、以下の割合で仕入税額控除を受けることが可能になりました。
|
期間 |
割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の8割控除 |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の5割控除 |
上記の期間では、割合に応じた仕入税額控除を受けることができますが、仕入れについて経過措置の適用対象とするには、以下の要件を満たす必要があります。
・仕入先から受領した区分記載請求書等の保存
・帳簿に経過措置の適用を受ける(8割または5割の控除を受ける仕入れである)旨の記載
区分記載請求書等とは、インボイス開始前に適用されていた請求書で、軽減税率の対象となる品目などが記載されています。しかし、インボイス制度の開始によって、仕入税額控除には、区分記載請求書ではなく、適格請求書が適用されることになりました。
経過措置の期間内は、インボイスに適用されていない区分記載請求書でも、仕入税額控除を受けることが可能です。ただし、経過措置終了後に仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要なので知っておきましょう。
また、期間によって経過措置の割合が変動する点や、書類や帳簿の保存方法が定められている点には注意が必要です。
参考:日本税理士連合会「インボイス制度実施に当たっての経過措置について」
少額特例に該当するか検討する
税込1万円未満の仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられます。この対応は少額特例といわれ、2029年9月30日までの措置です。
インボイス発行事業者ではない免税事業者からの仕入れでも、帳簿への記載だけで仕入税額控除を受けることができます。ただし、少額特例の適用を受けられるのは、「基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1億円以下」または「特定期間の課税売上高が5,000万円以下」の事業者に限ります。
消費税の確定申告書から課税売上高を確認できるので、少額特例に該当するか検討してみましょう。
参考:国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」
個人から仕入れた時の消費税に与える影響

インボイスがない仕入れの場合、消費税にどれくらい影響するのか気になる方も多いでしょう。ここからは、インボイス発行事業者から仕入れるパターンと、免税事業者である個人から仕入れるパターンについて、以下のケースを想定し、消費税の納付額を比較します。
・販売した商品は税込み220万円
・仕入れで支払った金額は税込み110万円
・消費税の税率は10%
・1つの商品が売れたときの消費税額を計算する(原則課税)
・免税事業者などの仕入では経過措置を適用し、仕入税額控除の計算は積み上げ計算を採用
*計算結果をわかりやすくするため実際の計算方法とは異なります。
【①インボイス発行事業者から仕入れを行った場合】
インボイス発行事業者からの仕入れでは、仕入れで支払った消費税を控除して消費税を納付します。事業者の消費税の納付額は、以下の計算で求められます。
|
20万円(売上で受け取った消費税)- 10万円(仕入税額)=10万円(納付額)…① |
【②免税事業者などの個人から仕入れを行い、経過措置8割控除を適用した場合】
経過措置の適用を受けるときは、割合に応じて仕入税額を求めなければなりません。経過措置の場合は、請求書の金額に以下の数字を乗じて仕入税額を算出します。
|
110万円 × 10/110 × 80/100 =8万円(仕入税額) |
事業者が納める消費税の金額は、以下の計算で求められます。
|
20万円(売上で受け取った消費税)- 8万円(仕入税額)=12万円(納付額)…② |
【インボイス発行事業者と個人を比較したときの消費税の納付額】
2つのパターンを比較し、消費税の納付額にどれくらいの差が生じたか確認します。
|
インボイス発行事業者から仕入れたパターンでの消費税の納付額…① |
100,000円 |
|
免税事業者などの個人から仕入れたパターンでの消費税の納付額…② |
120,000円 |
|
①と②の差額 |
20,000円 |
インボイス発行事業者から仕入れた場合、消費税は20,000円の節税になったことがわかりました。今回は1つの商品に対しての消費税を計算しているため、商品の売上数が増えれば、金額にかなりの差が生じることが予想できます。
ただし、あくまで一例です。個人の仕入れによる自社への影響を把握するには、実情に合った計算が必要です。石黒健太税理士事務所では、自社に合わせたシミュレーションや節税対策のご提案を行っています。お電話でもご相談可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
個人との取引が継続するときの対策

今後も個人からの仕入れが必要な企業も多いでしょう。しかし、個人との取引では事務負担が生じたり、消費税に影響が出たりすることも事実です。個人との取引が継続するときは、以下の対策を取ることで、事務負担の削減や、消費税の納付額の負担を抑えることが可能です。
・取引の都度精算する
・インボイスが発行できる取引先を探す
・簡易課税制度を検討する
内容を詳しく解説します。
取引の都度精算する
税込1万円未満の仕入れでは、帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができる少額特例があります。そのため、月単位の購入ではなく都度購入にするなど、取引方法を変更し、取引の都度精算とすることで少額特例が適用される可能性が高くなります。
例えば、3,000円と9,000円の商品(合計金額12,000円)を同時に購入した場合、1万円以上のため少額特例は適用できません。しかし、3,000円と9,000円の商品を別々に精算した場合、それぞれの取引が1万円未満となるため、少額特例が適用されます。
少額特例が適用されれば、仕入税額控除により消費税の納付額を抑えることが可能です。しかし、都度精算によって、帳簿の仕訳や支払・精算業務などの事務手間が増えるといったデメリットが生じます。
都度精算を行うかの決定は、事務負担と節税効果を比較して検討する必要があるでしょう。
関連記事:国税庁「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位」
インボイスが発行できる取引先を探す
インボイスが発行できる取引先から仕入れを行い、仕入税額控除を受けるといった対策もあります。新規取引先などは、取引前にインボイス発行事業者か確認するといいでしょう。
取引先に直接確認する方法以外に、インボイスが発行できる取引先を探す手段としては、国税庁が運営する「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で調べる方法があります。
また、法人の場合、インボイス発行事業者の登録番号は法人番号が使用されるのが一般的です。そのため、インボイスの登録番号が不明な場合は、国税庁が運営する「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索し、インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで確認すればインボイス発行事業者かどうかがわかります。
また、インボイスが発行できる個人を探す場合は、インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトのページ「公表情報ダウンロード」を参考にすると良いでしょう。こちらのページでは、前月末時点で登録があるインボイス発行事業者の情報をダウンロードできます。
ダウンロードしたファイルに所在地などのフィルターをかけて検索を行うことで、取引先候補に最適な個人を探すことが可能です。
簡易課税制度を検討する
簡易課税制度とは、消費税における事務負担を削減するために設けられた制度です。簡易課税制度における消費税の計算は以下の通りです。
|
消費者から受け取った消費税 - 消費者から受け取った消費税×みなし仕入率 = 消費税の納付額 |
上記の計算は、課税期間で集計して行います。そのため、原則課税のように仕入れごとに消費税の計算を行う必要がなく、経理担当者の事務負担の削減が可能です。
また、業種ごとの割合に応じた仕入税額控除の適用を受けられるため、相手が個人でもインボイス発行事業者であっても消費税の計算に影響が生じないのは最大のメリットといえます。ただし、業種ごとに割合が異なる点や、適用には条件がある点には注意が必要です。
簡易課税制度を適用できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られ、事前に税務署への届出が必要です。
関連記事:簡易課税制度選択届出書の提出期限はいつまで?出し忘れた場合の対策と簡易課税を選択する前の注意点
インボイスの悩みは気軽にご相談を!
インボイスが発行できない個人からの仕入れでは、経過措置や少額特例などを利用して仕入税額控除を適用し、消費税の負担を抑えることが大切です。しかし、経過措置などは期間が設けられているため、個人との取引が継続するときは取引方法を変更するなどの対応が必要です。

石黒健太税理士事務所では、インボイスや消費税についてのご相談を承っています。企業の実情に沿った節税対策や、イレギュラーなケースにおける対応策などもご提案可能です。お電話でもご相談を受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。


 らの仕入れで気を付けないといけないポイントはある?」インボイス制度後は、仕入れ先から受け取った請求書がインボイスではない場合、原則的に仕入税額控除が適用できません。
らの仕入れで気を付けないといけないポイントはある?」インボイス制度後は、仕入れ先から受け取った請求書がインボイスではない場合、原則的に仕入税額控除が適用できません。